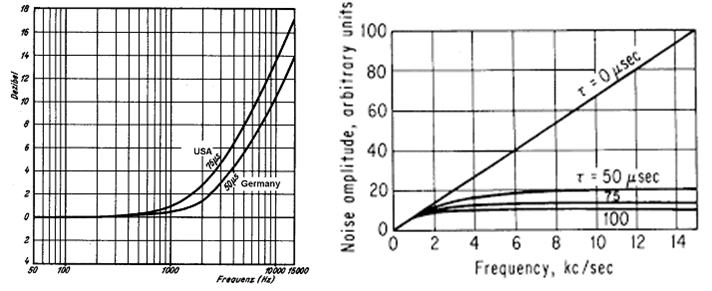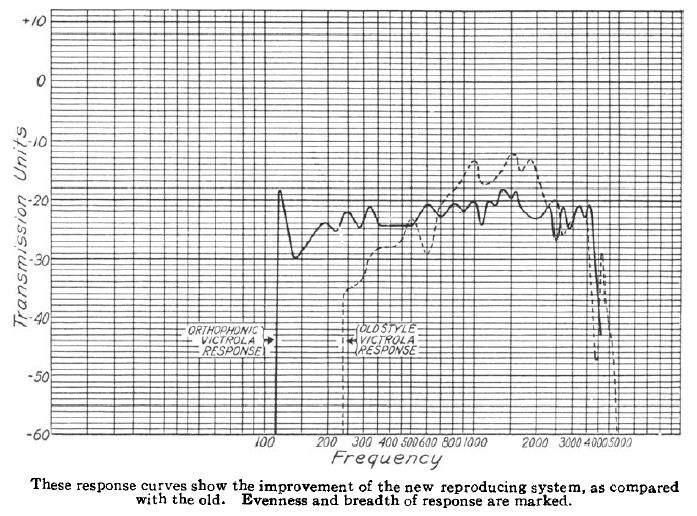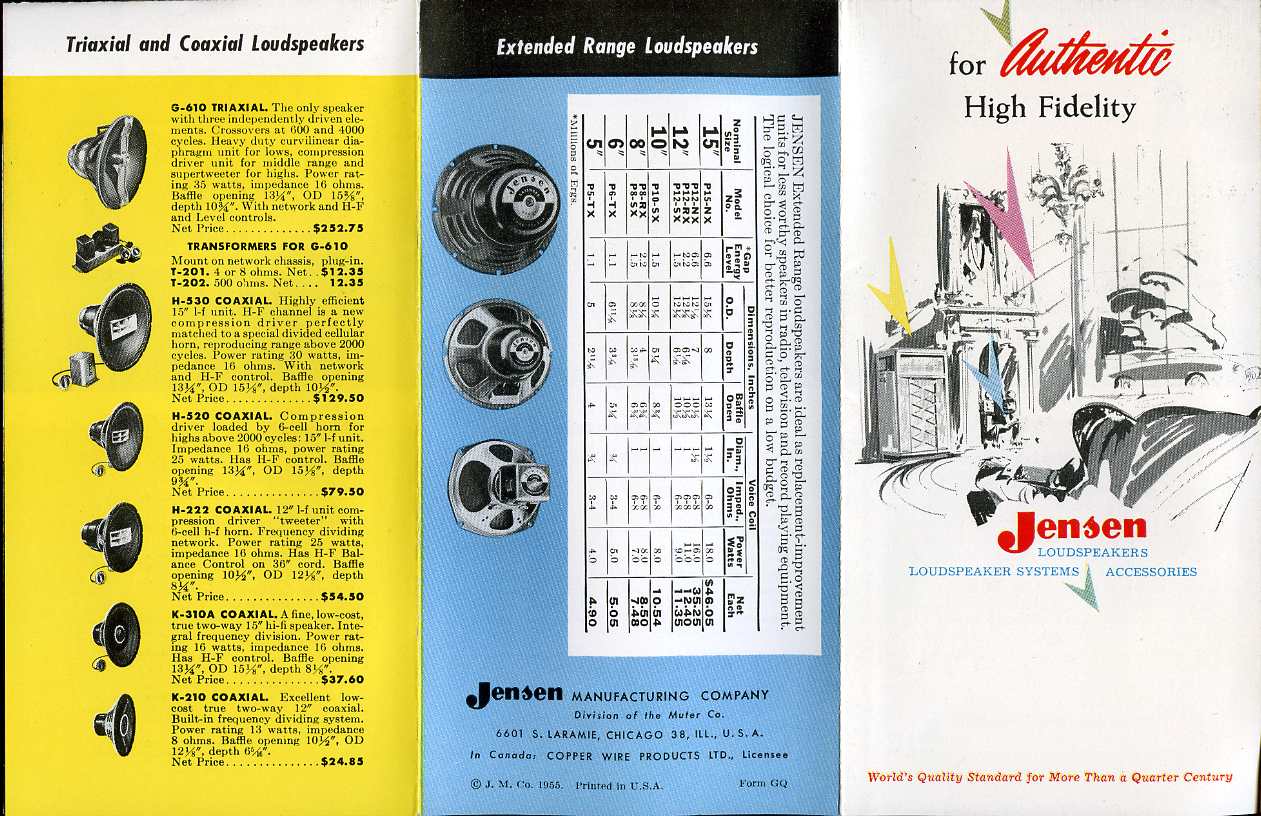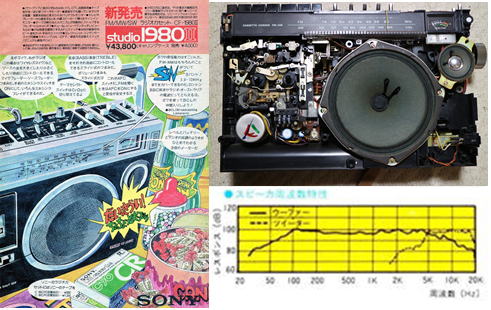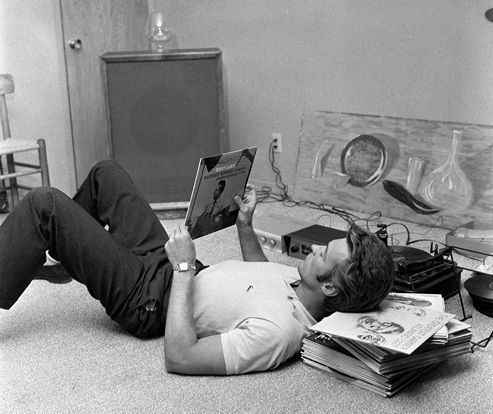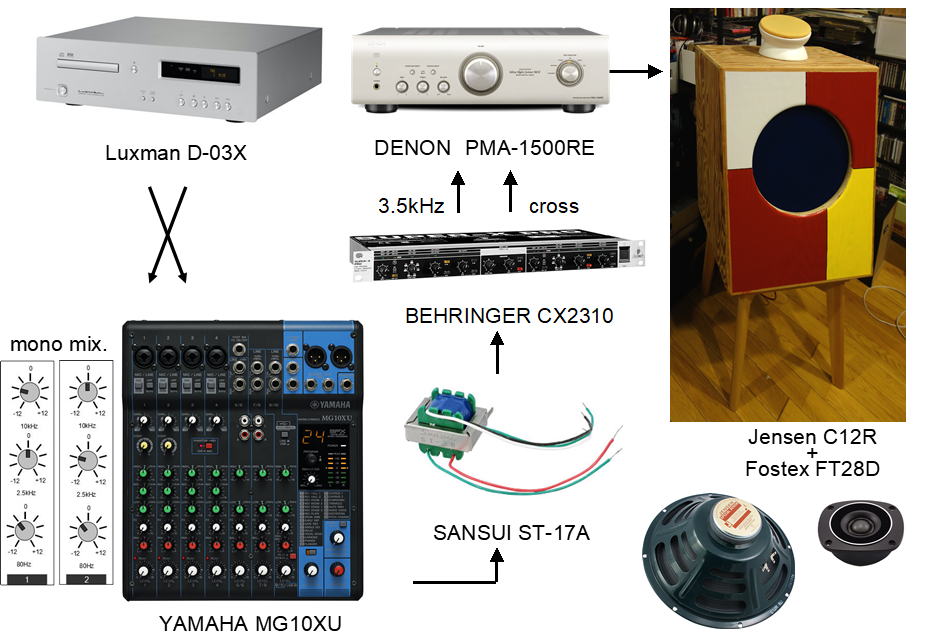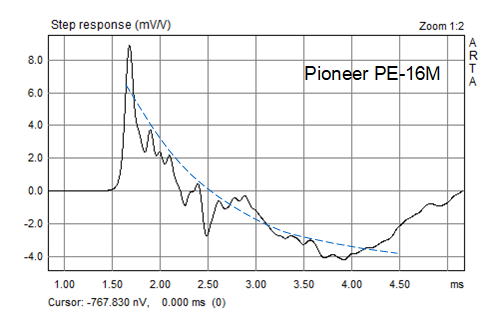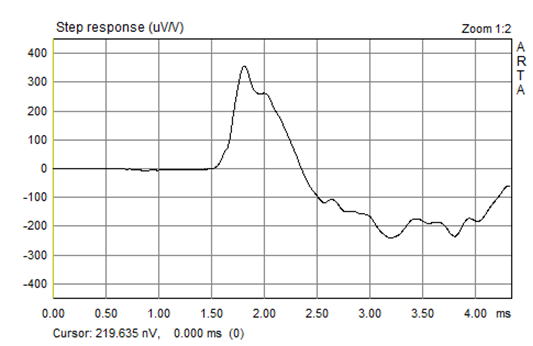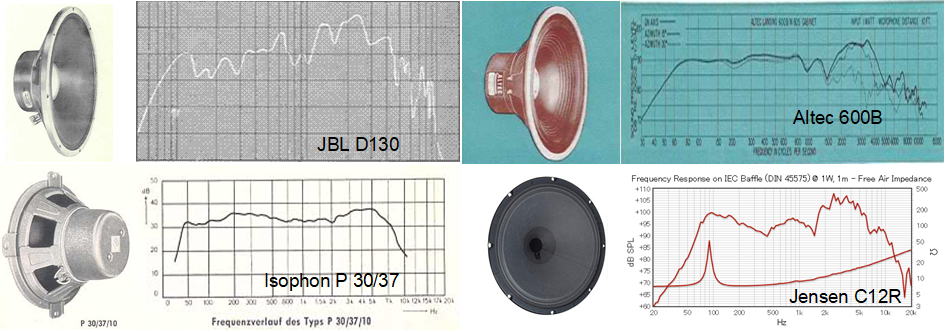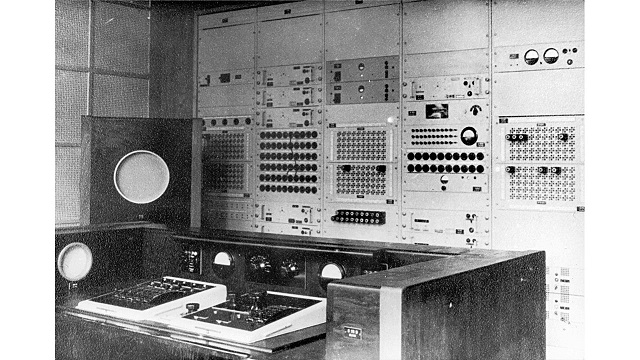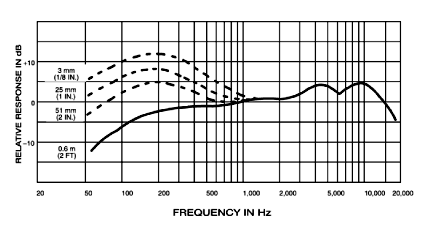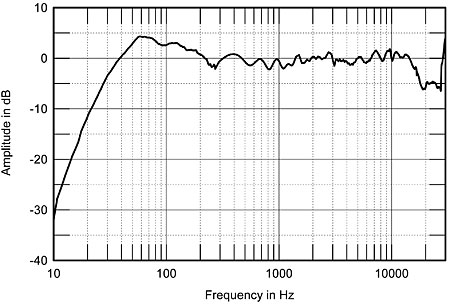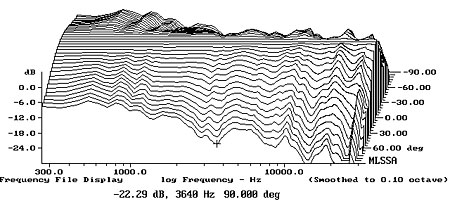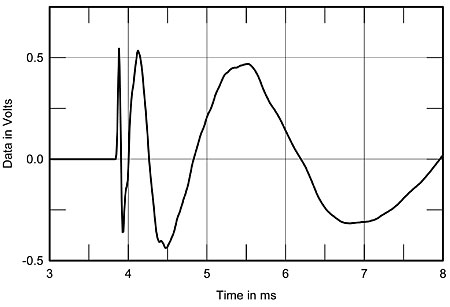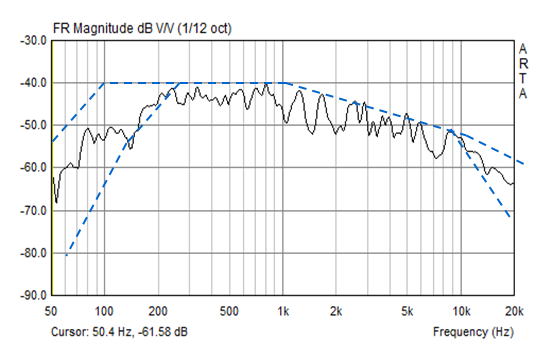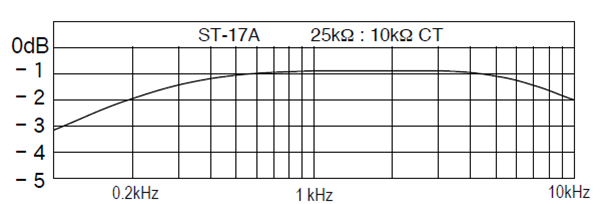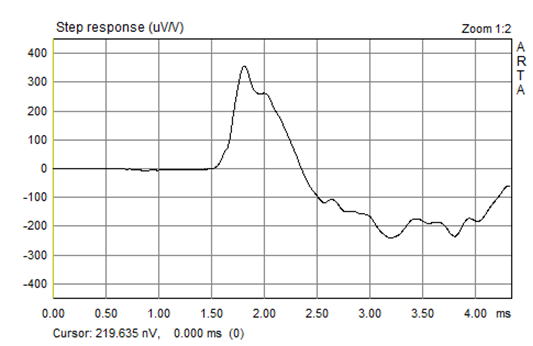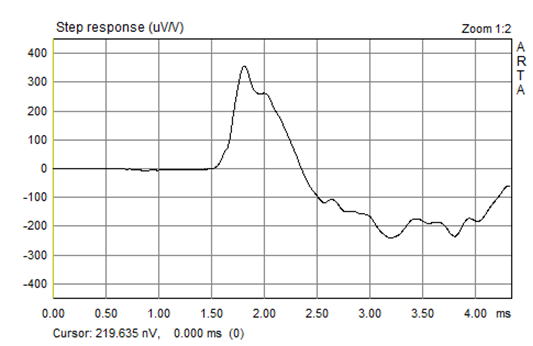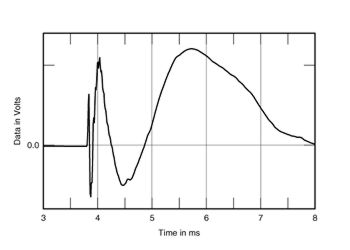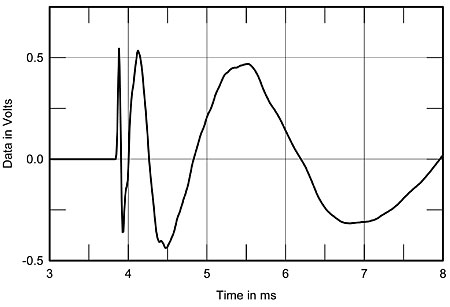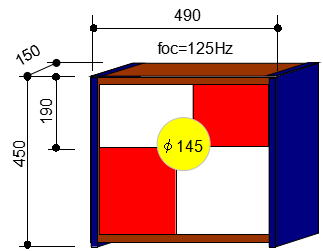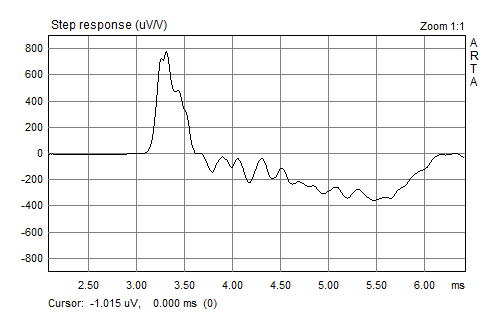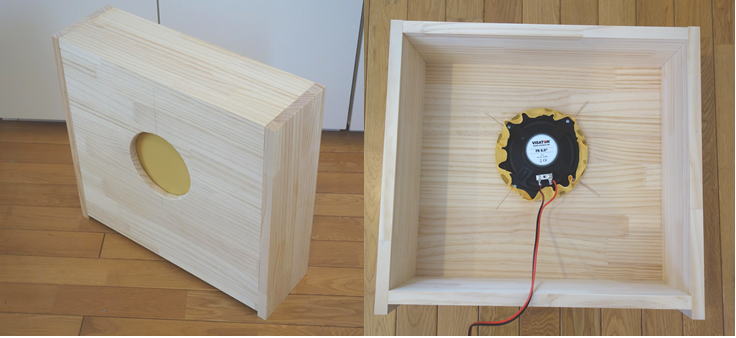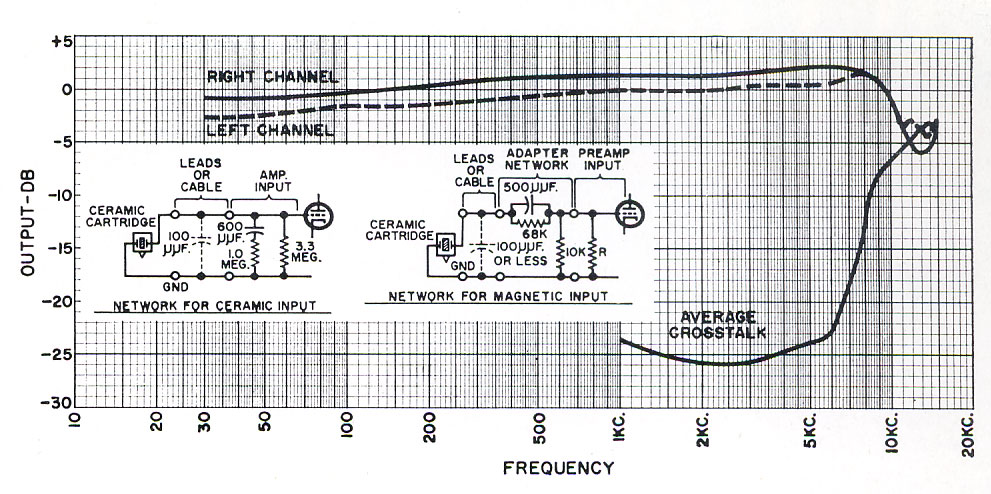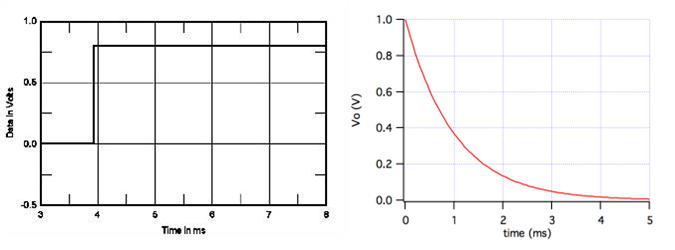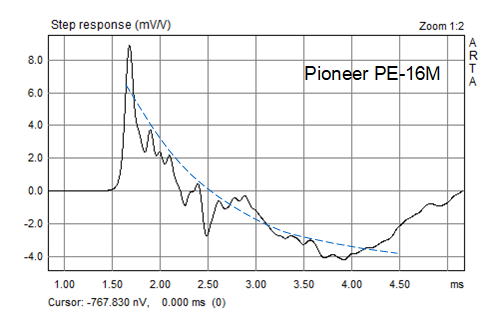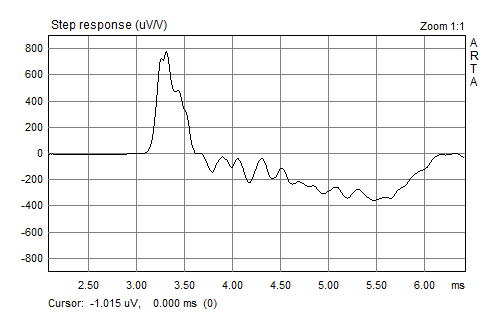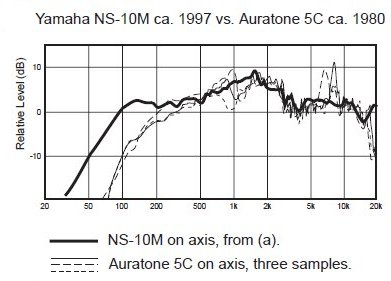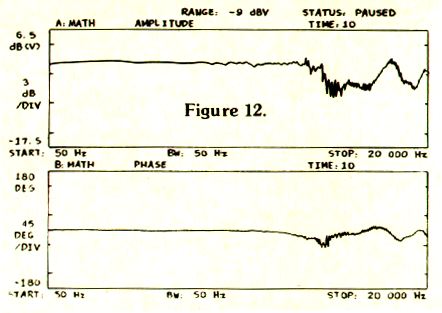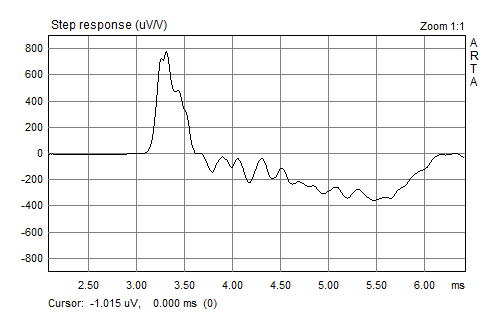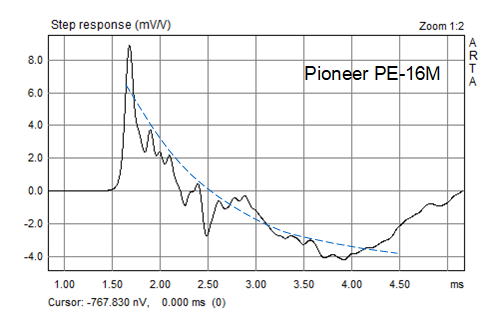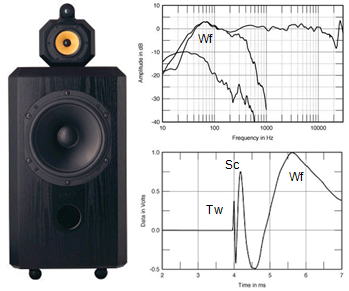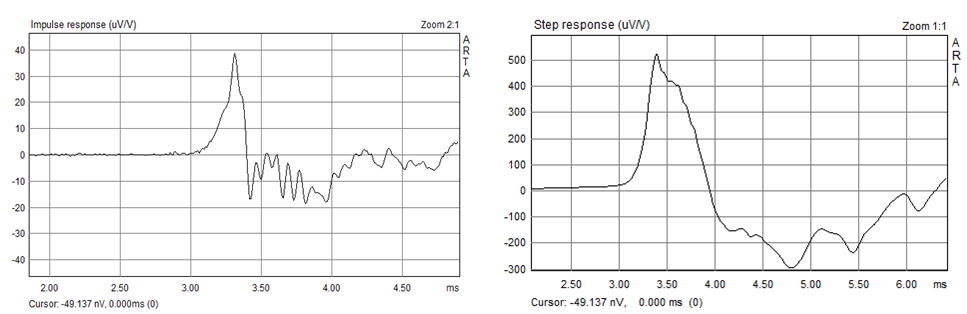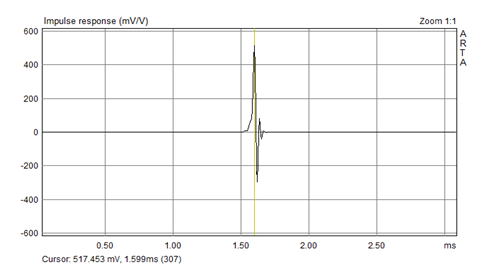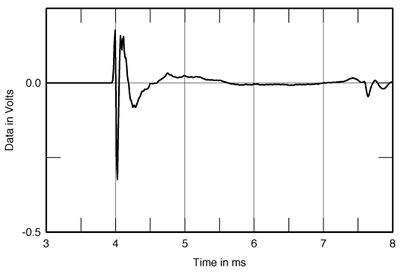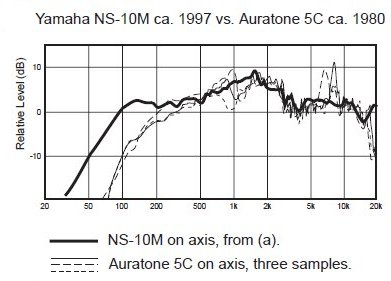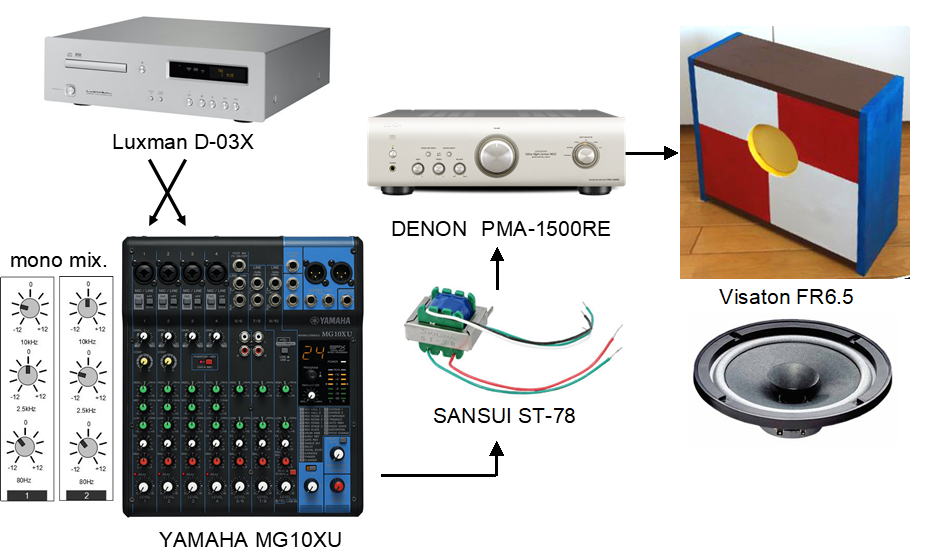���m�����Ƃ�
1ch�Ƀ~�L�V���O���ꂽ�����̂���
�X�s�[�J�[1�{�ʼn��y������
�X�e���I�Ȃ�Ėʓ|���������̂̓�����
���y��S���炽�̂�����
���m�����̓��m�N���Ǝ��Ă���
�Ƃ����̂�1950�N��܂ňꏏ�ɉ߂���
�I�[�f�B�I�̓X�e���I�ɁA�J�����̓J���[�ɂȂ�������
�ł������Â������ł͂Ȃ�
���m�N�������̃R���g���X�g�ʼnA�e��[�߂�悤��
���m���������y�̍\�������m�ɂ����
�y���m���������nj�Q�z
�l�ɂ���ďǏ�͂܂��܂�����
����������m�����^���������ł����郄���f���Ǘ�B
���}�X�^�[�S���ǁj
�@���}�X�^�[�Ղ̕ҏW���j���ς�邽�т�
�@�����������đO��Ƃ̈Ⴂ�ɂ��Ĕᔻ��������B
�@�ҏW���j���ς�������烊�}�X�^�[�������Ƃ�f���Ɏ~�߂Ȃ��B
�}�g���N�X���ǁj
�@�I���W�i��LP�ƌĂ�鏉���v���X�Ղɂ���
�@�Վ����W�Ȃ��D�ʐ��������������B
�@���܂��ɂ̓}�g���N�X�ԍ��𗅗ĉ��ɎT���B
�C�R���C�U�[���`�ǁj
�@�C�R���C�U�[�J�[�u�̈Ⴂ��
�@�V�n���Ђ�����Ԃ������̂悤�ɘb��������B
�@���ꂪ�K�i�̖�肾�Ƃ���ւ�
�@�^���̐l�H�I�ȉ��ςɂȂ��邱�Ƃ�F�����Ă��Ȃ��B
SACD�ˑ��ǁj
�@���ł�SACD�ɂ���Ή����ǂ��Ȃ�Ǝv�������
�@�����ĕ֗���CD�ł̃����[�X���o�J�ɂ�������B
�@�ǂ�����j���[�g�����ȋL�^�}�̂ł�����
�@��{�͓������e�Ƃ������Ƃɕ������������Ȃ��B
�y���m�����������J�߁z
���m�����Ƃ������t�������Ґ���������c���f�������B
���m�����E�n���X�����g�j
�@���r���[�ɘ^���̗��j�I�Ӌ`��\�ِ���Ȃ���
�@�u���m�����Ȃ̂Ŏc�O�v�ƌ��܂蕶��������B
���[�t�@�C�E�n���X�����g�j
�@�Â��^��������~�j�R���|�ŏ\���ƐM�������
�@�����̑��u�̍Đ��o�����X���������ƂɋC�t����
�@�u�^�����Â��̂ʼn��������v�ƈ��Ԃ����B
�f�W�^���E�������E�n���X�����g�j
�@���m�����������w�b�h�z�������
�@�c�݂�G�����ڗ������蓪����ʂƂȂ邱�Ƃ����m�炸��
�@�u�m�C�Y���Ђǂ��v�u�����܂��ĕ�������v�Ȃ�
�@������]�����������ŏ������ށB
�p�F ���m�����E�X�s�[�J�[�ł͉��ꊴ���o�Ȃ��̂ł́H
�`�F ����̎w�����������X�s�[�J�[�𐳖ʂ��璮���Ɖ��ꊴ�͏o�܂���B
�@�@�����̃X�s�[�J�[�̓`�����l���Z�p���[�V�������҂�����
�@�@��������30�����x�̎w���������Ȃ��A�E�[�n�[�̕Ȃ��o�₷���Ȃ�܂��B
�@�@�w�����̍L���X�s�[�J�[�������ς��ɖ炵�Ď߉����璮���܂��傤�B
�p�F ���m�����E�X�s�[�J�[�͑傫���ق��������̂��H
�`�F ����a�̃G�N�X�e���f�b�h�����W�����ቹ���璆�����܂�
�@�@�������j���[�g�����ŗǂ��ł��B�@
�@�@����a�E�[�n�[�͏d�ቹ���o�����߂ɃR�[�������d���������̂������A
�@�@�g�`�̗����オ�肪�݂����߁A�Â��^���őf���ɘ^��ꂽ�ቹ��
�@�@�G�b�W���������s���C���ɂȂ�₷���ł��B
�@�@�����a�E�[�n�[�͂����Ɣ������݂��A�G���N���[�W���[�̋�����
�@�@�҂��Ȃ���Βቹ���o�Ȃ��̂ŁA���肵���s���R�Ȓቹ�ŁA
�@�@���傫�ȉ��ʂłȂ��Ɣ������܂���B
�@�@���m�����^���͍���ɘc�𑽂݂��܂ނ��߁A���̃o�����X�̓C�^�`�������ɁB
�@�@�����W�̋������m�����^���ɍ������E�[�n�[��I�Ԃׂ��ł��B
�p�F ��^�z�[������Ԃ悭�Ȃ����H
�`�F ���m��������ɍł��ґ�Ȏd�l�̓g�[�L�[�p�̑�^�z�[���ŁA
�@�@������̐��\�͐܂莆�t���ł��B�悭�L�������ő剹�ʂŒ�������
�@�@�Ǝv�������ł����A���j�A�j�e�B�������̂ŏ����ʂł����Ăɖ�܂��B
�@�@����ŁA����ɑΉ�����y���R�[���Ŕ����̗ǂ��E�[�n�[��
�@�@�ꕔ�̃��v���J�i�������Č��݂ł͐�������Ă��炸�A
�@�@�r���e�[�W���ŏ�Ԃ̗ǂ����̂�{���ȊO�ɕ��@������܂���B
�@�@�����Ɠ���̂������R�[���̑���a�E�[�n�[�͎��C�ʼn������ς���
�@�@�i�ቹ�̐L�т�����̉��������Ȃ�j�̂ŁA���{�̂悤�ɍ��������̋C���
�@�@���Ȃ�C��t���Ȃ��Ɩ{���̐��\���ł��܂���B
�@�@����Ƃ͋t�Ƀz�[���h���C�o�[�̂ق��͋����_�C���t�����Ȃ̂ŁA
�@�@�������Ă������͕ς�炸�o�����X�����Ȃ��̂ł��B
�p�F 20cm�̃t�������W����ԃo�����X���ǂ��̂ł͂Ȃ����H
�`�F Hi-Fi�����ɐ������ꂽJBL L8T�AWE 755A�Ȃǖ��샆�j�b�g������A
�@�@���݂ł����z�Ŏ������Ă��܂��B
�@�@�ŋ߂ɂȂ�_�u���R�[���ō��\���ȃ��j�b�g�����B����A������Ă��܂����A
�@�@���ӂ��ׂ��Ȃ̂�Qts=0.4�ȉ��̃o�X���t�������̂��̂��قƂ�ǂŁA
�@�@�ӊO�ɑ傫���Ă������肵���G���N���[�W���[���K�v�Ȃ��Ƃł��B
�@�@�̂�Siemens��SABA��20cm�t���������W�̂悤�Ɍ�ʉ�����ɓ���Ă�
�@�@�u���u���k���邾���Œቹ�͏o�܂���B
�@�@���j�b�g�̓����ɍ���������I�Ԃ��Ƃ��ǂ��o�����X�ݏo���܂��B
�p�F �����a�̃t�������W�����m�����Œ����Ƃǂ����낤���H
�`�F 8�`12cm�̃t�������W�͉��i���荠�ŁA�ቹ���獂���܂Ńo�����X�悭��܂��B
�@�@����ŁA���݂̃t�������W�̓X�e���I�Đ��p�ɐv����A����̎w������
�@�@�X�����_�[�ɂ��Ē�ʊ���ǂ��o���悤�ɂ��A���ɒ��̓G���N���[�W���[��
�@�@�����ŕ⊮����̂ŁA��ݍ��ނ悤�ɏ_�炩�������ŏo�Ă��܂��B
�@�@���̍���A�ቹ�̑g�����́A�X�e���I�ł̃T�E���h�X�e�[�W�̍Č��ɂ�
�@�@�ǂ���p����̂ł����A���m�����ɂȂ�ƍ��悪�^�C�g�ŋߐړI�Ȃ̂ɁA
�@�@�ቹ���ɂ��ĉ��肷��ȂǁA���F�̕Ȃ��o�₷���Ȃ�܂��B
�@�@���g�����������łȂ��A���F��^�C�~���O�ɂ����������Ă݂܂��傤�B
�p�F���m�����X�s�[�J�[�p�Ƀ��m�����A���v���ǂ��̂ł́H
�`�F���ݐ�������Ă郂�m�����A���v�͑�^�X�s�[�J�[�����̍����i���嗬�ł��B
�@�@�`�����l���f�o�C�_�[����āA���ʂ̃X�e���I�v�����C�������m�����̃}���`�A���v
�@�@�Ƃ��Ďg�p����ƈ�Γł��B
�p�F���m�����X�s�[�J�[���}���`�A���v�Ŗ炷�����b�g�́H
�`�F�l�b�g���[�N��H�̕��ׂ��Ȃ��̂ŁA�A���v����X�s�[�J�[�֑f���ɓd���𑗂�
�@�@���Ƃ��ł��܂��B�܂��l�b�g���[�N�E�t�B���^�[�̌����͈͂ł̃X�s�[�J�[��
�@�@�ʑ��̂˂��ꂪ�N���ɂ����ł��B
�@�@�`�����l���f�o�C�_�[�Ŏ��g���o�����X�����Œ����������Ȃ��l�́A
�@�@�܂��t�������W�ō����ƒቹ�̃o�����X�Ɋ���Ă��������B
���m���������̓��m����LP�����̐��E�ł͂Ȃ�
�X�e���I�����ă��m�����Ƀ~�b�N�X�������
���m���������ɂ͈ȉ��̓��T������B
1)�X�e���I���ƕLj�ʂ�苒���邪�A���m�������ƈ֎q��l���ł����܂�B
2)���m�����͎����ʒu�����R�B�Q���]�����Ē����Ă������B
3)���m�����ɂ��邱�ƂŁA���y����l�̂̃p�[�\�i���e�B���m���ł���B
4)���m�����ł̓h�������O�ʂɏo�Ă��ă|�b�v�X���v���[���X�������Č������B
�X�e���I�����̃��m�����E�~�b�N�X�@����1�j
��ԒP���Ȃ̂�2ch����s�Ɍ�������1ch�ɂ܂Ƃ߂���̂ŁA
��ʓI�ɂ͗ǂ��s���Ă����B�������A���̕��@�̌��_�́A
�z�[���g�[���̋t���������S�b�\���ł�������邱�ƂŁA
����̕s�����������̂Ȃ����ɂȂ�B
�����̃��m���������ւ̈��]�́A�ނ���X�e���I�^����
���m�����Œ����Ƃ��́A�c�������̗ɂ��B
�X�e���I�����̃��m�����E�~�b�N�X�@����2�j
�r���e�[�W�E�I�[�f�B�I���D�Ƃɐl�C������̂��A
�v�b�V���v�������g�����X���t�ɐڑ����āA2ch���܂Ƃ߂��@�ŁA
�������̌덷�̂����肪�ǂ����~�ɂ����܂�ƁA�܂�₩�ȃ��m�����ɂ�������B
�������A������v�b�V���v�������p�g�����X���̂���O�ɑk��Â��������Ȃ��A
���̃R���f�B�V�������܂��܂��ŁA������N�W�������܂�1��5�`10���~������
�g�����X��������������������Ȃ���Ȃ炸�A���ʂ̐l�ɂ͂����߂ł��Ȃ��B
�X�e���I�����̃��m�����E�~�b�N�X�@����3�j
�^���p�~�L�T�[���g�����@�ŁA2�����̍��搬����
�C�R���C�U�[�Ō݂��Ⴂ�Ƀ��x�������o���č������邱�ƂŁA
�̂̋^���X�e���I�̋t�����������ł���B
�u�t�^���X�e���I���������v�Ƃł����t���Ă������B
���ꂾ�Ə��ʂ��ߕs���Ȃ��܂Ƃ܂��āA����̏����������Ȃ��B

���m�����Œ����Ɖ��ߊ����o�Ȃ��Ǝv���l�������悤���B
������X�e���I�ł̒�ʊ���T�E���h�X�e�[�W�͂Ȃ���
�}�C�N�Ɗy���̋������͂�������Əo�Ă���B
���R�̓p���X���̏o���Ǝ�������y���̃o�����X��
�y��̋������I�Ɏ@�m�ł��邩�炾��
�X�e���I�^���̒�ʊ��͍���̃p���X���ŔF�������邽��
�}�C�N�Ƃ̋������͐l�H�I�ɉ��H�ł���悤�ɂȂ��Ă���B
���m�����Œ����ƁA�}�C�N�Ɗy��̋����������ɖ߂�
�{���̉��t�̃_�C�i�~�b�N���ǂ�قǂ̂��̂��@�����t���B
���ꂪ�y�Ȃ̍\�����ǂ��Ȃ��Ă��邩��m���|����ɂ��Ȃ�B
�y�Ȃ̍\���Ƃ����Ə����傰����������Ȃ���
�Ⴆ�Ίy�Ȃ̕��͋C�̓T�E���h�X�e�[�W�ɂ��Ƃ��낪�傫��
���������Ȃ̂��A�L���z�[���g�[�����̂���
���̊y�Ȃ̃��Y������y������荞�ރ^�C�~���O�Ȃ�
���t�̊�{�I�ȂƂ��낪�x�z�����B
�ǂ��m����̂̓{�u�N������|�����u�A���@�����v�Ɓu�h�̒j�v��
�A���@�����͐����A�h�̒j�͋��������ł����l�ߏ�ԁB
�Ƃ��낪���������m�����Ƀ~�b�N�X���Ē�����
�قƂ�ǂ̊y��͋ߐڃ}�C�N�ɋ߂��A�����W�Ŏ��^����Ă���
�A���@�����̃h�����̂ق��������ƃ^�C�g�Ń_���T�u���B
�ނ���X�g�[���Y�̂ق����S��̂���u���[�X���̃��Y�������ށB
�����͈�ʓI�ȃA���o���̕]���Ƃ͈قȂ�̂��Ǝv����
���̑唼���G�R�[�̑召�ň�ۂ����܂��Ă��邱�ƂɋC�t���B
���̃}�C�N�ɓ��������ɊҌ�����Ɖ��t�X�^�C�������n�b�L������B
���m�����^�����̂�1960�N�㔼�œr�₦�邪
���m�����ł̎�����1980�N��O���܂ő����Ă���
�^���X�^�W�I�ł����W�I�A�L���ł̃��X�i�[��ΏۂƂ���
�I�[���g�[��5c 1�{�Ń��j�^�[���邱�Ƃ��s���Ă����B

�Ƃ͂����e���r�����ă��m�����������قƂ�ǂ������킯��
�X�e���I�Œ����@��Ƃ����̂�FM�ƃ��R�[�h�Ɍ����Ă����B
MTV�ȂǍŐV�̏��̓��m�����Œ����Ă����̂��B
���̓��m�������������鑕�u���e���r��W�J�Z��
�قڌ��肳��Ă����_���B ���{��FM�X�e���I�������{�i������̂�1970�N��ɓ����Ă���
����܂ł̓e���r���N�ł�FM�g��Hi-Fi�K�i�Œ�����I�[�f�B�I�������B
�Ⴆ��1960�N��܂ł̐^��ǃe���r�̃X�s�[�J�[���݂��
��^�̉Ƌ�e���r�͉������ׂ�2way�X�s�[�J�[�������B

�������̍����̔ԑg���^�[�Q�b�g���Ǝv����
�싅�̒��p�ł��Տꊴ�Ƃ����Ӗ��ł͏\���Ɍ��ʂ��������Ǝv���B 1960�N��܂ł�Hi-Fi���m�����̎��オ�߂���������
1980�N��܂ň���������Lo-Fi���m�����̎���Ƃ��ꗂ�
���m�����Đ��̕�����ɂȂ��Ă���B
�����ŁA�X�e���I�͖{�i�I�ŁA���m�������⏬�����ꂽ���j��
�ǂ�����ăs���I�h��ł����ۑ�ƂȂ��Ď����オ��B
���͖{�i�I�ȃ��m�������u�Œ������y�͕��ʂɗǂ����Ȃ̂��B
�N���V�b�N�̘^�����Ε����邪
�����X�e���I�ł���ʊ��̑��������S���قȂ�B
1960�N��܂ł͕Lj�ʂɃX�N���[����ɍL���鉹�ꊴ��
����͉f��قł�PA�Ɠ��l�̉����v�P���Ă���B

1970�N�ォ�玟��ɃT�E���h�X�e�[�W�̊T�O�����B������
�����͉pBBC�̌����ɂ���Ă���B

1990�N��ȍ~�̓p���X�g�Œ�ʊ����o�������ɕς��
���s�������܂ōČ��ł���悤�ɂȂ����B
�}�C�N�������������Ԋu�Ŕz�u�����B

�|�b�v�X�̃X�e���I�^���͂����ƎG��
1960�N��O���܂ł̓f���I���m�����܂��̓s���|���X�e���I�ƌ���ꂽ
���E�̐M�����S��������Ă���^�C�v�B
�E�H�[���E�I�u�E�T�E���h�̓��m�����~�b�N�X���ƒ��{�l�������Ă���B
1960�N�㖖����1970�N��O���̓X�y�[�X�G�C�W�̂悤��
���d�͋�Ԃɖ����ɍL���鉹�ꊴ�B
�T�E���h�X�e�[�W���m������̂�1970�N��㔼�����
����͐��BBC�̌����ɂ��Ƃ��낪�傫���B
���̌�̃X�e���I�^���̏�
�E�H�[���E�I�u�E�T�E���h�̑��̂悤�ȃI�[�o�[�_�u���d�˂����̂���
�s�[�N�����ɒ[�ɒׂ��ĉ������グ�����̂܂ŗl�X��
�ނ���e�N�m���W�[�̔��W�Ƃ͋t�s����悤�Ȋ���������B
�X�e���I�����猴���ʂ肾�Ǝv���ق����ԈႢ���B
�̕��Ń{�[�J�����������Ȃ烂�m������������
�{�[�J����1�{�̃}�C�N�Ř^���Ă���̂ɃX�e���I�ʼn������`����̂�
������̃v���[���X�������ۂ�����A�p���X�����ۗ����������
�����O�ɔ���o���A�����ɃX�����_�[�ɒ�ʂ���悤�f�t�H��������Ă���B
�}�C�N���|�b�v�m�C�Y�ɕq���Ȃ̂͗ǂ��m���Ă��邪
�|�b�v�K�[�h��t���Ă��A���b�v�m�C�Y�i���r�߂���j�͒��ӂ����B
����������ʊ������������m�C�Y�Ƃ��Ĕr�������Â��^����
�r�b�O�}�E�X�Ƃ����X�e�[�W�����ς��ɐO���L���錻�ۂ����邪
����̓E�[�n�[�̔������݂��^�C�v�ŋN���₷���B
�N�C�[���u���Ƃ������̗~�]�v�́A�r�b�O�}�E�X�̌��ʂ��t��ɂƂ���
���J�r���[���̒ቹ������Ă��鐺�ʼn��o���Ă���B
��������m�����Œ����ƁA���ɂ��������l�̒j��
�N�[���ɑ������Ƃ���p���I��ɂȂ�B���͂̎G���������邩�炾�B
����̓u���[�X�̃_���j�ɒʂ��郍�b�N�̖{���I�ȗv�f���Ǝv���B
�N���V�b�N�̓��m����������
�����Ղ��y���邵�A�ĔՂ���������邯�ǃ��m�����J�[�g���b�W�ōĐ�����Əd�ʔՂ��̍��������̏R�U�炷�[���ėY��ȉ�������B
�����ƕč��ł̓J�b�e�B���O���x���Ȃǐ^�t�̐��i����
�����������̓A�i���O�Ȃ�ł͂̌��ۂ�
���̓}�X�^�����O�̖������J�b�^�[�E�l���S���Ă��B
CD�̏ꍇ�́A�ܖ��N�S�������悤�ɐ��e�[�v�̉����̂��̂͑f���C�Ȃ�
���}�X�^�[�̕��������₩�ȕ����ɓ]���Ă�������B
�������A�v���ł����ƒ����������Ȃ�̉��ɂȂ�̂���
�ςȃs���A���Y���������ĉ����������邱�Ƃ��֊��Ƃ����B
�ܖ��N�S�̃R�����g�͈ȉ��̂��́B
http://www.audiosharing.com/people/gomi/kyositu/kyou_05_1.htm
�L�R�m�O���A�A�i���O�͂ł��邾���X�g���[�g
�f�W�^���͋t�ɉ���肵���ق����ǂ��悤�Ȃ��Ƃ������Ă����B
CD�̉����Ɗ����錴����
1.�o�͑��̃o�b�t�@�[�A���v����͂ʼn��̉��ʊ����o�Ȃ��B
�@��R��ŃC���s�[�_���X�����킹�������̂��̂������B
2.20kHz���ӂɗݐς���f�W�^���m�C�Y�Ńs�[�L�[�����B
3.�A�i���O���L�̐^��ǂ̃����M���O�A���C�q�X�e���X�X�Ȃ�
�@���ɉ���S����o���Ȃ������ꖡ�C�Ȃ��Ȃ�B
�������AEG�A���v�A�J�[�g���b�W�Ȃǂɓ���ւ����
�A�i���O�ʼn����ǂ��Ƃ������R���𖾂ł���Ǝv���B �t��21���I�ɓ����ĉ��b�����̂�
1950�`60�N��̕����p���C�u�^����
�t���g���F���O���[��RIAS�Z�b�g�͂Ƃ�����
�~�g���v�[���X/NYP��N�����C�^���X/�o�C���C�g���y�ՂȂǂ�
�����ǂ̃I���W�i���e�[�v���烊�}�X�^�[�����
����܂ŊC���ՂŒ����������R�̂悤��
�N���Ń_�C�i�~�b�N�ȉ��Ŋ��\�ł���悤�ɂȂ����B
�����͂����ƃ��m�����E�X�s�[�J�[�Œ����ׂ����B
�����Ŗ��Ȃ̂��A�N���V�b�N�Ń��m����LP�̌�����`�Ƃ͉����H�Ƃ������̂ł���B
�����b��ɂȂ�̂��A�����v���X�ƃo�W�F�b�g�ՂƂ̉��̈Ⴂ�͂Ƃ�����
CD�����̃}�X�^�[�e�[�v�������ォ��̃R�s�[�ł�������Ƃ�����ۂ������B
CD�Ȃ�̗ϗ��ł́A�e�[�v���̂܂܂̉��𖡕t�������ɐ��m�ɂ���
�ƌ��������Ƃ��낾���A���̐������炵�ď����v���X�ՂƂ͑S���قȂ�B
�l�X�ȃ��}�X�^�[�Ղ��N�X��������邪�A��������J�������ł���B
�Ƃ��낪���_��T���Ă����ƁAEMI��f�b�J�A�R�����r�A��RCA�̂������
���t�@�����X�ƍl���Ă����I�[�f�B�I�����قȂ�
�����ōō��̌��ʂ��o��悤�ɒT���Ă����炵���̂��B
EMI�ƃf�b�J�̃T�E���h�̌X�����S���قȂ�̂͂悭�m���邪
���j�^�[�X�s�[�J�[�͓����^���m�C�Ȃ���
EMI�̓\���b�h��Lockwood���A�f�b�J�̓R�[�i�[���[�N���g�p���Ă����B
����ɓd�~�܂ł�����
EMI��HMV���ȉ~�t�������W��Lorenz���R�[���c�C�[�^�[�𑫂�������
�f�b�J�̓Z���^�[�Ƀ^���m�C�����A���e�ɃE�[�n�[��2�{�������\���������B
�܂�A���̐��i�Ƃ��ẮA���̃g�[���ƃo�����X�����悤�ɍl�����
���Ђ̃��[�x���̌��Ƃ��Ĉ����p����Ă������Ƃ�����B
���Ȃ݂ɗΐF�ƌĂ��ăR�����r�A�̓A���e�b�N�iVOTT�^�C�v�j
���₩��RCA�̓I���\�����m�̊J����������2way LC-1A�ł���B
����ŁA�ŋ߂̃��}�X�^�[CD�́A�����������[�x���̌�������
���Չ������������Ō㐢�Ɏc�����Ƃ��Ă���悤�ɂ݂��邪
�̐S�̃I�[�f�B�I��������ɒǂ����Ă��Ȃ��悤�Ɏv����B
���m�����^�����w�b�h�z���Ŏ������镾�Q�͂Ƃ�����
�唼���߂�݂������������Ȃ����^�E�[�n�[�ł�
�ߐڃ}�C�N�ő������Ȃ��ቹ�Q�̓X�J�X�J��
�c�C�[�^�[�̃p���X�����������ڗ������邾���ł���B
�����͘^���̏ɍ������I�[�f�B�I���������Ȃ��ߌ��ł���
�������z�ōw������CD�ɔ������肵�Ă����
���}�X�^�[CD�Ɍ�������^�ۗ��_�̌����Ƃ��Ȃ��Ă���B
�A�i���O�Ղ��ƍI�����āA�f�W�^�������ꗂ��o�₷���̂�
�f�W�^��������Ă��鉼�ʁi�ŐV�Z�p�A���m�ȉ��A�L�ш�etc�j���x����
���̖{���I�ȕ������������Ă��܂�����ł���B
�l�I�Ȉӌ��ł́A���m�����̉�����100�`8,000Hz��
�ϓ��ɖ�悤�ɒ�������Ă���Ώ\���ł���B
����̓{�[�J���}�C�N�̓�����ł����炩��
�l�Ԃ̃R�A�Ȍ��ꊴ�o�ƈ�v���ĉ��y���\�������B
�ϓ��Ƃ����̂́A���������^�C�~���O�̖�肪�傫��
�ŋ߂̃X�s�[�J�[�̂悤�ɒቹ�����ɍL����^�C�v�͕s��
�t�B�b�N�X�h�G�b�W�Ńp���p���ɖ�悤�Ȃ��̂łȂ���Ȃ�Ȃ��B
���m�����̉�����100�`8,000Hz�ŏ\���Ƃ����̂�
������̂�SP�Ղ�AM���W�I�̂��Ƃ������Ă���킯�ł͂Ȃ�
�Ⴆ�}�C�P���E�W���N�\���u�X�����[�v��^�������ۂɂ�
�����ȃI�[���g�[��5c�Ƃ����t�������W�łقƂ�ǂ̃~�L�V���O������
�Ƃ�������������f����B
https://umbrella-company.jp/contents/auratone-history/

�X�����[�̉�������z������̂�
�E�F�X�g���C�N�Ђ̍��؈�ࣂȃ��j�^�[�V�X�e������
���̃R�A�ȕ����͐l�Ԃ̉��̈�ł����Ȃ苷���͈͂ɗ��܂��Ă���B
�܂�A�I�[�f�B�I�ɂ͍L�ш�ȊO�ɒNj����ׂ����\������
�Ƃ���������O�̌��_�ɍs��������̂ł���B
>>30�̃����N�̂悤��
�u15,000Hz�ȏ�̓J�b�g���A�Ⴂ�ق���40Hz�ȉ��́A��̂Ă�B
���̂����7�`8,000Hz�c�������3dB������A���̂ق����������肪�悭�Ȃ�v
�Ƃ����J�b�e�B���O�E�l�̈ӌ��͂��ׂ��炸���݂����ʂ��Ă���̂��B CD�K�i�̍��莞�̃I�[�f�B�I���ƁA���̌�̃f�W�^���Ή��@��̖�����
���̓_������l�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
CD�K�i��20kHz�܂łƂ������R�ɂ���
�����̘^���G���W�j�A����15kHz�ȏ�͊y���Ƃ��Ďg��Ȃ��Ƃ����ӌ���
���ۂ̉^�p��FM�����Ƃ̋����W��ړI�Ƃ��Ă������炾�ƍl������B
�Ⴆ�A�O�҂̘^�����̈ӌ��̓N�C���V�[�E�W���[���Y�Ȃǂ���f���邵
��҂̓}�[�P�b�g�Ƃ̊W���烉�W�I�Ŏ��������R�[�h���w���Ƃ������ꂪ
�嗬���������Ƃ�����B
�����Ɗ̐S�Ȃ̂�FM�g���L�̎O�p�m�C�Y��
���{����2kHz�ȏ�Ł{4��B�̃G���t�@�V�X���|���邽��
�S�̂ɏ_�炩���}�b�g�ȕ��͋C�̉����Ɏd�オ��X���ɂ��邱�Ƃ��B
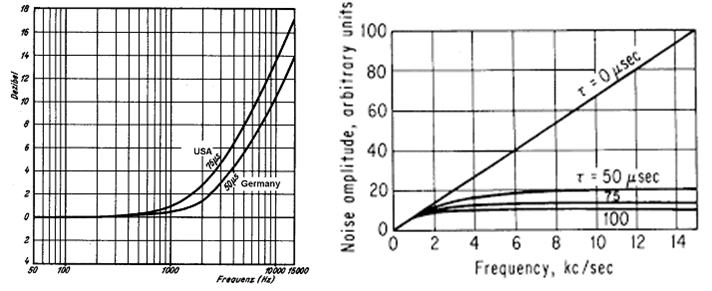
CD�̉����̑����́AFM�����Œ����f������悤�ɂł��Ă���
�Ǝv���̂��Ó������A8�`10kHz�Ƀ|�C���g���i�������̂������Ă������B
������͂��͂�O�p�m�C�Y�̖��̔ޕ��ŞB���������̂��B ��������20���I���ɋN�������I�[�f�B�I�̃f�W�^�����̕��Q��
�l�Ԃ̒��o���g��������ƋU�����f�t�H�����ɂ���Đ��藧���Ă����B
�I�[�f�B�I�̐i���Ƃ����̂��A�������R�ł���B
���̏؋��Ƃ��āA�}�C�N1�{�Ř^���������p���m�����^����
���Ȃ����ȃo�����X�Ŗ邱�Ƃ��悭�݂���B
�z�肵���T�E���h�X�e�[�W���悭�p���X���������Ȃ�
�E�[�n�[����͂Œ��悾���ł̓����������邩�炾�B
�܂�A�}�C�N�̌����ȂǍĐ����Ȃ����Ƃ��������Ă���B
���Ȃ݂Ƀn�C���]����ʓI�ɂȂ������݂ł�
>>38�̂悤�Ȑv�̃c�C�[�^�[�͏��Ȃ��Ȃ�����
CD�K�i�ł��f�W�^���m�C�Y���ڗ����Ȃ����Ă���B
���̃n�C���]�K�i�ɂ��Ă��A�����グ������
���^��40kHz��ۏł���}�C�N���Ȃ��Ƃ������l���������B
�n�C���]�̎��ۂ̌��p�́A�p���X���̃f�W�^���m�C�Y��
���S�ɉ���O�ɂ��������ƂŎG�����������Ƃ������x�ɉ߂��Ȃ��B
CD��DA�ϊ����̃t�B���^�[���V���[�v���[���I�t����
�p���X�����Ń|�X�g���v���G�R�[�̃m�C�Y������ɏo�Ă�����
�X���[�^��V���[�g�^�ȂǗl�X�ȃ^�C�v���o�Ă���B
https://velvetsound.akm.com/jp/ja/stories/meister/meister-tutorial01/
�����𑍍����Ă��A������̈����͖������W�r��ł���
�ނ���m�C�Y�ɖ�����Ă������̂ق����K����������������Ȃ��B �f�W�^���m�C�Y���A�i���O�n�̃m�C�Y�ɖ�����Ă�������Ƃ�
FM�����̎O�p�m�C�Y����\�I�Ȃ��̂�������
�ŐV�̃A�i���O�^����CD������AAD�p�b�P�[�W���ǂ������������B
�܂��R���f���T�[�}�C�N�ɐ^��ǂ̃v���A���v���������ǂ��ƌ������̂�
EMI�̃G���W�j�A��88.2kHz�K�i�ł̘^�����n�߂����������B
�܂��\�j�[�̌����ŁA�������x���̃z���C�g�m�C�Y�����������ق���
���̗֊s���͂����肷����ʂ�����Ƃ������Ƃ��B
�I�[�f�B�I�̍œK�Ȏ��g���ш�ɌÂ�����u40���̖@���v�Ƃ����̂�������
����̓N���f���U�̂悤�Ȓ~���@���A�y���Ɏ��g�������̗ǂ��d�~���
�Ȃ�ŐS�n�ǂ���������̂��ɂ��Ē��ƍ���̃o�����X�ɂ���Ƃ�
�N���f���U�̎��g�������̗��[��100Hz��4kHz���|����40���Ƃ������̂��B
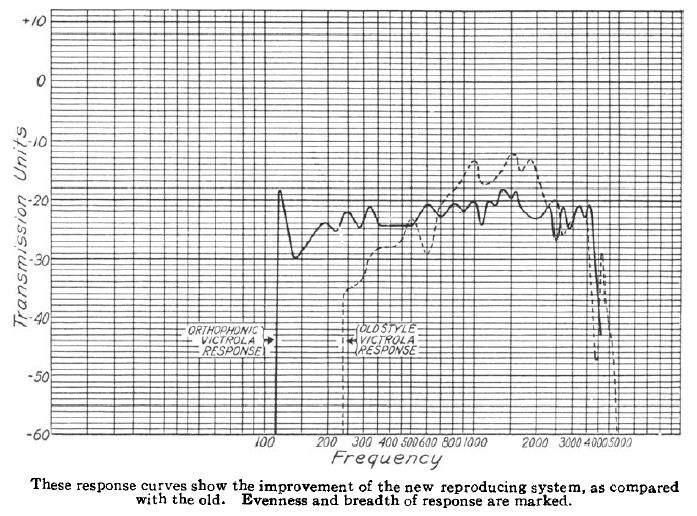
����ɂ͐l�Ԃ̉��̈�20�`20,000Hz���܂܂�Ă�����
AM�F100�`8.000Hz�AFM�F50�`15,000Hz�Ƃ�������
���ۂ̋K�i�̂ق��́u80���̖@���v�Ő��藧���Ă���B �Ƃ��낪�N���f���U�ɂ͕ʂ̓�����������
�U���ƂȂ�T�E���h�{�b�N�X�ŏE�����X�N���b�`�����������M���O�Ƃ���
���ʓI�ɌG����^���Ȃ���g������@�\��������Ă���B

����͑f���ȃJ�[�u��EMS�Ɣ�ׂ�Ɩ��炩�ł���B
����EMS�̓��b�p�������ݔՂ��ő���Ɋg������^�C�v
����̃N���f���U�͓d�C�������ݔՂ��Đ����鑕�u�ł���B
���̃����M���O�́A���݂ł͍����g�c�݂Ƃ��Č�������邪
������Hi-Fi�Z�p�ł́A�^��ǂ̃I�[�o�[�V���[�g
�g�����X�̍����c�݁A�X�s�[�J�[�̕����U���܂�
������Ƃ���ō����g�c�݂Ƌ������ăo�����X���Ă����B
���̋Z�p�̌n������ꂽ�̂�
1960�N�㖖�Ƀg�����W�X�^�[���̃~�L�T�[�삪����Ĉȍ~��
���b�N�o���h�u�h�A�[�Y�v�̘^���G���W�j�A�͕ҏW����
�I�[�i�[������Ƀ~�L�T�[��^��ǂ���g�����W�X�^�[�ɑウ�����Ƃ�
�p���`������V��̍����T�E���h���S��������o���������B
�����́u�\���b�h�X�e�[�g�̐���v�ƌĂꂽ��
������NEVE��ɂ͔{���̑������C���g�����X���d�g�܂ꂽ��
EMT�̃v���[�g���o�[�u�����p�����悤�ɂȂ����B
�d�C�^���ɂ́A�����������特���I�ȎG�����K�v�������̂��B ����1970�N��ȍ~�̃X�e���I�����͂���Ȃ�ɈӖ���������̂�
�v���[�g���o�[�u�Ŗ��t�����ꂽ�^���̑N�x��
�e�[�v�̎��C�ɂ���Ď����₷�����Ƃł��m���Ă���B
�����Ƃ��ߎS�Ȃ̂̓f�W�^���ł����݂��A�i���O���^����
1980�N��̃|�b�v�X�̂悤�Ɏv���Ă��邪
���Y���̗����オ�肪�ׂ�āA���������ĕ������邱�Ƃ������B
���������P���̎���ꂽ�T�E���h�̕]����
��x���m�����Ɏd���Ē����ƁA��Ԑ��̕����������邩����
���̊y���Ƀ��Z�b�g����āA�y�Ȃ̈Ӑ}�����������B
�X�e���I�^���̉��ꊴ�ɂ̓g�����h�̗��s��p�肪������
1970�N��̃��o�[�u�̎g�����͌����ςɂ��g�����
�{�u�E�f�B�����̃x�[�X�����g�E�e�[�v�̊��S�łł�
��������70�N��A���o���ւ̔ᔻ����������
���{�̃V���K�[�x�C�u�u�\���O�X�v�ł������̓f���e�[�v�ȉ��ƌ���ꂽ��
���ɂȂ��Ă݂�Η��s��̃��o�[�u�ŃR�e�R�e�ɂ��Ȃ��Ő����������炵���B
����̓��[�x���𗧂��グ������̑��r���
�I�[���f�B�[�Y�D���Ƃ��d�Ȃ��Ă����悤�Ɏv���B
�����̕����X�^�W�I�́A���W�IDJ���̐ݔ���
�w�b�h�z���Ń��W�I�p�ԑg���ҏW���Ă����B
���j�^�[�̓r�N�^�[SX-3���ƌ����邪
������������ƃS�[�W���X�ȕ�AMI���̃W���[�N�{�b�N�X������
���N���ォ�畷���Ă�1960�N�O��̃A�����J���B�|�b�v�X��
�h�[�i�b�c�Ղ��d����ł����B
���̃R���N�V������CD�ŕ�������Ă��邪
�����̐[�郉�W�I�ʼn���������ē��W��g�ނقǂ�
�C�̓���悤�������B
��ʂɂ́A���r��̓E�H�[���E�I�u�E�T�E���h���ƌ����邪
�V���K�[�x�C�u�̗B��̃A���o������͕ʂ̕��i�������Ă���B
����45�X�^�W�I�F��O�EAMI�W���[�N�{�b�N�X�A���E�r�N�^�[SX-3

�i�C�A�K�����[��������

�i�C�A�K�����[��CD�Ղ�JBL 4343�ɉ����Ă��� ��������̃r�N�^�[ SX-3��1973�N�ɐ����J�n���ꂽ���̂�
���^�̏��^�X�s�[�J�[���\�t�g�h�[���E�c�C�[�^�[�̑���ł���B
���݂ł͓����v�҂��N���v�g���Ђ�KX-3�Ƃ��Đ��삵�Ă���B
����KX-3�̐v�ł͖��^���\�t�g�h�[���Ƃ�����{�H���͕ς��Ȃ���
�E�[�n�[��25cm����16cm�N���X�܂ŏ�������
�N���X�I�[�o�[��2kHz����3.5kHz�܂ŏグ�Ă���̂�������
���R�̓{�[�J������E�[�n�[�ŃJ�o�[�ł���悤�ɂ����������Ƃ������Ƃ������B
���̃{�[�J����̍l�����͓��{�I�ȗ��R��������
�ꉹ�̂����A���ƂȂ�800�`3,000Hz���J�o�[�ł���悤�ɂ��Ă���B
����̓A�W�A�n����ł͏���ł����߂���ш��
�t�ɉ��Č���ł͎q���ƂȂ�2.5�`6kHz�Ɍ�b���ڂ邽��
1.5kHz�t�߂ő��X�ɐ�グ�Ă��܂��v�������B

�ȉ��̐}���ɏ�������ł���̂�
�X�s�[�J�[�̐U���ʃo�b�t���ƌ����Ă��ꍇ�̍Œዤ�U���g����
�_�C���N�g�ɋ�C��U�������邱�Ƃ̂ł���͈͂ł���B
����ȉ��̎��g���͔��̔��˂������͋��U�œ�����2���g�ƂȂ�B �����̃E�[�n�[��c�C�[�^�[�̑ш���݂Ďv���̂�
�X�s�[�J�[�̐v�́A���{�I�ɐl�Ԃ̌���@�\�Ɏ����č���Ă���
����͎���������
�l�Ԃ̒��o�͌���I�R�~���j�P�[�V�����̂��߂ɔ��B���Ă���
�Ƃ��������ł���B
�܂�I�[�f�B�I�͒��팻�ۂ������N���������@��ł͂Ȃ�
�l�Ԃ̃R�~���j�P�[�V�����̂��߂̋@�킾�Ƃ�����̂���
100�`8,000Hz�Ƃ������[�t�@�C�ш��9���̏�l�܂��Ă���B
�����1950�N��̘^���ł��\���Ɋ��������闝�R�ł���
�ނ���21���I�ɂȂ��Ă��ς��Ȃ����̂ł�����B
���m�����ʼn��y�ӏ܂���ׂ����R�Ƃ���
�l�Ԃ̃R�~���j�P�[�V�����̎����A���Ɏ����ł̑Θb�̎d���ł���B
����͑吨�̐l�������l�߂ɂȂ��Ԃł͂Ȃ�
�ނ���Ζʂ������ׂ͗Ō�炤���ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ����낤���H
�X�e���I���烂�m�����ɂ���ƕ����`�����l�̂̑��݂ɕς��
���y�̃p�[�\�i���e�B���������̂ł���B
�����1960�N��ɕҏW���ꂽ���C���Ղ�
�ŋ߂ɔ��@���ꂽ�����Ƃ̐��i�̈Ⴂ�ɂ��\��Ă�B
1960�N��̃��C���Ղ͊ϋq���������p�b�P�[�W�̈ꕔ�ł���
�ŋ߂̔��@�����̂ق��͉��Ƃ��Ă̓V���v������
�~���[�W�V�����̃p�[�\�i���e�B�����������̂��I��Ă���B
�T�C�������K�[�t�@���N���F1967�NNY���C��
�s�[�^�[,�|�[��&�}���[�F1967�N���{�c�A�[
�W���f�B�E�V���F1972-73�NBBC���C��
�ȂǐS�Ɏc����̂����ł��F�X����B
����Ɋϋq�̓��肪�����������F�����F�b�g��1969�N�}�g���b�N�X�E���C����
�{�u�E�f�B������1962-64�N�ɑ�^�����E�B�b�g�}�[�N�E�f���܂Ŋ܂߂��
���\�ȃR���N�V�����ɖc��オ��B
�p�[�\�i���e�B�Ŏv�������ׂ�̂̓��W�IDJ�ł���B
1970�N��Ɍ��ꂽ���W�J�Z�͓��{���̉Ɠd���i��
���̉����v��AM��FM���g�����邽�߂�
�Â��W���[�N�{�b�N�X�Ɠ����G�N�X�e���f�b�h�����W�{�c�C�[�^�[�ł������B
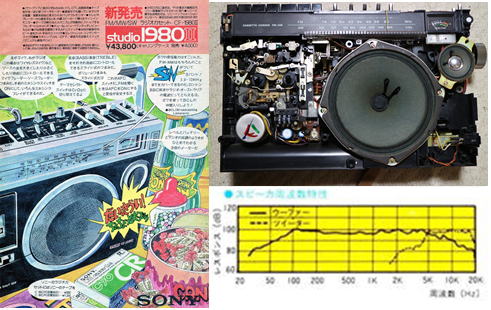

���͓����̍Đ��Ɋւ��ẮA���W�J�Z�̂ق����ǂ��v����Ă���
�E�[�n�[�̍����2kHz�ȉ��Ő����Ƃ��ɁA�m�y�͉f����̂ɉ̗w�Ȃ̓_��
�Ƃ������ۂ��܂܋N���邪�A����͌���I�������W���Ă���B ���r�ꂪ�厖�Ɏ����Ă���AMI�ЃW���[�N�{�b�N�X����
1959�N�̃r���e�[�W����ɓ��ꂽ������10�N�����o���������B
�����炭���m�����d�l�i�t���J�[�g���b�W GE�o������III�j���������Ƃ�����
��r�I����������邱�Ƃ��\��������������Ȃ��B
���{�Ńr�[�g���Y��������悤�ɂȂ����̂�1964�N�ȍ~����
�����Ղ����������ʼn��H�̗m�y����ł��C�M���X���̃��b�N�Ƃ������̂�
�S�����m�̑��݂������炵���B�A�����J���E�|�b�v�X�̉������ł�����B
�E�F�X�^���E�J�[�j�o���ȂǗm�y�J�o�[�̗̉w�V���E����������
1966�N������}����GS�u�[���ɐ�ς��
�����̗��s�̎�͉̗w�ȁA�|�\�l�Ƃ����g�g�݂ɂȂ��Ă������B
�̃��m�ƃT�E���h�̒J�Ԃ��ł��āA�I�[�f�B�I�̕]������ς��������������B
���{�̏ꍇ�́A�V���O���ƃA���o���Ń~�b�N�X�̕��͋C�̈Ⴄ���̂�����
�Â��̓V���O���̓��m�����A�A���o���̓X�e���I�Ƃ������ݕ������������B
���ɃV���O���E�o�[�W�����́A�A�C�h���≉�́A���邢�̓e���r���̂Ȃ�
�{�[�J�����S�ɃN���[�Y�A�b�v�����o�����X�ł܂Ƃ߂��Ă���
��Ƀ��W�I��L���ł̎����҂��^�[�Q�b�g�ɂ����T�E���h����ł���B
����̃A���o���E�o�[�W�����́A�X�e���I�̉��ꊴ���L�߂ɂƂ���
���V���t�H�j�b�N�ȕ��͋C�ł܂Ƃ߂��Ă���
�R���T�[�g�����ӎ������t�@�������̏��i�ƂȂ��Ă���B
�ꍇ�ɂ���Ă̓A�C�h���̃|�X�^�[�t���Ƃ������T�ōw������P�[�X���������B
���̗��҂��r�����ꍇ�A�A���o���͖{�i�I�A�V���O���̓��W�I����
�ƍb����t�����������A�y�Ȃ𖡂키�ɂ�����A����͑Ó����낤���H
�̎�̃p�[�\�i���e�B����茰���ɔ��f���Ă���̂̓V���O���ՂȂ̂��B
�����ăV���O���ՂƑ����̗ǂ��I�[�f�B�I�̕]�����������K�v������B
���ꂪ���W�J�Z�ł���A���̃o�[�W�����A�b�v�̓X�e���I�ł͂Ȃ�
�Â��W���[�N�{�b�N�X�ł���Ƃ��������ĂɂȂ�B
�|�b�v�X�̉��ꊴ�ɂ��A�����J���ƃ��[���s�A�������邪
���������敪���o�Ă����̂�1970�N��̂��Ƃ��Ǝv���B
����܂ł̓A�����J�ɒǂ����ǂ��z���̏�
�C�M���X�̃n�[�h���b�N�͂ނ���A�����J���ȏ�ɃA�����J�����B
���{�̏ꍇ���^���Z�p�̓������A�����J�o�R��������
�r�[�g���Y���A�����J���E�A���o������X�^�[�g�����B
���������A���o���̓��m�����ŏ\������������������B
���[���s�A���ƌĂׂ鉹�ꊴ�i�T�E���h�X�e�[�W�j�����^����
�Ⴆ�u���C�v�u�I�y�����̖�v�Ȃǂ̃R���Z�v�g�A���o���ł͂��܂�
�����I�ȃX�g�[���[�̂�����̂��o�Ă����悤�Ɏv���B
�X�e���I�łȂ���Ǝv���̂́A���̎�̍�i���w���̂��낤��
���m�����Œ����Ȃ����Ƃ����ƁA�ӊO�ɂ����ł��Ȃ��B
�ނ��냂�m���������炱���A�y�Ȃ̃V�i���I������₷���B
�e���r�h���}�̂悤�ɉ������N���[�Y�A�b�v����Ă��邩�炾�B
���m�����Đ��ɂ́A1�{�̃��m���[�O�Ƃ��Ĉ������@�����邪
��ʂ̐l�ɂƂ��Ă̓X�e���I�Ɠ����悤��2�{�̃X�s�[�J�[��
�R���T�[�g�z�[���̉��ꊴ���Ē��߂�悤�ɒ������Ƃ̂ق���
�f�t�H���g�ɂȂ��Ă���悤�Ɏv���B
���̗��R�̓X�e���I�K�i�����m�����ւ̉��ʌ݊�����S�ۂ�����
���ڏ�͂Ȃ��Ă��邩��ŁA�����̐l�͑�͏������˂邩������
�X�e���I�X�s�[�J�[���m�����^��������B
����ŁA�X�e���I�Ղ̓��m�����ł̎����������������Ƃ��鈳�͂�����
���m�����Œ������Ƃ̃f�����b�g�������֒�����Đ�`���ꂽ�悤�Ɏv���B
���ɂЂǂ��̂́A�X�e���I�^�������m�������[�h�Œ����Ƃ���
���悪�ۂ܂�����ԂŁA����̓��m�����̃��W�J�Z�Œ������ߎS�ȉ����B
�����FM�`���[�i�[�Œ���AM���������S���S����������
��͂胉�W�I�P�̂Œ��������������B
1970�N��ȍ~�̃��m���������͎��̎��オ�������̂��B
����Ő^���Ƀ��m�����^���ƑΛ����Ă����̂����_���W���Y��
�����1970�N��ȍ~��JBL�̃��j�^�[�X�s�[�J�[��ʂ���
���@���E�Q���_�[���͂��߂Ƃ���ߐڃ}�C�N�̐��X�����T�E���h��
�ĕ]�������悤�ɂȂ����B���𗁂т�悤�ɑS�g�Œ����X�^�C�����B
�|�b�v�X�ł̃��m������A�́A�A�i���O�Ղ���[�����p�~�ɂȂ���1990�N���
�E�H�[���E�I�u�E�T�E���h�̊J�c�t�B���E�X�y�N�^�[���uBack to MONO�v
�Ƃ���3���g�̃A���o���ŁA���g�̃T�E���h�����m�����~�b�N�X����
���j�I�ȃJ�~���O�A�E�g���ʂ��������Ƃ��B
���̌�A1960�N��̃��b�N�𒆐S�Ƀ��m������A���͂��܂�
�r�[�g���Y�̃��m�A���o���S�W���o����ɂقڒ蒅�����B
�����Ƃ��V���O���Ղ̃��m�~�b�N�X���X�e���I�ƃA�����W���قȂ�̂�
1990�N��ł����ՂŎ��m����Ă�����
�������ł��r�[�g���Y�̃X�^�W�I�^�����R���v���[�g������
�R�A�ȃt�@���̂��߂̃A�C�e�����ƔF������Ă����B
���m�A���o���͂����ł͂Ȃ��A���m�����^���̃T�E���h���̂��̂�
�r�[�g���Y�̃��b�N����[�I�Ɏ������̂ƔF�����ꂽ�_������I�������B
�����l�I�Ƀr�[�g���Y�̃��m�����^���ōł���ۓI�������̂�
BBC�ɏo�������y�j�̌y���y�v���O�����̐��K�Ղ̓o���
�p�t�H�[�}���X�o���h�Ƃ��Ă̐l�C�Ԃ��f�i�Ƃ�����e���B
�č���R&B�y�Ȃ̃J�o�[�����S�ƂȂ邽�ߌ������Ă����̂��낤��
���̗��R�������̉p���̖@���Ń��W�I�ł̃��R�[�h�Đ���
���R�[�h�̔���j�Q����s�ׂƂ��ċ֎~����Ă������炾��
�������R�Ńr�[�g���Y�̓����}���V���[�ŕč��̃q�b�g�Ȃ�����ł����̂��B
����ŋL�^�Ƃ��Ďc���Ă��Ȃ��̂��A�@���������������ĕ��������C�����W�I�ǂ�
�����ʂ�D�ŊC�m�ɏo�ă��R�[�h�i8�g���J�Z�b�g�j��������Ă����B
���̂�����������O�̊y�Ȃ̔������݂邽�߂Ƀf���e�[�v����������肵����
1960�N����I���ɋ߂Â��ė��ɏオ�����C�����W�I��DJ������
���~���[�W�V�����Ƃ̍L���R�l�𗘗p����BBC�œ��Ԃ�g�ނ悤�ɂȂ����B
���e�̓��R�[�h�ɂȂ�O�̖����\�̊y�Ȃ��Љ����̂�
���̘^���ł̃p�t�H�[�}���X���Ƃ�������������
�����̃u���e�B�b�V�����b�N�̋P�����悭���f���Ă���Ƃ�����B
����BBC���C���̈�A�̘^���������Ɍ��J���ꂽ�̂�
�����������炩�Ȃ莞�Ԃ̌o������̂��Ƃ�
�~���[�W�V�������������R�[�h��Ђ���Ɨ�����
���̈����C���Ղɑ������Œ��쌠���R���g���[���ł���悤��
�Ȃ��Ă��炾�Ǝv���B
�����悤�Ȃ��Ƃ́A�����\�̃��C���^���ɋy�Ԃ��Ƃ͕K�R��
�{�u�E�f�B�����̂悤�ɐϋɓI�Ƀu�[�g���O�V���[�Y���o���l����
���C�m�E���[�x�������@���������}�X�^�[���ă����[�X���邱�Ƃ�����B
�����ł����Ă̂悤�ȑe���ȃR�s�[���i�����Ȃ���������ɔ��
�f�W�^���ҏW�Ő�\�肩��S�~���܂Ŏ��݂ɂł���悤�ɂȂ���
�Z�p�v�V�̉��b������悤�ɂȂ����B
����ł�����}�����I�[�f�B�I���̂ق��́A�ނ���t�s���Ă���悤�Ɏv���B
�����������s�����ȂǑ��݂��Ȃ����A���X�x�K�X���̏�i�ȃf�B�i�[�V���E�Ȃ�
���b�N�̂ǂ̉��t�ł��肢�����ł���B
�ǂ��݂Ă�1970�N��̂悤�ȃ��_���W���Y�̂悤�Ȍ������ɂ͎���Ȃ��̂��B
���̓_�͂����������y���牽����肽�����̚n�D�̈Ⴂ�ɂ���
�������������o���Ă��Ȃ��悤�Ɋ�����B
�|�b�v�X�̃X�e���I�^���̉��ꊴ��
1.�E�H�[���E�I�u�E�T�E���h
2.�R���T�[�g�z�[���̃T�E���h�X�e�[�W�����z��������
3.�f�B�X�R���N���u���̖��w�����̉���
4.�q�b�v�z�b�v�n�̃\���b�h�ȋߐڃ}�C�N
�ƂȂ邪�A���2�̓��m��������̈��ł���
�O�҂̂���1�͂����������m�����ō��肳�ꂽ�B
����2�̃R���T�[�g�z�[���^����
���͌��2����߂�قǂ̃R���e���c�͂Ȃ��B
�l�X�Ȏ�Ԃ��|���Ă��y�Ȃ̍\���Ƃ͕ʂ̌���
�܂�X�e���I�łȂ���Ζ��킦�Ȃ��Ǝ��̉����ƂȂ�B
���͂₻��͐l�H�I�ȉ��z����ł��茴���ł͂Ȃ��B
�f�B�X�R���N���u���̉��ꂪ���w�����Ȃ̂�
�R���T�[�g�ł̃}�i�[�����t�҂ƊϏ҂̃q�G�����L�[��r���������炾�B
�܂�u�`�Ɠ������@�Ŕq������̂���V�Ƃ������Ƃ�
�X�e���I�����ł͋������邱�ƂŐ��藧���Ă���B
����̓X�e���I�����̐����Ȓ������Ƃ�������
�X�e���I���u�ł������݂��Ȃ��������@�ł���B
���m���������͉��y�Ƃ̕��������R�ȊW�𑣂��B
�������ׂĂ邪�m���Ƀ��m�����Ȃ�ǂ��Œ����Ă��ǂ����
�E�H�[���E�I�u�E�T�E���h��
1963�N�̃��l�b�c��N���X�^���Y�̃q�b�g�ȍ~�̂悤�ɂ����邪
�u���b�N�����[���̃��[�O�i�[���A�v���[�`�F���N�����̂��߂̃|�P�b�g�E�V���t�H�j�[�v
�ƃt�B���E�X�y�N�^�[���g�������Ă���悤�ɂ��̑O���킪������
�o�W�F�b�g�E�R���s�ŕ�������Ă���1959�`62�N�̃V���O���W�ł�
�e�B���p�j�������I�[�P�X�g�����A�����W�Ɍ���Ă���B
�R���T�[�g�z�[����z�肷��悤�ȃG�R�[��ߏ�ȃI�[�o�[�_�u��z�����邪
���������ŋN����k�ތ��ہi�ǂ̔��˂Ŕg�`���ł����������j�𗘗p����
�����S�̂��h�ꓮ���悤�ȃ}�b�V�u�ȉ����ɓ���������B
������l�b�c�̃A���o���ɂ���u�z���b�c�E�A�C�E�Z�C�v�̃J�o�[�̂悤��
�_���X�z�[���ł̉�����^�����悤�Ȃ��̂��܂܂�邪
���ۂɕ�����k�킹��剹���Ŗ炷�Ƃ�������
�e�B�[���Y���g�����������W�I����ł����̂悤�ɕ�������_���d�v�������B

��L�̎ʐ^��1950�N�㖖�Ƀg�����W�Y�^�[���W�I���o�ꂵ������
�e�B�[���Y�����y�����@�Ƃ��ėǂ��݂�ꂽ���̂�
�ߐڂŒ����Ă��邽�߁A�ቹ���������Ē����邵
����̃p���X���̉������m�ɕ�������B
�E�H�[���E�I�u�E�T�E���h��l�X���F���������̌��ł���B
���������KOSS�Ђ̃w�b�h�z�����J�����ꂽ�B

���E���̃X�e���I�w�b�h�z���Ɩ蕨����Œm���邪
���g�̓��W�I�ɕt�����Ă��郍�[�t�@�C�ȃR�[���X�s�[�J�[�������B ���̂悤�ȋ��ш��`��1980�N��O���܂ő����Ă���
�I�[���g�[��5c���X�^�W�I�̈�p�Ń��j�^�[�X�s�[�J�[�Ƃ��Ċ��Ă����B
���ۂɂ́A���[�t�@�C�̂Ȃ��ɂ����l�Ԃ̊����h�蓮�����v�����傫��
�Ƃ݂Ă������낤�B
���W�I�p�X�s�[�J�[�Ƃ����ƁA���݂ł͂��Ȃ萫�\�̗�������̂Ǝv��ꂪ������
1930�N�ォ�琻������Ă��郉�W�I�p�X�s�[�J�[��
�T�˃��R�[�h�̑傫���ɏ����ĕω����Ă���ƍl���Ă������낤�B
1930�N���SP�Ղ�10�C���`�i25cm�j
1950�N���LP�Ղ�12�C���`�i30�����j
1960�N���EP�Ղ�7�C���`�i16cm�j
1980�N���CD��5�C���`�i12cm�j
1930�`50�N��͓d�~�ƌĂꂽ���m�����Đ��@��������
1960�N��ȍ~�̓X�e���I�p�Ƃ������ƂɂȂ�B
CD���W�J�Z�́ACD�̐��\�����R���p�N�g�����l�b�N�ƂȂ���
�X�e���I�ł�10cm���x�̃X�s�[�J�[��W���Ƃ��Ă���B
���f�B�A�̃T�C�Y�Ƙ^���̒��g�͓��R�̂��ƂȂ���Ⴄ�̂���
1960�N�ȍ~�̃X�e���I���̗���͏��^���̗���ł���
���y�̂��t�B�W�J���Ȑ�����r�����Ă�������ł�����B
���̗������[���Z�b�g����̂����m�������̈Ӑ}�ł�����B
���m�����Ŏ������邱�Ƃōł��s�����Ȃ̂̓I�[�P�X�g����i��
���̃X�e���I�������R���T�[�g�z�[���ł̃I�[�P�X�g�����̓`�������Ȃ̂�
���������X�e���I�^�����̂��N���V�b�N�̃I�[�P�X�g�������ƂȂ�B

�Ƃ��낪�A���i���ɂ��鉹�y�ŃI�[�P�X�g���̓o��p�x��10�������
�\���Ƀ}�j�A�̗̈�A�܂�ӎ����Ē����Ă���ƍl���Ă����B
�܂�10���ɖ����Ȃ��n�D�̂��߂ɃX�e���I�𑵂��悤�Ƃ���B
���m���������̓X�s�[�J�[�������Ȃ����Ȃ̂ł���قlj��i�͉�����Ȃ��B
�������X�e���I�Đ��ɕt���܂Ƃ��V���̐��X���l�����
�w����p�ȏ�̃I�}�P�ɜ߂��܂Ƃ��邱�Ƃ͕K�{�Ȃ̂��B �X�e���I�Đ��ɕt���܂Ƃ��V���Ƃ�
1.�����ʒu�̍��E�Ώ̂ɃX�s�[�J�[���Z�b�g��
�@���̒����ȊO�̏ꏊ�ł͉��������������B
2.��ʊ��̑����̓c�C�[�^�[�̃p���X�M���Ɉˑ����Ă���
�@���̔����U���̐����ɍׂ����Z�b�e�B���O��K�v�Ƃ���B
3.�p���X���M���̐��m�ȓ`���̓P�[�u���ނɂ��e����
�@�����x���A�≏�́A��������ȂǕ��G���������ł���B
4.�f�W�^���ɂȂ�Ɠ`�����̃W�b�^�[�A�G�R�[�A�O���m�C�Y�Ȃ�
�@�ʏ�̑��葕�u�ł͌v��m��Ȃ����ڂ��lj������B
5.�C���V�����[�^�[�A�P�[�u���Ȃǂ̃A�N�Z�T���[�ނ�
�@���ꂾ���ŃA���v��X�s�[�J�[�ɕC�G���鉿�i�̂����݂���B
6.�A�i���O�E�v���[���[�̃Z�b�e�B���O��1970�N��ȍ~�ɓ���ɂȂ�����
�@�f�W�^������ɐ�������[�r��Ă��邽�ߍ��z�ɂȂ�₷���B
7.�A�i���O����͂Ȃ������ʔ���̃t�H�m�A���v�ɂ������Ă�
�@EQ�J�[�u�Ȃnj����Ҍ����̓��e�ɓ��ݍ��ݍ������Ă���B
��L�̉������
1.���m���������ɂ���Ύ��R�ł���B
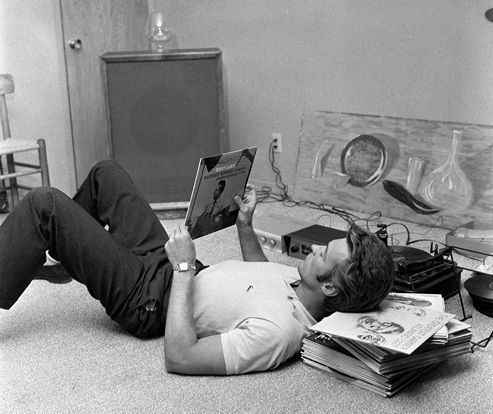
2.���m���������ɂ���E�[�n�[�̏d�v����Ɋ�����B
�@���ꊴ�ł̌떂�����������Ȃ����炾�B
3�`4.���m���������ł͏o���̃^�C�~���O�Ȃ�
�@�I�[�f�B�I�V�X�e���S�ʂ̃t�B�W�J���ȓ������̐S�ɂȂ�B
�@�^�C���R�q�����g�i�X�e�b�v�����j�͏d�v�ł���B
5.���m���������ɂ���E�[�n�[�̐U����ȊO��
�@����قNjÂ�Ȃ��Ă����B
6.CD�ł����ʂɒ�����悤�ɃV�X�e���������ق���
�@�����̐����炵�č����I�ł���B
7.���ʂɃA���v�t���̃C�R���C�U�[���g�p���悤�B
�@�^�[���I�[�o�[���S�œ������ł���悤�ɐv����Ă���B �����ėǂ����m�A���v���Ă���H
���ʂɃX�e���I�A���v�̂ق��������ĕ֗��B
������2way���`�����f�o�g���č��Ech������ƒ��ɕ�����
�}���`�A���v�Ŗ炵�Ă���B
�������ƌ����炵�̗ǂ��Ƃ����サ���Ǝv���B
�c�C�[�^�������Ńt�������W�ꔭ�̃��m�X�s�[�J�[���Ȃ�ׂ��V���v���ȍ\���Ŗ炵��������
�\�[�X�̓X�e���I������~�L�T�[�ō�������X�e���I�C�����m�A�E�g�̒��A���v�݂����̂ǂ����Ǝv�������ǁB
�������ŏ��͒��f�W�A���Ń��N�n����炵�Ă�����
�����n���̂���̂̓I�[�o�[�V���[�g�Řc��ł������炾�����B
�t�ɍ����g�m�C�Y��}�����������͉̂��ʂ͏o�Ă����������o���h���l�܂�B
���̕ӂ̉���������A�ǂ̐��i���^�ۗ��_�Ȃ̂͊�{�v����������������B
�����̂�DC�������R��Ă������A�t�B���^�[�Ȃ��Ō��C�����͂悩�����B
���ʂ�5���~���x�̍��YFET�v�����C���ɏ�芷�����Ƃ���
�ƂĂ��f���ɉ����o�邱�ƂɋC�t���[���B
���Ȃ݂ɓ����t�������W�ł����m�������͎�45�x�Œ����ăt���b�g
���ʓ����͒������h�ڂ�5�`6dB�����グ������������B
1960�N��ȍ~�̂قƂ�ǂ̃t�������W�͐��ʓ����Ńt���b�g�B
����͍���̃`�����l���Z�p���[�V�����𖾗Ăɂ��邽��
�X�e���I�p�ɍ���̎w�������i��悤�ɐv���Ă���B
���m�����Œ����ꍇ�́A�������ɍ�����g�U����悤��
4�`10dB�قǗ��Ƃ����o�͂œ���܂���Ǝ��R�ɂȂ�B
���ƈ�ʓI�Ȑ��\��R�X�p�̘b����
��̓I�ɂǂ��������y��炵���݂������f�����
���������X�y�b�N���������邱�Ƃ��ł��邩������Ȃ��B
���̏ꍇ�́A1950�N��̃h�C�c�E�N���V�b�N�����^������n�܂�
1970�N��̗w�Ȃ�1950�`60�N��p�ă��b�N����V�X�e����������
���̃��m���������̕����ɑǂ�����B
���ł�1990�N�ȍ~�̌Êy�퉉�t�A2000�N�ȍ~��J-POP�Ȃ�
�c�{�ɂ͂܂��ă��m�����C�s���B
�̕��̃{�[�J�����Y��ɒ���������ł�
�̃��m�̏ꍇ�͑ш�I�ɋ����̂ŊÂ�����������
�@200Hz���t�@�b�g��100Hz�ȉ��͍i�����ق������̊��������i�j�����ʁj
�@500�`1500Hz���X�b�Ɣ��������ق����\��Z���Ȃ�i���ɓ��{��j
�@3�`6kHz�Ŕ{�����A�N�Z���g�����Ɣ������ǂ��Ȃ�i���ɉp��j
�����A�A���A�q���ɑ��ĐF�X�Ɨv���������B
�O���t�B�b�N�C�R���C�U�[�Ȃǂ��g����Ȃ玎���Ă݂�Ɣ��邪
100Hz�ȉ���10kHz�ȏ���{�[�J���ɂ͗v��Ȃ��B
�������������͐^��ǁ{�t�������W�ŗ���ꂽ���e�ł����邪
���ɍA���̕\��v��Ȃ��p�Č��ł̐v���L������
1�`2kHz�ňʑ����������ނ悤�Ȃ��̂��W���ƂȂ����B
���̎��_�Ń\�E���n�̃{�[�J���͗ǂ�������Ȃ��Ȃ�����
�̗w�Ȃ̓��W�J�Z�̂ق��������������₷���Ƃ����t�]���ۂ��������B
�l�I�ɂ͒���̔�����ǂ����邽�߂Ɍ�ʉ�����ɓ����̂��D����
�R�[�������t���t�����Ȃ��悤��Qts��1.0�ȏ�̃��j�b�g��I��ł�����Ƃ����B
���݂��� Visaton FR6.5 ���荠�ł�����������Ȃ��B
8cm���炢�̂ق��������{�[�J�����Y��Ƃ����l��������
���R�͋�������炸��800�`2500Hz�̍A�����N���A�ɕ������邩��B
������͏��^�o�X���t�p�ɐv�����Qts��0.3�`0.5�ɂ��Ă��邪
�����ʂ�150Hz���炢���烍�[���I�t���Ă���ق������̓N���A�ɂȂ�B
�A���v�̂��Ƃ������ƁA�����̓f�m���̃v�����C�����g���Ă��邪
MOS-FET�̃A�i���O�A���v���g�����R��
�B�����Ƃ��ăT���X�C�g�����X ST-17A�Ƃ������[�t�@�C�d�l�̃��C���g�����X���g����
�{�[�J���ɍ��킹���{�����o���₷�����Ă��邩���
�ǂ����f�W�^�����Ɛ܊p�F�t�������p���X�M�����t�B���^�����O�Œʂ�Ȃ�
�Ƃ����^�f�����@�ł��Ȃ�����ł�����B
�O�Ƀf�W�^���A���v�Ńt�B���^�[���Ȃ��ƍ����g�̃I�[�o�[�V���[�g�����邳��
�Ə��������A���̃X�p�C�N�m�C�Y�͊y�ȂɊW�Ȃ��A���v���L�̈�艹����
�g�����X�̏ꍇ�́A�y�Ȃ̉����ɍ��킹�Ĕ{�����o��Ƃ����Ⴂ������B
�������̂ɐ^��ǂ̃����M���O�m�C�Y�����邪�A������͒�����̉������ɏ��B
���C���g�����X���f�W�^���m�C�Y���������邾���Ȃ�
�����ƒቹ���������ʂ�Hi-Fi�ȓ����̂��̂������Ă��邪
ST-17A��MM�J�[�g���b�W�̂悤�Ȓg�F�n�̐F�����������čD�݂��B
�F�X�Ə��������ǁA���݂̃f�W�^�����L�ш�t���b�g��
�{�[�J�������ʓI�ɍĐ�����ɂ͕s�\����
�l�Ԃ̐��ɏœ_�̂����������̃v���|�[�V�����𐮂��Ȃ�������Ȃ��Ǝv���B
�R�A�Ȏ��g����͏d�ቹ�⒴�����ɂ���̂ł͂Ȃ�
�ނ���100�`8,000Hz�Ƃ������[�t�@�C�ш�̂Ȃ��̃v���|�[�V�����ł���
�{�f�B���C���Ɠ����悤�ɋ����A�A���A�q�������ꂻ�ꖣ�͓I�ł���ׂ����B
���Ǝ����̃V�X�e���ɂ��Č�����
Jensen C12R�Ƃ����M�^�[�A���v�p���j�b�g���g���Ă邪
�����Ƃ��Ă͍ō��̃v���|�[�V�����Ȃ̂����A�ǂ����N���t���Ȃ��B
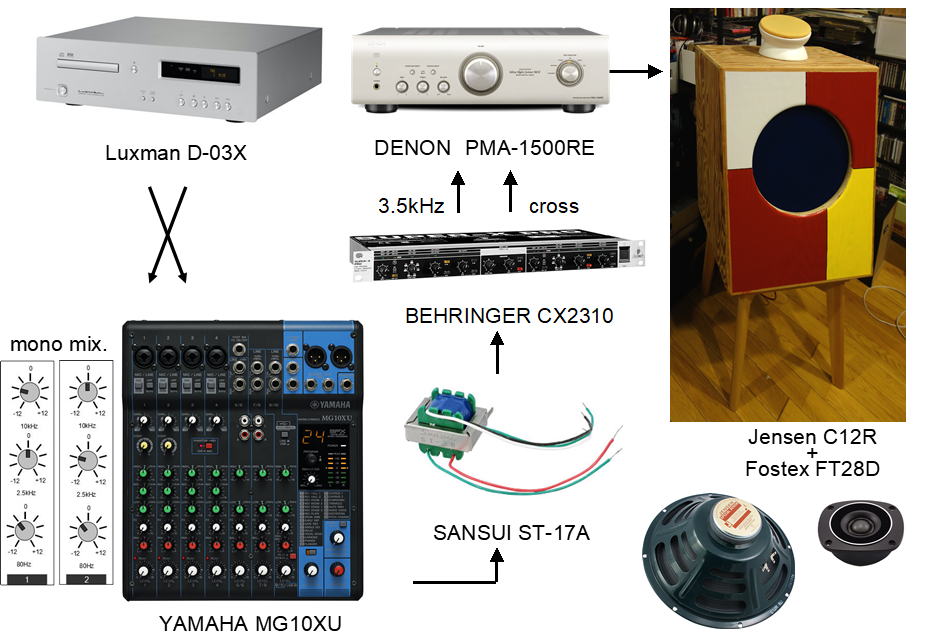
���̃��j�b�g��1947�N�Ƀ����[�X���ꂽP12R�̃Z���~�b�N���Δł�
�J�������͔ėp��PA�p�X�s�[�J�[�������B
1950�N���Rock-ola�ЂȂǃW���[�N�{�b�N�X�ɂ��g��ꂽ���i���B
���̃��j�b�g�̗ǂ���
1.�t�B�b�N�X�h�G�b�W�̃o�l�������ă~�b�h���[�܂Ŕ������ώ��ɑ���
2.Qts��2.0�ȏ�ƍ�����ʉ�����ł����肵�Ė�
3.�{�C�X�R�C����1�C���`�Ə����������悪�N���A�ɖ�
�@�����̃_�X�g�L���b�v���t�F���g�ŌŗL�������Ȃ�
4.�����U���������n�Ń��o�[�u���Y��ɏ��
5.�M�^�[���m�̂��߂ɐV�i�ň��������Ă���
��_�Ƃ����c
1.Fo��90Hz�t�߂ŏd�ቹ���o�ɂ����i�x�[�X���C���͖��Ăɕ�������j
2.�c�C�[�^�[�Ȃ��ł͌��݂�Hi-Fi�̊�ɖ����Ȃ�
�@��^�z�[���ɍ��킹��̂������i�����y������j
3.�M�^�[�A���v�p���c�݂��炯�Ɗ��Ⴂ����₷��
4.�r���e�[�W�I�[�f�B�I���D�Ƃ���̂܂��
Fo�������̂̓{�[�J����̖��Ă��ƃo�[�_�[�������
10cm�t�������W���ቹ���o�Ȃ���
200Hz�t�߂܂Ń_�C���N�g�ɐU���������邽��
�{�[�J���̎��̊��┗�͂͑S���Ⴄ�B ���Ȃ݂ɋC�ɂȂ�C12R�̕����U���i���c�݁j����
�����g�̗����オ��ɑ���u�X�e�b�v�����v���v�����Ă݂��
�V���O���R�[���Ɠ������Y��ȃ��C�g�V�F�C�v���悫�Ȃ���
��ʓI�ȃt�������W�ɔ�ׂ����ƃN���A�ł���B
�p�C�I�j�APE-16M�i�������U�j�̃X�e�b�v����
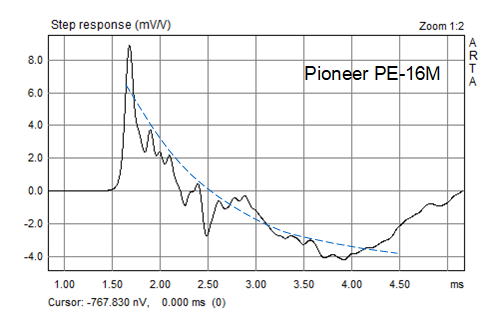
Jensen C12R�{Fostex FT28D�̃X�e�b�v����
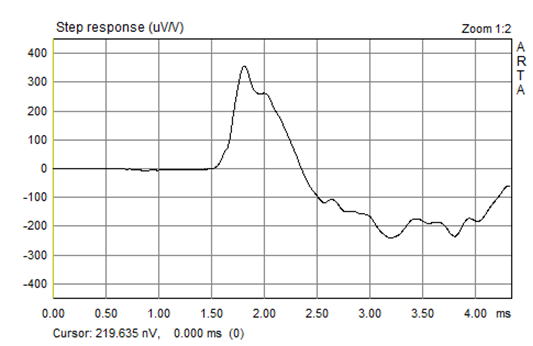
���̓M�^�[�A���v�̃f�B�X�g�[�V������
�A���v�̐^��ǂ��ߓ��͂Řc�܂������ł���
���������������ʓI�ɍĐ����Ă��邾����
�X�s�[�J�[���̂��̂̉��͂ނ���N���A�Ȕg�`���Ɣ���B
1ms�ȉ��̃f�W�^���I�ɊςĂ����Ȃ萳�m�ł���_�ł�
���ꂪ�{����75�N�O�̉����Z�p�Ȃ̂��Ƌ�������ł���B
�X�e�b�v�����Ɋւ������͈ȉ��̂Ƃ���B
https://www.stereophile.com/content/measuring-loudspeakers-part-two-page-3 �l�I�ɂ̓{�[�J���̕��G�Ȕ����@�\�̍Č��ɂ�
�^�C���R�q�����g�i���ԓI�Ȉ�ѐ��j���d�v���ƍl���Ă���
�Ⴆ�A�ʏ�̃}���`�E�F�C�ł͎q������ɗ�����
�����͒x��Ă���Ă���̂����ʂ̕\���ɂȂ��Ă���B
���ۂɂ̓u���X���狹������������^�C�~���O������
���̃��Y����^�������y�\���ɐ[���ւ���Ă���B
���̑��̏㉺���铮���́A���\�����X�s�[�h��
���艹�̃p���X�����ƈꏏ�ɐ����o�Ă���B
�����Ēቹ���x��Ă���悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��̂ł���B
�����ЂƂ͂��̒x�ꂪ1ms�ɒB���邱�Ƃ�
����̗����オ��Ƀ}�X�L���O����ĞB���ɂȂ�_�ł���B
1ms�͐����Z�����ԂɎv����������Ȃ���500Hz�̔��g���ɑ�����
����ȉ��̎��g���A������200Hz�ߖT�̕\�����قƂ�Ǖ����B���Ă��܂��B
�����������ԓI�ȕs�����̓V���O���R�[���ʼn�������邪
���^�t�������W��800Hz�ȉ����G���N���[�W���[�̋��U�ŕ₤�̂�
�X�e�b�v�����̌v���ł͔���Ȃ��������ŏ_�炩���g�`�Œx��Ă���B
10cm���x���̏��^�t�������W�Ŗ{�i�I�Ȃ��̂��o���̂�
1965�N�̃t�H�X�e�N�XFE-103���ŏ���
����܂ł̏��^�X�s�[�J�[�͌g�у��W�I�p�̂��̂�
�Đ��ш��200�`4,000Hz�𒆐S�Ƃ����J�}�{�R������������
���^�t�������W�Ƃ����W���������J���������O�Z���[�ł���B
���̂ق��ɓ��{���̏��^�t�������W���j�b�g��
�e�N�j�N�X�A�p�C�I�j�A�A�R�[�����ȂǗl�X�ɔ̔����ꂽ�B
����ɑ�����1968�N������Altec 405A��
��`�A�i�E���X�̓V��X�s�[�J�[�Ƃ��Ă��g�p����
������250�`8,000Hz���t���b�g�ɂ����J�}�{�R�^����
30cm�����̖����ɓ���邱�ƂŐl�Ԃ̐��̓����Ƀt�B�b�g����Ƃ���
�A�����J�̉����w��̕W���I�ȃ��j�b�g�Ƃ��Ă����p���ꂽ�B
1970�N�ォ��^���X�^�W�I�p�Ƃ��Ă̓I�[���g�[��5c���L����
�t���b�g�ȗ̈悪150�`12,000Hz�Ƌ������̂�
������ʓI���������W�I���X�i�[�̊���T�E���h����Ɍ������Ȃ����̂������B
�ꎞ�����Y���~�������A���݂ł͍Đ��Y���͂��߂Ă���B
1990�N��ɂ�BOSE 101���p���[�n���h�����O���������Ƃ�
���C�ݕ��̗�����������������`���āA�X��PA�ȂǐF��ȏꏊ�Ō��������B
BOSE�̓����ɓd�����g�����C�R���C�U�[��������
�����ʂ̂Ƃ��͒����u�[�X�g�A���ʂ��傫���Ȃ�ɂ����������ɒ�R��������
�Ƃ����ς�����@�\���t���Ă������A���ꂪ���^�t�������W�̎�_�������B
�s��Ɉ�ԃC���p�N�g�̂������̂́A�T�e���C�g�X�s�[�J�[�ƃT�u�E�[�n�[��g��
501�V�X�e����������������Ȃ��B���̍���SR�s��ł��D�ʂɂ�������
1970�N���JBL�������悤�Ȍo�܂������Ă������ƂƏd�Ȃ��Ă���B
����BOSE�̃��E�h�l�X�����������T�E���h��
����ł͏��^�t�������W�̋@�q�Ȕ������������Ƃɂ��Ȃ���
����h�̃I�[�f�B�I�}�j�A����ᔻ�����悤�ɂȂ�B
10cm�t�������W���o�n�߂��������ƂȂ����̂��\���̒Ⴓ��
���^�ł���ɂ��ւ�炸�A�^��ǃV���O���ł͑���Ȃ������������B
�����30W�N���X�̃g�����W�X�^�[�E�A���v�������ɏo��邱�Ƃʼn������ꂽ��
�ނ��돉���̃J���J������OTL�g�����W�X�^�[�A���v�̉����Əd�Ȃ���
10cm�t�������W�̖��ĂȃT�E���h����܂��Ă������悤�Ɏv���B
�����g�����W�X�^�[�ł��g�����X��g�ݍ��ނƃ}�b�L���g�b�V���̂悤��
�R�b�e�����������ɂȂ邱�Ƃ����肦��B
���^�t�������W�͂悭���W�J�Z�p�Ɠ����i�ƊԈ����̂���
���W�J�Z�͌�ʉ����➑̂ɓ���邽�߃t���[�G�b�W�̂��̂͂����ꕔ��
����I�[�f�B�I�p�ɔ����Ă�����̂̓o�X���t���ɓ����悤�v���Ă���B
��ド�W�I�ɕ����p���j�^�[�Ɠ����i�ƃ��[�J�[�Ő�`���Ă����Ƃ��Ă�
�������ꂽ�̂̓t�B�b�N�X�h�G�b�W�̕ʕ��������Ƃ����͓̂�����O�������B
�����P610�����Ă��X�J�X�J�̉������o�Ȃ��͖̂�������
�p�i�\�j�b�N�ł��L�ш�iHi-Fi�j�����̃e�N�j�J���E�K�C�h��
���l���W�I�ɍ����t�������W�����Ă�����200Hz�������
�����������ʂ��f�ڂ��ꂽ�肵�Ă����B
�����\��10cm�t�������W���J�����ꂽ�w�i�ɂ̓X�e���I�^���̕��y������
�X�s�[�J�[��2��u���X�y�[�X����ōς܂������j�[�Y�͓������獂�������B
�X�e���I�d�~�̂ق��͂Ƃ����ƁA�X�s�[�J�[2�{����ׂĎ��߂����i������
�Z���~�b�N�J�[�g���b�W�̃N���X�g�[�N������10dB�ȉ������������B
�����̃|�b�v�X�ɑ��������f���I�E���m�����̃X�e���I������
�Ȃ���ăX�e���I���u�̕��y�Ƃ��W����������������Ȃ��B
�������������2�{��ʁX�̔��ɓ���ăX�e���I���ʂ𖾗Ăɂ�
�������X�y�[�X�t�@�N�^�[�̗ǍD�ȏ��^�t�������W�͏d�ꂽ�B
����ŁA�����X�y�[�X�ŃX�e���I���ʂ��o�����߂̍H�v�Ƃ���
4kHz�ȏ�̍���Ŏw������30�����ɍi�邱�Ƃ�
�`�����l���Z�p���[�V�������҂���ʊ����o�����Ƃ��v�Ƃ��čs����B
�X�s�[�J�[�����ʂ������Ȃ���ΐ������o�����X�Ƃ͂Ȃ�Ȃ�
�Ƃ������Ƃ�����ɃX�e���I�����̃}�i�[�Ƃ��Ē蒅���Ă������B
����ȑO�̃��m�����p�t�������W�͎�45���Ńt���b�g�ƂȂ�悤
�������h�ڂɎ����グ������������Ă����B
Goodmans�ł�AXIOM80�͋��^�AAXIOM301�͐V�^�̐v��
JBL�ł�D208�����^�ALE8T���V�^�̐v�ł���B
���FPA�p�ƌ����鉹�������A���W�I�ł����l�̉����̂��̂��g���
1970�N��ɂ����Ă��Ɠd���i�̉����v�Ɉ����p���ꂽ�B
Lowter PM6�Ȃǂ͍��ł������̐v���@�������p���ł��邪
�ނ���o�b�N���[�h�z�[���ɓ���ăh���V�����Ŗ炷�����Ő����c���Ă���B
�t�H�X�e�N�X FE-206�����[�T�[�̌n���ɂȂ��邱�ƂɂȂ邪
Q������0.2�܂ʼn�����̂ŁA�ʏ�̃o�X���t�ł̓I�[�o�[�_���s���O��
��悪�o�ɂ����Ȃ�Ƃ������ۂ��N����B
�����Qo��0.26�Ƃ��ɘa���ăp�X���t���ł��g����悤�ɂ��Ă���B
������t���b�g�u���Œቹ�̏o�₷��FF�V���[�Y�ƕ��s���Ă���
�X�e���I�p�r�̊�{�I�ȃX�^���X���������Ă���B
�u���O�ǂ̂Ŏ����12�C���`���̐��@�����ĉ�����
�c�C�[�^�ȊO�������̍��̂�
�ŋ߂̃t�H�X�e�N�X�̕ω��ɂ��Ă�
FE-103��50���N�L�O�ŏo���ꂽsol�V���[�Y�őł��o���ꂽ
PA�I�ɍ����h�ڂɔ��U���鉹���ł���悤�Ɏv���B
�܂�p�[�\�i����Ԃł̃X�e���I�����ł͂Ȃ�
�X�s�[�J�[�Ŋg������V�`���G�[�V���������y�̋��L�Ƃ���
�R�~���j�e�B�̌`���̌������J���I�Ȋ������f����B
���̈Ӗ��ł�en����NV�̕ω���������
en�܂ł̃t���b�g�ȃ��X�|���X����
NV�ł̃��J�j�J��2way�Ɏ�����_�ȃv���|�[�V�����ɂ��݂ĂƂ��B
���������X�������m�����Đ��ɂǂꂾ���L�����͂܂��悭�킩��Ȃ��B
�Ⴆ�A���W�J�Z�Ɏg���Ă����悤�ȕ����U���̋����d�l�Ƃ�
�܂��Ⴄ�����ɂ��v����B
http://www.toptone.co.jp/products/full/F120C85-1.html
���W�J�Z�Ƃ����Ɠ��{�ł͈����Ƒ��ꂪ���܂��Ă��邪
�A�����J�ł̓q�b�v�z�b�v�̘H�ド�C�u�ł��Ȃ�g���Ă����B >>87
12�C���`�p���̓A���e�b�N618B�^�̔w�ʂ��O�������̂��g���Ă�B
��45cm�A����56cm�A���s24�`33cm
�o�b�t��18mm�A�T�C�h10mm�̕ď������g�p
618���͊Nj������ŗL���ɂȂ����̂Ő}�ʂ��l�b�g�Ō����ł��邪
��ʉ���Ŏg���ꍇ�͂����������s�������炵�ē�����Ȃ����Ǝv���B
�o�b�t�����{���ʁ~2��1m���x�Œ�������ƊT�˓����ɂȂ�B
�߃o�b�t���͂��Ƃ��ƕNJ|���p�̐v�Ȃ̂œ��ɕK�R���͂Ȃ��B
�̖̂ؐ����W�I�́A�X�s�[�J�[�ƃo�b�t���𖧒�������
�������Ԃ��邪�A���̂ق����o�b�t���̌ŗL�����o�Ȃ��B
���i�ɂ���Ă͔���̃T�u�o�b�t���Ƀl�W�~�߂��Ă������邪
�ŏ��͊��蔢��ܗk�}�ȂǂŌ��Ԃ��������ČŒ肷��Ƃ����B
Jensen�̐V�i�̓G�[�W���O�Ɏ��Ԃ�������̂�
�ŏ��̉����X�J�L���ł��C���������ɋC���ɕt��������
���̂����X�s�[�h���̑�������悪�D���ɂȂ��Ă���B ����Jensen C12R�Ƃ͈Ⴄ���j�b�g���������Ă���̂ł����
��ʉ���ɓK����Qts�̍����t�B�b�N�X�h�G�b�W�̂��̂�
�o�X���t�ɓK����Qts�̒Ⴂ�t���[�G�b�W�̂��̂�
����12�C���`�ł����҂�1950�N�ォ�獬�݂��Ă���B
�L���ȃ��j�b�g JBL D123�A�G���{�C SP12B�A�g�D���[�\�j�b�N120FR�Ȃǂ�
��{�I�Ƀo�X���t���i���Ȃ�J���̑傫���j�ɍ��킹�Đv����Ă���B
���{�̉Ɖ��ɍ��������Ƃ��ăI���P���^�̃E���g���o�X�t���b�N�X������
�����ɏd�ቹ���҂����悤�ȕs���R�������������ቹ��������B
2way�X�s�[�J�[��1930�N�ォ�獂���d�~�Ŏg���Ă����̂�
���łɍ����L���K�v�͂Ȃ����A�V���O���R�[���ɂ������K�v�����Ȃ��B
12�C���`�Ƃ��Ȃ��6kHz�ȏ�̍���͋}���Ƀ��x���_�E�����邵
�N���X�I�[�o�[��3kHz����ƈʑ��x��͖ڗ����Ȃ��Ȃ�B
Fostex FT28D�͂܂����������ȃ��j�b�g����
�t�H�X�e�N�X�̃��j�^�[�X�s�[�J�[NF-1�ō̗p���ꂽ�Ƃ���
HP�E�[�n�[�̔����̑��������������߂�
����Ƃ͔��̐��i�̃c�C�[�^�[��I�炵���B
https://www.miroc.co.jp/report-development/170426-fostex/
�������Ƃ�Jensen RP103�ɂ������āA�����Z���̃_�C���t�������g����
��r�I���₩�ȉ��̂�����̂��I��Ă���B
����Jensen C12R�ɍ��킹��̂ɐV���ɃL�����N�^�[��������
�s�s���̂Ȃ��͈͂�10kHz�܂ł�ۏ���Ƃ����X�^���X�őI��ł���B >>89
���J�Ȑ������肪�Ƃ��������܂�
�߃o�b�t���͖������Ė؍ނ��������̂͗p�ӏo���܂��T�˓����T�C�Y�̂��̂�����Ă݂܂� ����Jensen�̃M�^�[�A���v�p�ł��㎥�^A12�̌�p��
�R���T�[�g�d�l��P12N��Qts��0.77�ƂȂ��Ă���
��^�̃o�X���t�ɍ��킹�Đv����Ă���B
https://www.jensentone.com/vintage-alnico/p12n
�W�F���Z���Ђ�1940�N�ォ��ƒ�p�̃o�X���t�����Ă���
�ނ��듯��2way�Ȃǂƍ��킹�ϋɓI�Ɏg�����j���������B
����̗����łł���P12R��Qts��2�ȏ�̕��ʃo�b�t��������
�M�^�[�A���v��W���[�N�{�b�N�X�Ƃ��������K��PA�p�ɐv����Ă���B
���҂̃L���r�l�b�g�̈Ⴂ�́A�M�^�[�A���v����������������邽��
�X�s�[�J�[���M���M�����܂�傫���Ƀo�b�t�����k�߂Ă���
�W���[�N�{�b�N�X�͒ቹ��������x�҂�����
�G�N�X�e���f�b�h�����W�Ƃ��Ă͏��ʃX���X���̈ʒu�ɔz�u��
�L���r�l�b�g�����s���̐[�����̂ɂ��Ă���B �A���e�b�N618���́A���W�I�Ǘp�̉������j�^�[�Ƃ��ĊJ������
�A�i�E���X�����ĂɂȂ�悤�Ƀo�b�t���ʂ���r�I�������}���Ă���B
���̔��̂��߂̃A���e�b�N600B�́A604����2way�ɔ�T���߂ȃ����W�ł���B
http://www.lansingheritage.org/html/altec/catalogs/1949.htm
1940�N�㖖��FM������LP���R�[�h�ւ̊��҂����������̂�
������AM������SP�Ղ��܂��܂����݂�
�ނ���100�`8,000Hz�̋��K�i����������o����d�l��
���e��1�I�N�^�[���L����50�`15.000Hz��Hi-Fi�K�i�Ƃ����݂��Ă���
JBL D130��Jensen C12R�͐ܒ��I�ȃG�N�X�e���f�b�h�����W�ƂȂ�B
�Ƃ��낪���̃G�N�X�e���f�b�h�����W�̃|�e���V������
���|����̒��r���[�ȃX�y�b�N�Ƃ͗�����
�}�C�N�̐������g�����Ă��j�]���Ȃ����̋���������
SP�ՂɃ_�C���N�g�J�b�g���ꂽ�u���[�X�^���ł���������
20���I�̃��C�u�E�p�t�H�[�}���X������Â��鍪�{�I�ȗ͋��������B
�������ł��邪�����̂悤�ɖ����ȃf�W�^�����ゾ���炱��
�T�E���h�|���V�[����������Ă�����ׂ����낤�B >>91
��ʉ�����ƃ��j�b�g�̃_�C���N�g�ȐU���������Ă���̂�
����͂���قǏd�v�łȂ��Ȃ銴�������܂��B
���[�Y�i�u���ȃ��m�����V�X�e���\�z�̂��������F��܂��B ���m�����X�s�[�J�[����������ꍇ��
�X�e���I�Ɠ��������ʂɑΛ����Ē����悤�ȃ��C�A�E�g
�܂�X�e���I�̒����ɒu���̂����邱�Ƃ�������
��������m��������̎ʐ^���݂�ƈႤ���ƂɋC�t���B
�N���X�s�[�J�[�𐳖ʂŒ����Ă��Ȃ��̂��B
BBC���j�^�[���[��
�@
�@
��DDR���j�^�[���[��
�@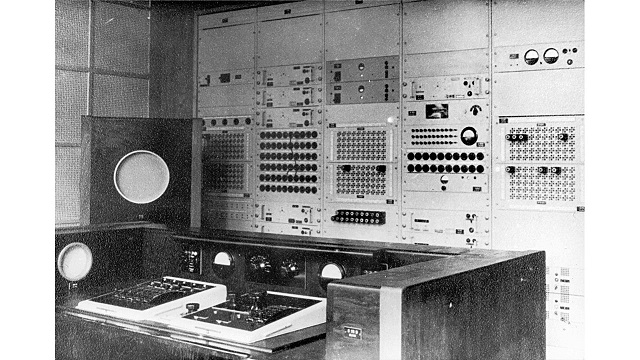
RCA�X�^�W�I
�@
EMI�A�r�[���[�h�i�E���̃��m���������Ŏ����j
�@
�@
�߂��璮���ăt���b�g�ȓ����ɂȂ�Ƃ����̂�
�L���w�����̕K�v��PA�X�s�[�J�[�݂̂Ȃ炸
��ʂ�Hi-Fi�X�s�[�J�[�ł����l�������B
���̎�̃X�s�[�J�[�Ō��݂̃X�e���I�^�����Đ������
�T�E���h�X�e�[�W�ȂLj�ʂ̕ǂɓh��ւ�����̎����邱�ƂɂȂ�B ���̋t�̂��Ƃ��l�����
1960�N��܂ł̘^�������݂̃X�e���I�X�s�[�J�[�ōĐ������
�@�G�R�[���[���ɓ��ꂽ�{�[�J���̉�����ʂ͑O��W���t�]
�@�V���o������ԑO�ɏo�ăL�b�N�h���������Ɉ�������
�@�I�[�o�[�_�u�����p�[�g����\�肵���悤�ɕ����o��
�ȂǂȂǂ̒����ۂ��N����B
PA�I�ƌ����鉹���̂����ЂƂ̓�����
����т��ǂ��A�������X�s�[�J�[�̈���O�ɏo��
�Ȃǂ̃v���[���X�i���̊��j���O�ʂɏo�邱�Ƃ�����B
JBL�ږ�̃W�����EM. �A�[�O����������
�u�n���h�u�b�N�E�I�u�E���R�[�f�B���O�E�G���W�j�A�����O�v�ɂ�
500�`2,000Hz���{3dB/oct�ʼnE���オ��ɏグ���C�R���C�W���O���{����
�u��������O�ɏo��v�悤�ɕ�������ƃR�����g������
����͂��̂܂܃��m���������PA�X�s�[�J�[�ɓ��Ă͂܂�B
���m�����ʼn����X�s�[�J�[�̉��Ŗ�����A�܂Ƃ����悤�ɖ�Ȃ�
����͒����Ɏ��s���Ă���Ƃ�������B
�^��ǃA���v�ł����ł̓g�����X�̐��\���ǂ��Ȃ���
�T�E���h�X�e�[�W���]���ɂ����A�F�����Ė点����̂���������
���Ă̓g�����X�̐F�t�����ז����ăX�e���I����j�Q���Ă����B
1970�N��ȍ~��MOS-FET��OTL��H������ɂȂ������R��
FM�X�e���I�����Ƃ̊֘A��������A�W���I�ȃT�E���h�X�e�[�W���F�����ꂽ��
1960�N��܂ł̃X�e���I�E�J�[�g���b�W��
�I���g�t�H���A�V���A�[�Ȃǂ̍����i�ȊO�ł̓N���X�g�[�N������
�G�R�[���������ŃX�e���I�̉��ꊴ������ƌ������Ă����X��������B
ECM���R���T�[�g����JAZZ�^��������Ƃ���������������̂��B
�X�e���I�@��̊�{�v��1960�N��Ɋ������Ă������Ƃ�z����
�Z�p�����̐Z���ɂ́A�Ȃ������Ԃ�v�������ƂɂȂ�B
�t�Ɍ����AHi-Fi�^���̔��W�j�̑唼�̓��m�����ł��\���ł���
�X�e���I�łȂ���Ȃ�Ȃ����y���܂����Ȃ����Ƃ�����B
����͐i�������ƌ����錻�݂̘^���Z�p�ɂ��Ă�
�}�C�N���^�ƃX�s�[�J�[�Đ��̊�b�Z�p��1950�N��ƕς���Ă��炸
�f�W�^�����^�ŏ������̂悤�ɑf���ȉ��ɂȂ�Ȃ�ق�
�l�Ԃ̒��o�ɍ��킹�����E�h�l�X�̍œK�����ۑ�ɂȂ��Ă���B
���m���������͎���x��̃g�b�v�����i�[�Ƃ�������̂��B
Hi-Fi�^���̌��`��
�}�C�N�̉����A���v�ƃX�s�[�J�[�Ŋg�����邱�Ƃɂ��邪
���̑����I�ȃp�t�H�[�}���X��^���Ƃ�����i�Ŏ��n������炵���̂�
�I�[�f�B�I�Z�p�ƂȂ�B
�e�[�v�^�����n�܂������̈�Ԃ̖ڋʂ̓v���C�o�b�N��
�A���e�b�N�����W�Ƃ��Ă��u�����������v�Ƃ����s�ׂ�
�^�������Ẳ��t���I�����������̃`�F�b�N�ɂƂǂ܂炸
�ǂ̂悤�ɒ����Ă��炢�������̐ϋɓI�ȉ���
�~�L�V���O�ɂȂ����Ă������B
�����̑n���I�ȃ~�L�V���O�̑��l�҂�
�G���L�M�^�[�ŗL���ȃ��X�|�[��������
�}���`�g���b�N�ł̃I�[�o�[�_�u�ɂ��
�d�q���y�ɋ߂��V�������y�X�^�C�����J�Ă����B
�X�e�[�W�E�p�t�H�[�}���X���|�Ƃ��郍�b�N�ɂ�����
���������l�H�I�ȉ��y����͂���قǐi�W���Ȃ�������
�Ⴆ��1970�N��̃N�C�[���̂悤�ɃX�^�W�I���[�N���S��
���C�u�^����ϋɓI�Ɏc���Ȃ������o���h�Ȃǂ�
�V�����X�^�C���̃��b�N�o���h�Ƃ������Ƃ��ł��悤�B
����ŁA�N�C�[���������ł͖{�̂��ł��Ȃ��o���h�Ƃ������Ƃ͂Ȃ��B
�܂��u�I�y�����v�̂悤�ȃA���o�������m�������Ɩ��͂��������邩�ƌ�����
���ۂɒ����Ă݂�Δ��邪�A�ނ���p�t�H�[�}���X�E�o���h�Ƃ��Ă�
�K�b�c���������킢��1960�N��̃o���h�ɕ�������炸�����B
�ނ���X�e���I�Đ��Ŋe�p�[�g�̉������ו�������邱�Ƃ�
�o���h�̈�̊����킪��Ă���悤�ɂ�������̂��B
�{�w�~�A�����v�\�f�B�[�̃R�[���X���^�̃w�b�h�z�����j�^�[��
�{�����[���R���g���[���̊������炵�ă��m�����Œ����Ă邩������Ȃ��B
�_�E�����[�h���֘A���恄��
�������Ƃ̓s���N�t���C�h�́u���C�v�ł�����
21���I�ɓ�����5.1ch�T���E���h�E���~�b�N�X�Ȃǂ��o����
�����̎ʐ^���݂�ƃI�[���g�[��5c�Ń��m�����������`�F�b�N���Ă���B
��������W�I�ł̃v�����[�V�������Z�[���X�ɐ[���֘A���Ă����Ƃ�������
�����̉p���̎�҂̑��������m�����̑��v���[���[���g���Ă���
���{�Ŋ���s�[�^�[�E�o���J�����������������B
�Z���~�b�N�J�[�g���b�W��ECL82�Ɍq���ȉ~�X�s�[�J�[��炷�悤�Ȃ��̂���
����ł��p���̃��b�N���㎿�Ȕ��W�𑱂����̂�
���m�������������y�̖{���������Ď���Ȃ��؍��ł�����B



�{�[�J���u�[�X���^���X�^�W�I���ɕ��݂��ꂽ�̂͂���قnjÂ��b�ł͂Ȃ�
1960�N�㔼�ɃJ���t�H���j�A�̃T���Z�b�g�E�X�^�W�I�ł͂��܂����B
���̗��R�͂Ƃ����ƁA�f�B�Y�j�[�f��̎d�����ꏏ�ɂ��Ȃ��Ȃ���
���ɃX�g�����O�̃Z�b�V�������ꔭ�^��ɓq����̂͑���Ȏ��Ԃ�v�����̂�
�A�C�\���[�V�����E�u�[�X�Ƃ��ēƗ����������Ŏ��^�����̂��͂��܂肾�����B
���̂��ƂŃX�^�W�I�̉ғ�������C�ɏオ������
�{�[�J���u�[�X�Ƃ��ēƗ������̂��A�V��������̃o���h�����������Ȃ̂�
�A�����W���ϋl�܂�܂ʼn��x���{�[�J����^�蒼���̂Ɍ��C�����������炾�Ƃ��B
�h�A�[�X�A�u���W��'66�A�^�[�g���Y�A�����A�`���b�g�E�x�C�J�[�Yetc�c
�ǂ�Ȉ����������}���`�g���b�N�ł��Ȃ��Ă������Ƃ����B
�}���`�g���b�N���^��1970�N��ɓ��蕁�y������
1960�N�㖖��16ch���x�������̂��w���I�ɔ{�X�Q�[���̂悤�ɑ������B
�̗w�Ȃ̃A�����W���[�̓����f�B�[��s�ł���y�Ȃ͑薼���܂��Ȃ�
�Ō�Ƀe���r�Œ��������ɂ́A�����̃A�����W���������o���Ă��Ȃ����炢
���Z�ŕ��G�Ȍo�H�Ŏ��^������Ă����炵���B
����ł�1980�N�キ�炢�܂ł̓|�b�v�K�[�h���g�킸��
�}�C�N����20cm���x�����ă{�[�J�������^���Ă���
���̂̉������\�����Ă����B
�A�C�h���̎肾���Đc�̂��鐺�ōĐ������
�t�B�W�J���ȋ��x���ɋ�����������Ȃ��B
�|�b�v�K�[�h���g���ă}�C�N�������܂ŋ߂Â���悤�ɂȂ����̂�
1990�N��ȍ~���Ǝv�����A�f�W�^���Ή��ł̃m�C�Y����������̂��낤���B
�ނ���CD�E�H�[�N�}���Ȃǃw�b�h�z���ł̎��������S�ɂȂ������炾�Ǝv���B
�����ʼn̏��͂��̂��̂��キ�Ȃ����Ȃ�Ă̂͑S���̓s�s�`���B
1950�N��̃u���[�X�̎���K���K���ɋߐڃ}�C�N�������B

�ǂ�ȂɎ��オ�ς�낤�ƁA�l�Ԃ̐��̖{���͕ς��Ȃ��B �{�[�J���̐��̐c�Ƃ�����1�`2KHz�t�߂̍A���̃N���A�l�X��������������
�����̗̈�ƂȂ�200Hz�ߖT��
�j���̐��̍����Ȃ��̊i���甭��������̂�
�W�����EM. �A�[�O�����u�n���h�u�b�N�E�I�u�E���R�[�f�B���O�E�G���W�j�A�����O�v��
�{�[�J����Z���ɂ���ш悾�Ɛ�������Ă���B
�}�C�N�ɂ͋ߐڌ��ʂ�����A�����ɋߊ��100Hz�ߖT���c��邽��
�̎肪�����ŋ����̑ш���R���g���[���ł���悤�ɂł��Ă�B
���J�r���[���̃}�C�N�̎g�����ŁA�������킴�Ɣ킹�邱�Ƃ�����B
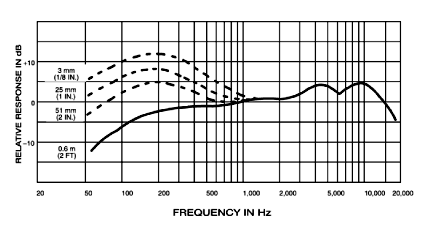
����ŁA1970�N��܂ł̘^���X�^�W�I�ł�
�}�C�N����1�t�B�[�g���炢������u���ăm�[�}���ɘ^���Ă�������
���������l�H�I�Ȓቹ�̖c��݂͉������悤�ɂ��Ă��邪
�㔼�g�̂��甭���鐺�͏E���Ă��邽�߁A�ނ��당���͎��R�ɓ����Ă���B
�����ʼnۑ�ƂȂ�̂��A�����L�������̎��g���p�����X�ł͂Ȃ�
�ނ��당�����u���X�ƘA�����ĉ̐��̌ۓ���`���Ă���_�ł���B
�y���ȃ��Y��������ł��邱�Ƃ�����A�[�����ߑ��̂悤�Ȃ��̂�����B
���̃u���X�̂��@�q���Đ�����ɂ̓E�[�n�[�̃_�C���N�g�ȐU�����K�v��
�X�s�[�J�[�a�ʃo�b�t���Ɍ����ĂčŒዤ�U���g�����v�Z�����
10cm��850Hz�A20cm��425Hz�A30cm��283Hz�ƂȂ�
���傤�ǐO�A��ʁA���̂Ƃ����ӂ��ɉ̎�̉�p���ς���Ă����B
����ȉ��̑ш�̓G���N���[�W���[�̓I���t�ˉ��Ŕg�`������邽��
�~�b�h���[�̑ш�ŋ@�q�Ȕ���������ɂ̓X�s�[�J�[�a�������Ă��邱�ƂɂȂ�B

�t��8cm�t�������W�������{�[�J�����Y��ɍĐ�����Ƃ����̂�
�������L�̑��t�H���}���g���Y��ɐ蔲����
����ȉ��̑ш���ڂ����Ă���邱�Ƃɂ��B ����ŁA�����̑ш�200Hz�ߖT�ŋ@�q�ɔ����ł���悤�ɂ����
�Â����J�r���[���Ɛ����X�E�B���O���Ă���A�g�̂��Ɩウ��悤�ȕ\�����
1970�N��ȍ~�̃J���C�C�����̈�ۂ̃A�C�h���̎�ł�
�_���X�Œb�����^�����̍����t�B�W�J���Ȋ��o��������Ă���B
������^�C�~���O�������āA�U���̏d�����E�[�n�[�ł͒ቹ��������邾����
500�`2,500Hz�̍A���Ɠ����@�q���Ŕ������Ȃ�������Ȃ��B
�Ƃ��낪���݂̃E�[�n�[�̐v�͏d�ቹ���o�����߂̋@�\�ɓ�������
�������A�������܂��Đ��ł��Ȃ����̂������B
���g���I�ɂ͐����Ă��邪�A�^�C�~���O�������ɉ���Ă���̂��B
https://www.stereophile.com/content/measuring-loudspeakers-part-two-page-3
���������{�[�J���g��ōĐ�����@�\�́APA�@��Ƃ��Ă̎g�p���z�肳�ꂽ
�Â��v�̃G�N�X�e���f�b�h�����W���������킹�Ă���B
100�`8,000Hz�Ƃ����E�[�n�[�ł��t�������W�ł��Ȃ����r���[�ȃ����W��
�܂��Ƀ{�[�J���̃p�t�H�[�}���X���g�����邽�߂ɊJ�����ꂽ�Ƃ�����B
https://www.jukebox-world.de/Forum/Archiv/Rock-Ola/R.O.1455.htm
�G�N�X�e���f�b�h�����W�ōĐ�����{�[�J���ш��
���J�r���[����J-POP�܂ŁA��т����̐��̖ʔ�����`���Ă����B �ł̓G�N�X�e���f�b�h�����W���S�ėǂ����Ƃ�����
�����̎g���Ă���Jensen C12R�̓{�C�X�R�C���̋��U���s�[�L�[���₷���B
����͌Â��v�̃t�������W�ł��������̂�
�X�e�b�v�������݂�ƃs���Ɠ˂��o���ш悪���邱�Ƃ�����B

�i��}�F�t�B���^�Ȃ��A���}�F3.5kHz�n�C�J�b�g�j
�����3.5kHz�ŃJ�b�g���Ă������
���U���̂��̂͌���Ȃ��̂ʼn������x���ł͂ق��5dB�����邾������
�p���X���̃s�[�L�[���͏o�������Y��ɏ����ł��Ă��邱�Ƃ�����B
�t�ɂ���ȏ�J�b�g�I�t���g����������ƁA�����オ�肪�x��ē݂�B
�����͋��p����肷���Ȃ��悤�ɁA���������Ɏ��߂�̂��̂ƂȂ邪
�J�b�g�I�t���g���̉����́A�{�C�X�R�C���a1�C���`��C12R�ł�3.5kHz����
4�C���`�a��JBL D130��2.5kHz�ƁA���j�b�g�ɂ���ĈقȂ�B
���Ȃ݂�1950�N��̃r���e�[�WD130�͎��C�Ńo�����X���ς��
���C�̑������̓A���~�Z���^�[�L���b�v�̉������ڗ�������B
C12R�͂����܂ł����Ȃ����A�u�J�̂�����v�̖@��������炵��
�J�オ��̐��ꂽ���ɋC�����悭�����オ�銴��������B
��������̑����Ƃ�����A�����J���Ȋy�ώ�`�Ǝv���Ē����Ă���B ���{�̃j���[�~���[�W�b�N���A�����J���Ƃ݂邩���[���s�A���Ƃ݂邩
�I�[�f�B�I�̖��t���Ƃ��ċ������s���Ȃ��b�肾�B
�����I�[�f�B�I����JBLvs�^���m�C�Ƃ��������ɂȂ邪
�قƂ�ǂ̘^���X�^�W�I��JBL���E�F�X�g���C�N
���{�R�����r�A�������^���m�C���j�^�[�������B
�A���v�̉����̑g������
JBL�Ȃ�}�b�L���g�b�V���A�A���N�����A�T���X�C�Ƃ������ꂪ����
�^���m�C�Ȃ�N�H�[�h�A���b�N�X�}���A�㐙�������Ȃǂ��������B
�J�[�g���b�W�́A�V���A�[�ƃI���g�t�H�����v�������Ԃ��낤�B
�Ƃ��낪�A���̎�̍����I�[�f�B�I�̓W���Y�ƃN���V�b�N�̈��D�Ƃ̈ӌ���
JBL 4325�A�^���m�C SRM15�Ń��b�N�����Ƃ��̂͂��Ȃ�̃}�j�A��
�M�y�̃��R�[�h��^���]�����悤���̂Ȃ�j�̂ނ��낾�����B
���R�[�h�}�j�A�ɂƂ��ăI�[�f�B�I�}�j�A�͌y�̂̌��t�������̂��B
��������A���}�nNS-1000M�ɑ�\�����悤�ȍ��Y3way�X�s�[�J�[��
MOS-FET�̃v�����C���Œ����̂��j���[�~���[�W�b�N�̌��㐫�̂悤�Ɋ�����ꂽ�B
�������͏����̃o�u���E���W�J�Z���v�������ׂ�l�����邩������Ȃ��B
FM�����ƃJ�Z�b�g�e�[�v�̉����{���̃X�^���X��������Ȃ���
���W�I�ŗ����V���O���ՂƃA���o���E�o�[�V�����ł͉��ꊴ���Ⴄ���Ƃ��悭�������B
�X�e���I���u��LP�A���o�������u�������̂ŃA���o�������K�Ǝv����������
�ŋ߂�CD���C�V���[�Ŏ�����Ȃ��A���o���E�o�[�V�����ɋꌾ����l���K������B
�j���[�~���[�W�b�N�̏ꍇ�́A�A���o���P�ʂŕ]������邱�Ƃ������̂�
���������ꗂ����܂�N����Ȃ��Ǝv���̂���
���͍��Y�X�e���I�ł̌��̌��ɔ���ꂽ�A���o���̉����]���ł���B
�ǂ����K�v�ȏ�̃|�e���V�����������o�����Ƃ����ʂ��Ƃ����l�������̂��B
�l�I�ɂ�JBL 4325��4310�ł������蒮���ׂ����Ǝv����
���ꂳ��50�`15,000Hz�Ƃ���FM�����̑ш悵���o�Ȃ��̂�
���Y�X�s�[�J�[�ɕ������ƃX�[�p�[�c�C�[�^�[�𑫂��l�����Ȃ��Ȃ��B
�������������̊������������싷���ݏo�����̂����ł��邩�H
�ǂ�����o�����Ηǂ��̂��H�@�F�X�ƍl����̂ł���B
�j���[�~���[�W�b�N�̖��͂́A�V���K�[�\���O���C�^�[�̌��ƈ�̂�
���̈꒮���Ĕ���Ȃ̂���̐����قƂ�ǑS�Ă��ƌ����Ă����B
�������āA���̓����I�Ȑ��͂ǂ��ɂ��邩�Ƃ�����
���{��̏ꍇ��500�`2,000Hz�ɂ���ԍA���̋���������
�̎��ɍ��킹�����R�ȕ\��̑����I�m�ɖ炷�K�v������B
�t�Ɍ����A�̐��Ɣ��Ȃ��悤�ɒ���̊y��̖��x�������A�����W������
���̕ӂ��ʏ�̃I�[�f�B�I�̕������ł͖炵�ɂ��������ƂȂ��Ă���B
�܂蕁�ʂ̊�y�ł͍ł��[�����č��ݍ����Ă���͂��̑ш悪
�㉺�ɗ��U���Ă���̂ŁA�x�����Ȃ��Ȃ�̂��B
�����ƈ����̂��A���Y3way�̃X�R�[�J�[�̔�͂���
�{�[�J���悪�������ނ��ƂŁA���t�̒����f���𑝂������Œ�������
���F�h���V�����C���̃o�����X����邱�ƂɂȂ�B
�ނ��냉�W�J�Z��16cm�t�������W�̂ق�������̉������������Ƃ�����
�̎��̓��e���������蕷���Ȃ烉�W�J�Z�̂ق������͓I�������B
�j���[�~���[�W�b�N�������Ɛ^���ɒ��������Ƃ����j�[�Y�̗��ɂ�
�{�[�J���������ɏ[�������A�����������A�����W�𗧔h�ɋ�������
�Ƃ����A�������������t�����邱�ƂɂȂ�B
�ł����S�ɖ������Ƃ����ʂ��Ƃ��ȒP�ɂ�����߂Ȃ��łق����B
�������̃A�E�F�C�N�j���O�Ƃ��A�N�A�Ƃ������p�������Ă�Ƃ��̍������őu�₩�ȕ��͋C���Ǒ̌��ł���B
�܂����̍��͐Ԃ�V����������ǁB
�a���Ƃ����˂��Ă��܂����ˁB
1980�N��̃f�W�^���V���Z�͓o�ꂵ�����͐V�N����������
�A�i���O�ҏW�������̂ŁA�g���b�N�_�E�������e�[�v�������
�r�[�ɉ������������Ă��܂��Ė��͂��������Ă��܂��B
���̂��ߍ������A�������`�A�p���q���ȂǃC���X�g���S�̊y�Ȃ�
�i�������̓��}�X�^�[�ɐ������Ă���悤�Ɏv������̂́j
�����̎a�V��������͂������Č��������@��������Ă���悤�Ɋ�����B
���{�̊����y�ȂǃA�����J���獕�D�����ŋt�A������邭�炢����
�l�I�ɂ̓o�u�����O�̃C�P�Ă�l�����̃��C�t�X�^�C�������Ȃ̂�
���̕ӂ̌��������珉�߂Ă݂邱�Ƃ��Ǝv���B
�����ЂƂ́A���̌��J-POP�ŃA�����W��v���f���[�X����|���Ă�̂�
�������̂ق��Œm���Ă�l�̂ق���������������Ȃ��B
�x�X�g�e���Ƃ����ƓI���������k�ȃ��}�X�^�[�i���~�b�N�X�j�̗v���ɂȂ�
�d�͌������������܂łɂ́A�����ЂƉ����K�v�ȋC������B
�t��avex��URC�̃A���O���t�H�[�N�̉�����������Ƃ��͐����r�r������
�����Ɛ����Ƀ��}�X�^�[�����Ȃ��Ă���āA�����Ӗ��ŗ���ꂽ�����������B
���ꂪ�Ăѐ��ɂȂ��ăL���O�A�N���E���̔鋫���F�m���ꂽ�Ǝv���B
1980�N��̂����ЂƂ̌��ۂ�
J-POP�Ƃ����p�ꂻ�̂��̂V��FM�ǂ̑䓪��
���g���������ăR���v���b�T�[�����ʓI�Ɋ|����OPTIMOD�ɂ��
�f�̂܂܂�CD��������NHK���ڕ@�����悭���������B
�����炭�J�[�X�e�����Ȏd�l�ɂȂ����̂����̍����Ǝv���B
����NHK���A�i���O�@���L�x�ɔ�����a���̂悤�ɂȂ���
�R���B�Y���Ƃ���������Ă���c�Ƃ������ƂȂ̂���
�����̓��Ǝ҂ւ̈�����������������ł��������ȂƎv�����肷��B
������������g�U�^�̃X�s�[�J�[�̑�\�i��BOSE�Ђł���B
901�̓z�[���g�[���ƒ��ډ��̔䗦��8�F1�ƎZ�o�����f�U�C����������
�����̃c�C�[�^�[��������ς��Đݒu����301�Ȃǂ�
�J���I�P�X��X��BGM�̒�ԏ��i�Ƃ��Ȃ����B
��{�I�ɂ͒ቹ���h�b�V���\����ē��C�݃g�[������
�q�b�v�z�b�v��90�N��\�E���ł������낪�Ȃ��^�t�����������������B
���C�݃T�E���h�ŗL���Ȃ̂�AR�i�A�R�[�X�e�B�b�N�E���T�[�`�j��
�G�A�[�T�X�y���V���������̖����������悭���グ���邪
�w�ʂ̃A�b�e�l�[�^�[�̎w���ɁA�t���b�g�̉��Ƀm�[�}��������
���炩�ɍ���𗎂Ƃ��ق����D��ł������Ƃ�����B
AR-3�͂ǂ��炩�Ƃ����ƃN���V�b�N�����̗�����������������
1960�N���R&B�̉����߂ɂ悭�g��ꂽ���Ƃł��m����B

�����̘^���G���W�j�A�͕\�����ɂ�Altec 604E�Ń��j�^�[���Ă�����
�Ō�̉����߂̍ۂɃe�[�v���ƂɎ����ċA����
�I�[�f�B�I�}�j�A���D��Ŏg��AR-3��KLH�̃X�s�[�J�[�Ŏ������Ă����B
�Ⴆ���[�^�E���̃X�^�W�I���݂��
������Altec 604E�̃��m�����A���e��AR-3���u���Ă���B
����AR-3�̒u�������Ɠ��ŏ㉺�t���܂ł���B
���C�t���̕������邾�낤���AJBL 4310���S�����̂܂ܐ^���Ă���̂��B
���̂悤��1960�N��̃\�E���͓��C�݃T�E���h����ɂ��Ă���
BOSE�������悤�ȃ��[�c��������1990�N��ɔ��ꂽ�̂ł���B �Ƃ��낪���[�^�E���̘^���G���W�j�A������Bob Ohlsson��
1960�N��̃~�L�V���O�̑S�Ă����m�����ł���Ă����ƍ������Ă���B
���ڂ��C�����Ղ�ɓ����̂��Ƃ�b���̂���
������В����^����������@�ɂ����Ƃ�
�X�e���I�Ń~�L�V���O��������Ă���Ƃ������N�G�X�g��
�{�u���͂ǂ��ɂ��I���ł����ɂ������߁A�낤���N�r�ɂȂ肩�����Ƃ����̂��B
�X�e���I�Ȃ�āA���̉������E�ɕ����邾������H
�ƃf���A���E���m�����̐���ɂ��Ă͑f���C�Ȃ��R�����g�B
�A�����J�̃q�b�v�z�b�v�œ��{���̃��W�J�Z���d�ꂽ��
���ɒS���ŊX��舕����鋐��X�e���I���W�J�Z�ł͂Ȃ�
���m�����d�l��JVC RC-550���l�C�������B


���{�ł�3way�̃��m�������W�J�Z�Ȃ�ė��s��Ȃ�������
���傫�߂�10W�o�͂����܂��ă��b�v�̊Ȉ�PA�Ƃ��Ă����͂������B
3way�Ƃ����Ă�75Hz���炵���o�Ȃ�25cm�E�[�n�[�͑f�ʂ���
�X�R�[�J�[��2.5kHz�A�c�C�[�^�[��8kHz�̃��[�J�b�g�p�R���f���T�[������݂̂�
�Ɠd�̃��W�J�Z��AM-FM�R���p�`�̐v�����P����Ă���B
�ăr�N�^�[�Ƃ����A�A�����J�ł͓��C�݃T�E���h�̃G���A�ɓ��邪
���̕ӂ��q�b�v�z�b�v�̃T�E���h�X���ƃ_�u���Ă��邩�͊m���ł͂Ȃ��B ���Ȃ݂�BOSE 301�̃N���X�I�[�o�[��H���݂��
��̓d�����A�b�e�l�[�^�[���d����ł���ȊO��
�o�[�W�����ɂ���ĈႤ���̂̃c�C�[�^�[�̃R���f���T�[��3.7�`4.7�ʂe
8�����Z��4.2�`5.4kHz�t�߂ɂ���Ɨ\�z�����B
�܂�_�C���N�g/���t���N�e�B���O�̃_�C���N�g�����̂قƂ�ǂ�
�n�C�J�b�g�Ȃ���20cm�E�[�n�[�������Ă��邱�ƂɂȂ�B
��ʂ�2way�̃N���X�I�[�o�[��1.5�`2.5kHz�ł��邱�Ƃ��l�����
BOSE�̐v��Hi-Fi�����̃G�N�X�e���f�b�h�����W�{�c�C�[�^�[�Ɠ����ɂȂ�B
����͐�ɏq�ׂ��悤�Ƀ��W�J�Z�̉����v�ɂ����P���ꂽ���̂�
�{�[�J�������W����{�ɑS�̂𐮂��Ă��邱�Ƃ�����B
���̎�̃{�[�J�������W�܂őш���L�����E�[�n�[���G�N�X�e���f�b�h�����W��
������ł̕����U����������ꂸ�A�O�����ł����u�����v�̂悤�ȉ����o��B
���͂���̐ݒ肪�I�݂ȃ��j�b�g�Œ����{�[�J�����f���炵���̂��B
1980�N�㏉���ɐ���~�����X�s�[�J�[�e�X�g�����{������
���Y�X�s�[�J�[�̑����������̘c�݂�����A�N���V�b�N�ł͎S�s�Ƃ������̂��B
���̗��R�������Ă݂�ƈȉ��̂悤�ɂȂ�炵���B
�u�ʔ̓X�i��^�ƒ�d��X�A��ʔ̔��X�j�̓X���ɐςݏグ���X�s�[�J�[��
�@�����ɂ���l�B�̔����ȏ�́A�̗w�ȁA���́A�܂��̓j���[�~���[�W�b�N�́A
�@�܂���{�̉̂̈��D�Ƃ������Ƃ����B�����āA�X�s�[�J�[������ׂ�Ƃ��A
�@���̐l���������ɕ����ׂ�C���[�W�́A�����R���T�[�g��e���r��W�I�Œ�����ꂽ�A
�@���Ђ����̉̂���̐��ł���B�����ŁA�X���Ŗ炳�ꂽ�Ƃ��A�ł��邩����A
�@�e���r�̃X�s�[�J�[��ʂ��Ď��ɂ��݂��^�����g�̎肽���̐��̃C���[�W�ɋ߂�
�@���Â���������X�s�[�J�[���A�悭�����B�X�s�[�J�[����鑤�̂����胁�[�J�[��
�@�ӔC�҂��璼�ڕ������b������A���b�Ȃǂł͂Ȃ��B�v
���̃e���r�̉��ɂ���1967�N�ɒ����S�j�͈ȉ��̂悤�ɏq�ׂ��B
�u�ł̓��[�R�X�g�Ō����ɂ悭���������̉����o���ɂ͂ǂ���悢���A
�@����Ƃ��ăe���r�̉������グ�Ă݂܂��B�ƒ�p�̈����ȃA���T���u���^�d�~
�@����o�Ă��鐺���A�i�}�̐l�Ԃ̐��ƕ�����������l�͂܂����Ȃ��ł��傤�B
�@�{�\�{�\�Ƃ������Ԑ��Ƒ���͂��܂��Ă��邩��ł��B�Ƃ��낪�A�A���v�����ɂ���A
�@�X�s�[�J�[�ɂ���A�d�~����i����i�����̂͂��̃e���r�i���^�ŁA
�@���~�X�s�[�J�[1�{�̂��́j�̉����͈ӊO�Ɠ����ɋ߂��A�ƂȂ�̕����ŕ����Ă���ƁA
�@�i�}�̐��Ƃ܂������邱�Ƃ��悭����܂��B�v
1960�N�㖖��1980�N�㏉���ł͉̗w�Ȃ̕��͋C���啪�Ⴄ��
�l�Ԃ̐��Ƃ���������O�̂��Ƃ��A���͓�����O�łȂ��Ȃ��Ă���B
����_�́A1960�N�オ�܂������Ƃ̔�r�Ŏ��R����]�������̂ɑ�
1980�N��͊��S�ɓd�q���������ꂽ���y�̉���������Ă���_���B
�e���r�̉����̎^���������R�����ł�
�E�e���r�̉����̓}�C�N�̉������܂肢�����ĂȂ�
�E�A���v�A�X�s�[�J�[�Ƃ��ɒ��ƍ����~�����Ă��Ȃ�
�E�A���v��5�ɊǃV���O���ŃV�����V������
�E�e���r�p�ȉ~�X�s�[�J�[�̓}�O�l�b�g���傫��fo������������ł̎��ꂪ�悢
�E��ʂɂ��܂�{�����[�����グ���ɗp���Ă���
���X�𗘓_�Ƃ��ċ����Ă���B
�悤����ɁA�����̉Ɠd���i�Ȃ�̎d�l��
���������z������悤�ȁA�����낤�����낤�̑�\�ł͂Ȃ�
�ނ�����������ɍ��킹�ăo�����X�悭�g�ݍ��킳��Ă���
�Ƃ������ƂɂȂ�B
�����ōl����ׂ���
�W���[�N�{�b�N�X���e���r�����W�J�Z��
�ǂ�ǂ����Ȃ郂�m�����@��̃T�E���h�|���V�[��
�I�[�f�B�I�̐i���Ƃ͗����ɁA�������l�X�̂Ȃ��Ő��������Ă���
���̗��R�͐l�Ԃ̃R�~���j�P�[�V�����̊�{�ł���{�[�J�����
�������A�v���[�`���Ă������ʂł���ƍl������_�ł���B
���̊�{�I�ȃ}�C���h�i���j�̔������I�[�f�B�I�͑ޏꂷ�ׂ��ł���B
�{�[�J����i100�`8,000Hz�j�ŃI�[�f�B�I�����[��������Ƃ����̂�
���݂̋Z�p�ł͂قږY����Ă���B
�Ⴆ�Ήf��ق̉����K�iX�J�[�u�͂��̃X�^���X������Ă���
�����2�`10kHz��-3dB/oct�Ń��[���I�t�A10���g���ȏ��-6dB/oct�܂ōi��B
https://screenexcellence.com/downloads/AES_journal_article_JAES_V62_11_PG808.pdf
����͍L����Ԃł̎����I�ȉ����o�͂��w���Ă��邪
�~�j�V�A�^�[���嗬�̌��݂̓��{�ł͑z�������Ȃ��R���T�[�g��ꂾ�B


�����Ŗ��ɂȂ�̂��A�f�W�^���ŋώ��ɘ^�����ꂽ������
��x���̓����̃z�[���ɓ������܂�ėL���ƂȂ�Ƃ������Ԃł���B
�Ⴆ�A�X�s�[�J�[�̌v���͖������Ńc�C�[�^�[����ōs���邪
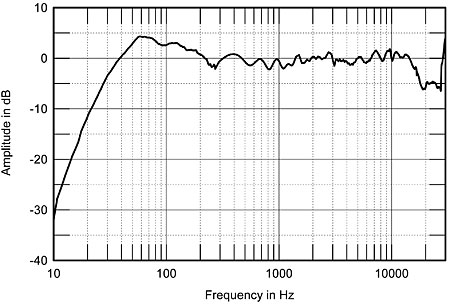
����𗣂���X�J�[�u�Ɠ��l�̓����ւƎ�������B
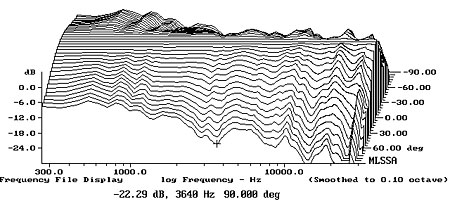
�t���b�g�ȓ�������ʂƂ����Ȃ��ł��A���[�t�@�C�������I�ȉ��������ƂȂ�B ���̃R���T�[�g�z�[���̎����I�ȉ���������F�߂Đ������Č������
1950�N��̃��J�r���[����21���I��J-POP�܂ň�т���������
�y���߂�悤�ɂȂ�B
�������ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂�
���g�������������Ă��Ă��A���Ԏ���ł������Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
���̎��Ԏ��ł̐��������^�C���h���C���Ƃ�����
�}���`�E�F�C�ŃX�e�b�v�������݂�ƃp�b�V�u�l�b�g���[�N�ňʑ����˂����B
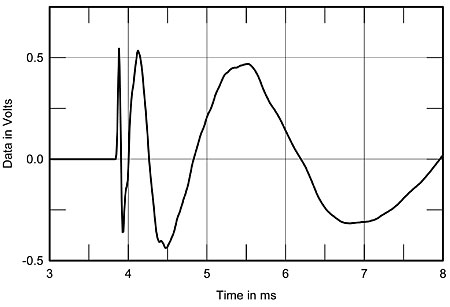
��L�̔g�`�́A�{���E��������̒����łȂ���Ȃ�Ȃ���
�l�b�g���[�N��H�ł̐l�H�I�Ȍ����ł��тꂪ������̂��B
���̂��Ƃ��A�ቹ�⍂���̃o�����X����ꂳ���錴���ƂȂ�B
���Ȃ݂Ɍ��݂̃X�e���I�^���ł͍����̃p���X�g�Œ�ʊ������߂Ă���
���Ԏ���0.5ms�x�ꂽ�g�`��-10dB�}�X�L���O����ĉ��ʍ���F������B

���̂��߁A���Ȃ萸�k�Ƀc�C�[�^�[�o�͂�����s����
���Ƃ͒x��Ď��������J�o�[���Ă���̂ł���B
�܂�X�e���I�ł̒�ʊ���T�E���h�X�e�[�W��
�����悻�y�Ȃ̉��t�Ƃ͊W�̂Ȃ��M������̂Ƃ��Ă���
�p���X�M�����ł��邾���N���A���s�q�ɏo�����ƂɎ��S���Ă���B
�t�Ƀ{�[�J���悪���낻���ɂȂ�A���̎h���̂Ȃ������t����x�ʂ�
�i�X�Ƌ����Ȃ��Ă���Ƃ�������B ���������p���X�g�̉e���́A20kHz��CD�K�i�ł�10kHz�̔{�����|����
�f�W�^���m�C�Y�̉e�����o��\��������
40kHz�܂Ŏ����Ă������Ƃ��ɁA�悤�₭���̈��E����B
���������������̃p���X�g�푈�̍��{�I�Ȗ���
�X�e���I�����ł̒�ʊ��̕\�o�Ɍ������Ȃ��Ƃ���
�Â���������Ɉˑ��������ʂȂ̂ł���B
�����Ŋy�Ȃ����m�����Ŋӏ܂��闝�R��
1.�y�Ȃ��p���X�g�Ɏx�z�����X�e���I�����̊č�����������
2.�p���X�g�̂Ȃ����ł������f���̂���I�[�f�B�I�@�\�����߂�
3.�{�[�J����ł̃t�B�W�J���ȉ^�����������y�̖{�����Ƌ��߂�
���̏ꍇ�́A���g�������͎�45���i�����ʒu�j�ňȉ��̂悤��
�z�[���g�[���ƃ}�b�`���O���Ă���B
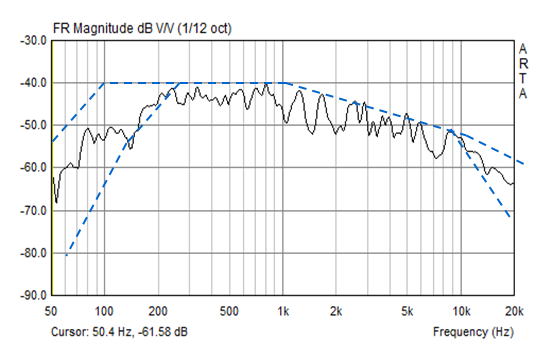
�f�W�^���m�C�Y�ɋN������p���X�g�͌Â��v�̃��C���g�����X�ŃJ�b�g���Ă���B
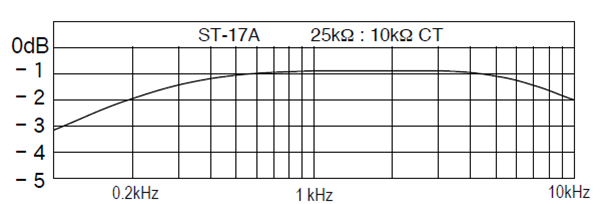
�X�e�b�v�����͋@�B�����̗D�ꂽ30cm�t�B�b�N�X�h�G�b�W��
�}���`�A���v�Ŗ炵�Ă��邽�ߋɂ߂đf�����B
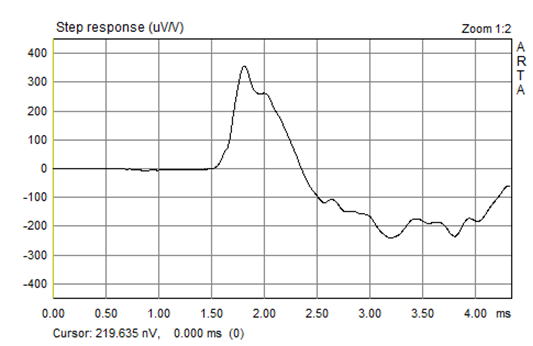
���ꂪ�f�W�^��DSP�����╡�G�ȃl�b�g���[�N��H�������
�f�̂܂܂̃X�s�[�J�[�̓����Ŏ������Ă���_�������ł���B
�X�e�b�v�����̋ώ����́A�����̓X�e���I�̒�ʊ��ɉe������Ƃ��ꂽ��
���m���������ł��{�[�J���̋����A�A���A�q�����ꑧ�ŕ\������̂ɕK�v��
�y��̉��߂Ȃǃp�[�X�y�N�e�B�u��I�m�ɏo�������ł��L���ł���B ���m�����ʼn��y�ӏ܂��闝�R�F
1.�p���X�g�Ɏx�z�����X�e���I�����̊č�����y�Ȃ��������
2.�p���X�g�̂Ȃ����ł������f���̂���I�[�f�B�I�@�\�����߂�
3.�{�[�J����ł̃t�B�W�J���ȉ^�����������y�̖{�����Ƌ��߂�
�܂��p���X�g�����y�̕]�����珜�O���邽�߂�
�E�ш���{�[�J����ɍi��Â��v�̃��C���g�����X���g�p
�p���X�g�̂Ȃ���Ԃł̃I�[�f�B�I�@�\�̏[�����邽�߂�
�E�X�s�[�J�[�̃^�C���R�q�����g�����𐳋K�̎p�ɖ߂�
�Ƃ������Ƃ�������
�����̎��ɂ���
�{�[�J����ł̃t�B�W�J���ȉ^�����������y�̖{�����Ƌ��߂邽�߂�
��������Ηǂ��̂��낤���H
����̓X�e���I���ʂŗ��������������Z�b�g��
�}�C�N�Ŏ��^���ꂽ�����̂��̂ɃN���[�Y���邱�Ƃł���B
�X�e���I�E�~�b�N�X�ɂ���ĉ����������Ƃ�
1960�N��ł́A���E�ʁX�̐M�������^�����f���I�E���m����
1970�N��ł́A���o�[�u���������߂����F���V�j�^�X�y�[�X�G�C�W�E�T�E���h
1980�N��ł́A�T�E���h�X�e�[�W��z�肵�������̃~�j�`���A�z�u
1990�N��ł́A5.1�����T���E���h�ł̃G���^���^VR�T�E���h
�ȂǂȂ�
�X�e���I�Ȃ�ł͂̉������ʂ����X�Ɣ������Ă�����
���ۂ͂ǂ���l�Ԃ̒��o�̍��o�����ɍ��o�����U���ł���B
�X�e���I�Ői�W�����̂́A�����Ƃ��ẴX�e���I�@�ނ�O��ɂ����w���헪�ł�����
�~���[�W�V�����̃p�t�H�[�}���X�E�A�[�g�̎��̌���Ƃ͕ʕ��ł���B
�I�[�f�B�I�@��̓p�t�H�[�}���X�E�A�[�g�̎����ӏ܂��邽�߂ɐ��m�łȂ���Ȃ�Ȃ��B
�U���̃X�e���I���ʂɖ|�M���ꂸ�Ƀ~���[�W�V�����̉��t�����\���悤�B
�Đ��ш���{�[�J����ɍi��A�^�C���R�q�����g�����𐮂������m�������u��
�����Ƃ����ʂ��グ��̂̓��C�u�^���ł���B
�ӊO�Ɏv���邩������Ȃ����A���C�u�����R���T�[�g���̉��ꊴ�ɐZ�肽��
�����v���ă��C�u�Ղ��w������l���������Ǝv���B
�������A���C�u�Ŕ�������X�e�[�W��ł̃p�t�H�[�}���X��
���m�����Ő����Ă݂�ƁA���߂Đ����̂��B
��l��l�̕\���̃X�P�[�������{�ɂ��c�ꂠ����B
��ʂɂ́A���C�u�^���̃f�����b�g�͎��^�}�C�N�̐��̏��Ȃ�
���ӂ̃m�C�Y�i�ϏO�݂̂łȂ��A�d���̃n�����A�n�E�����O�A�ߓ��͘c�݂ȂǂȂǁj������
�C���Ղł̃R�s�[�e�[�v�̗��G�Ȏ�舵����������Ă����B
����1960�N��̉����~�L�T�[���璼�o���̃e�[�v�ɂ�
PA�Ƃ��ēƗ����Ă����M�^�[�A���v�̉����܂܂�Ă��Ȃ����Ƃ����X����
�����ƃ��C�u���^�p�Ƀ}�C�N���[�Ă����̂�1960�N��ł��㔼�����
�E�b�h�X�g�b�N�̂悤�Ȃ��Ղ葛���Ƃ��Ēm���邱�ƂɂȂ�B
����炪�R���T�[�g�Ȃ�ł͂̉��ꊴ���킮�Ɣᔻ����Ă�����
���͈�l��1�{�ߐڂ̃}�C�N�A�X�e�[�W��ł̉��̔��Ȃǂ�
�X�e�[�W�p�t�H�[�}���X���ӏ܂��邤���ŋt�̌��͂�����B
21���I�ɂȂ��ē��̖ڂ��������C�u�ՂŌl�I�ɍD���Ȃ̂́c
�W�F�[���Y�E�u���E��1968�N�_���X�E���C�u
�@1960�N��̃G���^���^�X�e�[�W�̍ō���ŁA�_�u���E�x�[�X���_�u���E�h������
�@�S������m��Ȃ��t�B�W�J���ȈЗ͂������Ă���B
�@���炭���J����Ȃ������̂́A���̌�̃o���h�����o�[���ٖ�肪�������������B
���F�����F�b�g�E�A���_�[�O���E���h1969�N�}�b�N�X�E���C�u
�@�}�X���f�B�A���犱����Đ����ɕ��Q�̃h�T���胉�C�u�𑱂��Ă������̋L�^��
�@�ꖖ�̃��C�u�n�E�X�͂قږ��ϋq�A�V�X�^�[�E���C��38�����ڃv���C�̖v���Ԃ肪�����B
�@�̂��烍�o�[�g�E�N���C���̉��J�Z�b�g�e�[�v�Œm���Ă��������X�̐��K�Ղł���B
�W���f�B�[�E�V��1972-73�NBBC���C�u
�@1996�N�Ɍ��J���ꂽ�����Ǔ��ł̃��C�u���t�����A�s�A�m���M�^�[�e������
�@�Ɠ��̉̂����O�b�ƃN���[�Y�A�b�v����Ăǂ�ǂ��������B
�@���e���������s�[�X�̓������S�X�y�����������Ƃ�����A���ړx���Ⴉ�����o�܂����邪
�@���ƂȂ��Ă͍��̖�����ǂ����߂�����҂ɚg�����悤�B
�����������C�u�Ղ̑����́A�����ȃX�e���I�Œ�����
�R���T�[�g���Œ��������Ƃ͓��Ĕ�Ȃ�
�S�c�S�c���Đ�\�肵���悤�Ȉ�ۂɂȂ�B
����̓}�C�N�̐����̓˔����̂���o��������Ȃ������
���̑召�A�v���[���X�ȂǂŊy��ԂɃq�G�����L�[���ʉ���
�X�e���I�̉��z�T�E���h�X�e�[�W�ɓ��Ă͂܂炸
�}�ɓˏo�������������ƈʒu��������邩�炾�B
���邢�͐�\�肵�����o�́A�s�b�N�A�b�v�}�C�N�̉��ʍ���
���������ʂ̃}�C�N�̏ꍇ�͔����z���C�g�m�C�Y���|������
���̃A�R�[�X�e�B�b�N���畂���������ɂȂ�B
���͂����������Ƃ͌��_�Ƃ͎v���Ă��Ȃ��B
�Ƃ����̂��A�Ⴆ�R�[�������X�|���X�̊|��������
�{�[�J����[�h�M�^�[���o���h�S�̂����[�h���Ă�����
�h�����ƃx�[�X���K�b�V���g��ŃO���[�u�����������銴�o�Ȃ�
���R�Ȃ������Ŗ������������Ē���邩�炾�B
���ߊ����ʊ����o���I�ȐM���i�G�R�[�ƃp���X�j��
���y�̑N�x���x�z�����ẮA���C�u���͋t�Ɏ�����B
����BOSE���m���G�R�[�F���ډ���8�F1�ƒ�߂��悤��
�N���V�b�N�̃V���t�H�j�[�E�R���T�[�g���̓z�[���̋������d�v�ł���B
�t�ɃW���Y�́A�o�[��N���u�Œ����悤�Ȗ��ڂȊ������D�܂��B
����̓N���V�b�N�ł������y��s�A�m�Ȃǂł悭�������B
�ł̓u���[�X��b�N�͂ǂ����H
1970�N��ȍ~�ɑ傫�ȉ��œ�������������������
����ȃR���T�[�g���ɂǂ�ǂ�i�o���Ă�������
���̉��y�̍\���́A���X�܂ł̋K�͂ł���B
�ٖ��ȃo���h�̈�̊��̂Ȃ����b�N�͂����̉����B
�X�e���I�����ʼn�����ԏd�v���ƌ�����z�[���̗Տꊴ�B
�ł͉��y�ŏd�v�Ȃ̂́H�@�X�e���I���O��ł͂Ȃ��̂��B
�X�e���I�^���ŏd�v�ȗՏꊴ��
���ߊ����ʊ����o���G�R�[�ƃp���X�ŃR���g���[�����邪
����͊y���Ƃ͈Ⴄ�I�ȐM���ł���B
�����ĂقƂ�ǂ̓c�C�[�^�[��8kHz�ȏ�ŃR���g���[����
�y���̑O����ʂ�B�A���r�G���g�����Ƃ�������̈悾�B
���́A�y�����A���r�G���g�����ŃX�e���I�����ɑg�ݍ��܂���
���ɏ����������o�͂Ɏx�z���ꂽ���Ƃ��ĔF�������B
���̂��Ƃ��y���̃_�C�i�~�b�N���킢�ł��܂��̂��B
�t�ɁA�t��������p���X�������������X�e���I�@��͔ߎS�ł���B
�Ƃ����̂́A�c�C�[�^�[�̏o�͂Őh�����ĕۂ��Ă������̑N�x��
�g�`���ׂ�ă��S���S�����E�[�n�[�ł������f�ł��Ȃ��Ȃ邩��ł���B
https://www.stereophile.com/content/measuring-loudspeakers-part-two-page-3
���ɃX�e���I�Œ����Ă���̂́ABOSE���m�̌����Ƃ���Տꊴ��9���ł���
�~���[�W�V�����̃p�t�H�[�}���X�̓c�C�[�^�[�̍єz�Ɏx�z�����̂��B
���̍����n���X�����g����E�ނ���̂����m���������̕��j�ɂȂ�B �t�ɉ��ꊴ�̂Ȃ��|�b�v�X�̘^����1960�N��܂Ń��W���[�������B
���{����1970�N�㖖�܂ł̃V���O���Ղ̃~�b�N�X�܂ň������邪
��������݂̃X�e���I�@��ōĐ������Ƃ���W�������ł���B
�悭���W�I�I�Ƃ�������^���X�^�C������
�X�^�W�I�ł̐����t�̉��ړd�g�ɂ̂��Ă�������̖��c�ł�����B
�ɒ[�ȃp���X�����͕������̂ɂȂ���̂ō킪��Ă��邵
�ߏ�ȋt�������������s���ĂɂȂ�̂ŗ}�����Ă���B
���ꂾ���݂�ƁA���m���������͌Â��^���̂��߂ɂ���悤�ɂ݂��邪
���ۂɂ͌��݂̃|�b�v�X�ɂ����Ă��{���͂���قǕς��Ȃ����Ƃ�
�ŋ߂�J-POP�����m�����~�b�N�X���Ă݂�ƃn�b�L������B
J-POP�Ƃ����ƁA�ꎞ�����s�����悤�ɑł����ݒ��S���Ǝv����������
���ꂾ���ɐ��h�����A���x�[�X����������Ƃ��̃t�B�W�J���ȋ��x���͕������B
�l�I�ɍD���Ȃ̂́A�h���X�R�[�Y�u���}�v�A�g�V�Ñ�q�u�������b�v�Ȃ�
�Ȃ̂���{�[�J���Ɖ̎��̖��͂Œ�������^�C�v�̊y�Ȃł���
���m�����ɂ���ƃh�������x�[�X���{�[�J���Ɠ������O�ʂɏo��
1960�N��̃��b�N��t�@���N�ȂǂƂقƂ�Ǒ��F�Ȃ������͂��B
���Ȃ݂Ɏ��̏ꍇ�A�X�e���I�����̃��m�����~�b�N�X��
�~�L�T�[�ō�����݂��Ⴂ�ɂ��ċt�����������킷���@�ŗ��������Ă���B
���̏ꍇ�A�p���͒����̃��m�����̂܂܂ł���B

�̂̋^���X�e���I�̋t�����������ł���
�u�t�^���X�e���I���������v�Ƃł����t���Ă������B
�悭�s���鍶�E��Z��������@����
�t���������������ăo�����X���ς��B
�]���͂��Ȃ肱��Ń��m�����������������ꂽ�B J-POP�̂����ЂƂ̓����́A���O�ł̃w�b�h�z��������z�肵��
�������グ�đS�̂ɉ��ʂׂ̒ꂽ�~�b�N�X�ɂȂ肪���ȂƂ��낾�B
�D���ȃA���o���ł����ƁA�A�[�o���M�����h�u�K�C�K�[�J�E���^�[�J���`���[�v
�A���v���W�F�N�g�u�ߏ��K�N�}�Ӂv�Ȃǂ�����B
���������^���̏ꍇ�́A�����̕���\�Ȃ�ď����͖��ʂ�
�ቹ���玞�n��ł̕���\���K�{�ł���B
���n��ł̕���\�́A�X�e�b�v�����̃X�����_�[�����ƌl�I�Ɏv���Ă���
�܂�ቹ�̈����ۂ�1ms�ȓ��Ɏ��߂邱�Ƃ��]�܂����B
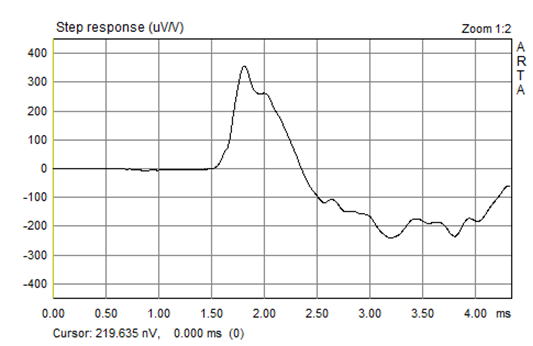
��ʂ̃X�s�[�J�[�͈ȉ��̂悤�ɃE�[�n�[�͒x��ቹ���_�u���B
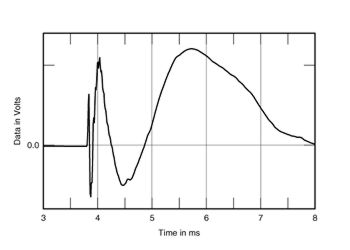
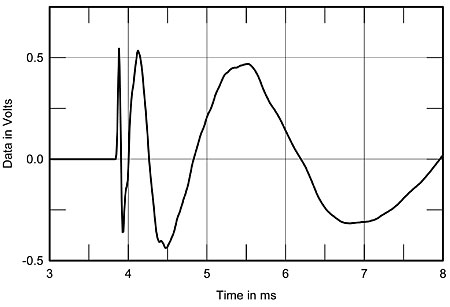
�ނ���E�[�n�[���x��ďo�邱�ƂŁA�c�C�[�^�[�Ƃ̔���������Ă���̂���
���F�̕���\�͊m�ۂł��Ă��A���Ԏ��ł̕���\���ቺ����̂��B �I�[�f�B�I�}�j�A�̊Ԃł͂��܂�b��ɂȂ肻���ɂȂ���
���{�̃|�b�v�J���`���[�̑��l���͐��E�ł�����̑��݂�
���ʂɕ��U�������ď��ƓI�ɂ͏��K�͂ɂȂ�₷�����_�����邪
���̍��ł̓C���f�B�[�Y�ł���Ă���e�����X�Ɖ����тő��݂��Ă���B
�R���Z�v�g�A���o���̎�̍��݂悤��
1970�N��̃N�B�[����P�C�g�E�u�b�V���Ƃقڑ��F�Ȃ���
�l�I�ɂ͎v���Ă���B
���������X����21���I�ɓ����Č����ɂȂ����悤�ȋC�����邪
�ʂɐV�����o�����ł͂Ȃ��A1970�N�O��̃A���O���V�[����
�u�I�����N�v��u�����̖��R�i��܂�j�v�������
�R���Z�v�g�A���o���̔��z�͏�Ɏߏ���s���Ă����B
����������A�̃R���Z�v�g�A���o�������m�����Œ�����
���y�ŕ\�����ꂽ���w��
���{���͉��y��@�Ŏ�ɗ]�����̂̍\����
�X�b�L���Ɨ����オ���Ă���̂��B
100�`8,000Hz�̃{�[�J������A�L�����[�g�ɏ[�����������m�����V�X�e����
�~���[�W�V�����̃t�B�W�J���ȋ��x���Ɖ��y�ŕ\�����ꂽ���ꐫ�̗�����
���ʂ��Ȃ���ꌳ�����čĐ�����B
�t�ɃX�e���I���u�̃A�L�����[�g�Ƃ�
�p���X�g�̒�ʊ��ƃA���r�G���g�����̉��ꊴ�̍Đ��ɕ��U����
�����I�ȏ�̐ݒ�ɃG�l���M�[���₵�Ă���B
����̓R���T�[�g�z�[�������y�̓a���ƌ�����悤��
�Љ�I�ȃq�G�����L�[�̐��A�ł�����
�~���[�W�V�����̐l�Ԑ��Ɋ�Â����y�̍Đ��ł͂Ȃ��B
�Â��u���[�X�̘^������
���t�̓N���A�ȉ��̊y���g�ݍ��킹���V���v���ȃA�����W�Ȃ̂�
��Ԙc��ł���̂��V���K�[�̃_�~���������肷��B
���̃_�~���̌͂ꂽ�j�����ɂ�������l�����Ԃ̂�����
�u���[�X�̔߈��Ƃ͐����͂Ɋ�Â��̂��B
����ɒނ��ăM�^�[�̉����c��ł����B
�h����������������藧�Ă�B
���J�r���[�̐��܂ꂽ�w�i�ɂ�
�v�t���̖ウ�����炯�o���̂ɂ܂���������w�i������B
�悭���m�����V�X�e���̒����ɃW���Y�E�A���o�����w���l�������B
���Ƃ��ƃ��m�����̗p�r���A1950�N��̃��_���W���Y�Ɏ��ʂ��邩��ł����邪
����ɏ����W���Y�E�{�[�J���̃A���o���������̃��t�@�����X�Ɏg���ꍇ�������B
�����ăE�B�Y�E�X�g�����O�X�̃A���o���͎g��Ȃ����낤�B
�Ƃ��낪���ۂ̃A���o���̔���s���͋t��
�����̂������ڂ̉ƒ�p���m�����@��̑�����
�E�B�Y�E�X�g�����O�X�̂悤�ȃ��[�h���y�������ɃG���[�V���i���ɍĐ����邩
���̈�_�ɍi���Ă����悤�Ɏv����B
�Ƃ����̂��w������x�T�w�̍D�݂������ɂ��������炾�B


���ɉ��Ăł̉Ƌ�̑I�����͏����ɂ��邱�Ƃ��傫���Ǝv���B ���_���W���Y��LP�Ղő�ʂɎc���ꂽ�w�i�ɂ�
���ڂ̃v���C�����^�ł���Ƃ������_�ɂ܂���
���ꂪ�N���V�b�N�ɕC�G����A�[�g���ƔF������Ă������炾�B
�ł̓u���[�X��J�r���[�͂ǂ����Ƃ�����
�e�B�[���Y�����L�ł���I�[�f�B�I�@���
���X �g�у��W�I����ヌ�R�[�h�v���[���[�ł���
���������m�����Đ��̌��̌��Ƃ��ČŒ�T�O�����ꂽ�Ǝv����B
���Ȃ݂Ƀ~�b�h�Z���`�����[�̐����������̍L���ɂ�
�e�B�[���Y��������ꏊ�ʼn��y���y���ގp���`����Ă���B

�ނ��뉹�y�Ɠ��l�ɃW���[�X���y����łق����Ƃ�����]���݂��Ă���B
�ʐ^�ł݂�I�[�f�B�I�@��̃V�`���G�[�V������
��������p�[�\�i����������̏�܂�
���ꂼ��ɍ����������K�͂Ŏg���������Ă����B

���m���������͂ǂ̃V�`���G�[�V�����ł����藧���Ƃ�����B ��̍L����ʐ^�ł݂Ĕ���悤��
�l�ŏ��L�ł��������@�킪�g�у��W�I����v���[���[�Ȃ̂ɑ�
�����̏�ł̓W���[�N�{�b�N�X���傫�Ȗ�����S���Ă������Ƃ�����B


�t�ɂ����A�l�ő傰���ȉ����@��Ń��J�r���[���l�͂Ȃ�
����p�̍����I�[�f�B�I�͐������̔�������Ă��Ȃ������B
�������|�b�v�X�̗��j�̂Ȃ��ő傫�ȃ~�b�V���O�����N�ɂȂ��Ă���̂���
���̐���ł̓f�B�X�R�������ݔ��ƂȂ��Ĉ����p�����B
���Ȃ݂ɃW���[�N�{�b�N�X�̃W���[�N��
���l�������_���X��V���̂��߂ɏW�܂鏬���̂��Ƃ�
��≺��Ōy�̂����Ӗ����܂܂�Ă����B

�Ƃ͂����A���E����ɃA�����J�����̐l�퍷�ʂ������ɂ܂�
���������F���ɊJ���I�ȏꏊ�𔒐l���������ꂽ�Ƃ����悤�B �������m�����V�X�e���ŏd������̂�
���̃W���[�N�{�b�N�X�����t�B�W�J���ȍĐ��\�͂ł���B
�܂�h�[�i�b�c�Ղ���z�����錴�̌��̌g�у��W�I�����v���[���[����
����傫�����邾���ŁA���J�r���[�̃G���[�V�������O�b�Ƒ����Ă���̂��B
���Ȃ݂ɃW���[�N�{�b�N�X�̎d�l��
30cm�G�N�X�e���f�b�h�����W�Ƀc�C�[�^�[��lj���
6L6��������EL34�̃v�b�V���v���A���v�ŋ쓮������̂�
�J�[�g���b�W���G���{�C�̃Z���~�b�N�^��GE�o���������g���Ă����B
https://www.jukebox-world.de/Forum/Archiv/Rock-Ola/R.O.1455.htm

�W���[�N�{�b�N�X�̉��i�́A�O�ς̑����ƃ��R�[�h�`�F���W���[���قƂ�ǂ�
�����p�[�c�͏��Օi�Ƃ��Ĉ����Ȃ��̂��I���X�����������B �����@��Ƃ��ẴW���[�N�{�b�N�X�̎d�l��
�g�[�L�[�⍂���I�[�f�B�I�@��ɔ�ׂ��Ȃ����Ă���B
����������̓|�b�v�X�̍Đ��ɕK�{�̃G���[�V���������˔����Ă���
�ڎw���ׂ����_�������Ă���B

�W���Y�ŕ]������Ɖ������������Ă��c�܂Ȃ����Ƃ���O��ɂȂ�̂�
�t�@�~���[�����̃��b�`�ȉ���1950�N���JBL��A���e�b�N�Ȃǂ�
�A�����J���E�r���e�[�W�̋@��ōō��x�ɖʔ�������������
�p���[�n���h�����O�ւ̑Ή��͂����������B
���������ӋC����̃e�B�[���Y�����̍r�������T�E���h�͏����ѐF������Ȃ��B
���J�r���[�̘^���͏o��������J�b�e�B���O���x���̋Ɍ���_���čU�߂Ă���
���̎��ɃV���E�g�ȂNJ��܂��Ƙc�݂ŃU���b�ƂȂ�B
���̍r�����S�n�悭�������邩���V�X�e���\�z�̌��ƂȂ�B
���̘c����A���������čK���Ȍ��ѕt���������̂��グ�邾���łȂ�
�O�����݂��߂ė܂𗬂��Ȃ���{���ŃW�F���V�[�����
�p���v�}�K�W���Ƃ��d�Ȃ��Ă���悤�Ɏv����̂��B
�ȉ��̃g�[�L�[�ƃp���v�}�K�W���̃��u�X�g�[���[�̈Ⴂ��
�ڎw���ׂ��I�[�f�B�I���̈Ⴂ��Y�قɌ���Ă���B

�����g��NOT NOW���[�x������o����
�uThe Cruisin' Story 1955-1960�v�Ƃ����R���s�A���o�����D����
�{�[�J���悾���ŃG���[�V���i���ɖ炷�錍���l�܂��Ă���
�����I�Ƀ��m�����V�X�e���̒����̃��t�@�����X�ƂȂ��Ă���B �����̐l�̓X�e���I�^���A����1970�N��ȍ~�̘^����
�|�b�v�X�̉�����]�����A�I�[�f�B�I���𐮂���̂�
�I�[���f�B�[�Y�ƕ������[�c���b�N�̎Q�l�����̂悤�ɂ݂Ȃ��X��������B
�������A���J�r���[�̍Đ��������W���[�N�{�b�N�X�ɂ܂ň����グ���
�V���v���Ȋy�Ȃ̃A�����W�ł��G���[�V���i���ɕ�������p������
����܂ł̌y���y�Ƃ����Ăѕ��Ƃ͋t�́A�h���h���Əd������������オ��B
���������l�ԓ��L�̊���́A�����̂��ς��Ȃ��̂ł��邪
�I�[�f�B�I���Ƃ��ĉ���D�悷�ׂ����́A�����Ō��߂�ׂ����ł���
�I�[�f�B�I�@��̐��\�ɔ����ĉ����тƂ����͖̂{�ӂł͂Ȃ��B
�X�e���I�����̃X�e���I�^�C�v�i�Œ�T�O�j�����y��ǂ�������������̂��B
���Ȃ݂ɃA�����J���E�T�E���h�Ƃ�����
JBL��A���e�b�N�Ƃ��������C�n�̔h��ȃT�E���h���v�������ׂ邪
�{����UREI�̘^���@�ނ̂悤�ɒ��悪�Z���ŃX���[�L�[�ȃT�E���h�ł���B
������WE�n��̃g�[�L�[�ł͂Ȃ��ARCA�n��̕����ǂ̂��̂�
���{�ł͕��i����Z�p��������Ă����̂ŁA���܂�V�N���̂Ȃ��]���ƂȂ�B
�I�[�f�B�I�̑�햡�Ƃ����ƁA�A�����J���ƃ��[���s�A���ɑ�ʂ���闝�R��
���̓�����O�̉��͉Ɠd���i�Ƃ��ĒN������Ɏ�ꂽ����ł�����B
�����������̓�����O�����[�����������Ǝv���Ƃ���햡�̈Ӗ��͑S���قȂ�B
�h���}�Ƃ����l�Ԃ̊����ɑi����@�\���t�B�W�J����Ȗʂ���b�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
���̏�l�Ԃ̌���ł���{�[�J����ɏW�����Ă���̂��B
����o�łŖ{�o������H
���͔�����
�f���ɂ��肪�Ƃ��A�ƌ����ׂ��Ƃ���Ȃ��낤����
�|�b�v�X�����̑��̍��I�[�f�B�I�Ƃ͌����Ȃ���
�m���ג��҂��ŏ��̘m�̎����ɂ��Č���Ă��ςȂB
�ł��V�����|�b�v�X�̒a���ɐS�Ƃ��߂�������������������Ƃ��܂�
Jensen��PA�p�X�s�[�J�[�Ƃ��T���X�C�̃��W�I�p�g�����X�Ƃ�
���݂̎g�����Ɣ����āA����̉��l���������Ă�̂�
���݂̃I�[�f�B�I���_�̉ۑ���L���Ȃ�������Ȃ��͎̂��Ɏ����䂢�B
���Ƀ��W�I���������S�̃~�b�h�Z���`�����[���̃I�[�f�B�I��
�܂������ăm�C�Y�Ƃ̓����������̂ŁA�����͓�̎��Ǝv���₷���B

AM�K�i�̂Ȃ��ɉ��������y�J�ɉ����ق�����
�ӊO�ɐl�ԍH�w�I�ɍœK�ȃX�y�b�N�ł��邱�ƂɋC�t�������B
�̂�100�`8,000Hz�̃��m�����ʼn䖝���Ă����̂ł͂Ȃ�
���̃X�y�b�N�ł��\���ɖ����ł����̂��B �u���O���ʂɖʔ������ǃX�}�z���Ƃ�����Ɠǂݓ���
�u���O��Z�߂Ă���������ƃm�E�n�E���l�ߍ���ł��ꂽ��2000�~���炢�܂ł������甃��
����A�ʔ�������Ő�����Ȃ�3000�~�ł����͔���
�l�ԍH�w�I�ɍœK�ȃX�y�b�N�Ƃ����̂�
���̃~�b�h�Z���`�����[�̍H�Ɛ��i�ɓ����I�Ȃ��Ƃ�
�k���̉Ƌ�Ȃǂ͌��݂ł�����S�n���ō��ł���B
����������͖̌p������y�[�p�[�R�[�h�Ȃ�
�����Ɠ������@�������ƌp������Ă̂��Ƃł���B
�d�����i�͏��Օi�̗������A�������i���Ȃ��Ȃ�
��v�ȃv���p�@�ވȊO�͖ڂɂ���@����Ȃ��B
���̂��߃}�b�`���ȃ^�t�K�C�������A�����J���Ɗ��Ⴂ����₷���B
�������W�F���Z����T���X�C�g�����X�͐����Ȃ����s�i��
������D�ꂽ���\�̕��i���F�X�Ƒ����Ă��Ȃ���
���ꂪ�Ȃ������I�ȏ�������ő��葱�����Ă��邩
�����I�Ȏ���Ō������K�v������Ǝv���B
�����ɐl�Ԃ̐���d�C�Ŋg������m�E�n�E���l�܂��Ă��邩�炾�B
>>148
�z�[���y�[�W���͂��߂�20�N�o���t�H�[�}�b�g���Â��̂�
�X�}�z�p�ɓǂݐ�₷�����̂��������Ă݂܂��B >>151
���[�I�����l�ł��I
���������Ղ��Ȃ��Ă�I
�ǂ��Ǝv���܂��I
����Ń��m�����[��������Ɨǂ��ł��ˁI ������̃x�X�N�����ǎ��C�O�^���𗬂��Ă��邵�A�C�ɓ����Ă���B
���m�����Œ����Ă͂�����Ƃ���̂́A���̔��G��̂悤�Ȃ��̂��Ǝv���B
�܂�}�C�N�Ř^���������A���₩�Ȃ̂��A�t�ɃU���U�����Ă���̂�
�����������������ۂ���Ă���B
�t�ɃX�e���I�Œ����Ƃ��́A����̎����Ɏx�z����₷���̂�
���C�g�̓��ċ�ʼn����e���R���g���[���ł���B
�ꌩ����ƌ��h���悭�ł������ŁA�f�ނ̗ǂ����ᖡ���邱�Ƃ�����Ȃ��B
JENSEN C12R�ŋ����Ē������T�C�Y�̔�����낤�Ǝv���Ă܂������c�C�[�^�������ƕs���ɂȂ����̂ŁA����ς�I�X�X����Visaton FR6.5�ō�邱�Ƃɂ��܂��B���T�C�Y�͓����ł��X�����ł��傤���H
�c�C�[�^�[�͊���������̂ł���
���݂̓t�H�X�e�N�X FT28D�Ɏ��܂��Ă��܂��B
�t�H�X�e�N�X�͍ŏ� �ʔ������Ȃ������̂ł���
�������ƕȂ��قƂ�ǂȂ��I�[���}�C�e�B�ł��B
Visaton FR6.5�̃��{���c�C�[�^�[��
PA�ł��g�p�ł���p���[�������˔����Ă��܂���
�����̐M���̔����œ����x���̋t���̃p���X�g���o��
4kHz�t�߂̃����M���O�����킹�āA�ǂ������������ƂȂ�܂��B
�^�C���R�q�����g�����܂ŋC�ɂ��Ȃ��Ǝv���܂���
�c�C�[�^�[�̈ʒu�͔���ʂœ�������悤�ɂ����ق���
�N���X�I�[�o�[�t�߂̈ʑ��̒�����������
�D�܂������������܂��B
���Ǝ����Ă��Ȃ��c�C�[�^�[��
Visaton TW6NG-8�Ƃ����R�[���c�C�[�^�[��
�\�����炵�ăh�C�c�� �^��ǃ��W�I�̏C�����i�Ƃ���
�������Ă���\���������ł��B
1960�N��̕��͋C���D���Ȑl�ɂ͂����߂ł��B
���߂�Ȃ����BVisaton�� Fountek�����Ⴆ�Ă܂����B
��ʉ���^�̍Œዤ�U���g����
foc=4250/(B+D*2)*2
B�F���AD�F���s���i�P��cm�j
�Ōv�Z����܂��B
���{2�~���s����100cm����foc��85Hz�ƂȂ�܂��B
�{�[�J�����S�ł���R�[�����̃o�^����}���邽�߂�
foc��120Hz���炢�܂ōi���Ă��悳�����ł��B
���̏ꍇ�A��43cm�ʼn��s��14cm�ƂȂ�܂��B
Visaton FR6.5�i���a14.3cm�j�̏ꍇ��
��������594Hz����A�N�e�B�u�ɂȂ�̂�
100~600Hz�����̔���
600~1200Hz���R�[�����̐U��
1.2~10kHz���T�u�R�[���̋��U
�Ƃ������|����3way�̃L�����N�^�[�ō\������܂��B
���ቹ�̖c����
���j�b�g�ƃo�b�t���̌��ԂŒ����ł��܂��B
�T�u�R�[���Ƃ̃o�����X�Ō��߂܂��傤�B
�T�u�R�[�������邳���ꍇ�́A�߉����璮���Ă��������B
600~1200Hz���W���b�ƐZ�ݍ��ނ悤��
��������ʒu���x�X�g�ł��B
���Ȃ݂ɐV�i�̃��j�b�g�͌Œ�l�W���ؔ��ɓ���ނ܂ł�
�Ƃ�ł��Ȃ��J�[�J�[�������Ŗ�܂��B
�C���������ɋC���ɖ炵�����Ă��������B
�܂��܂����J�Ȍ䋳�����肪�Ƃ��������܂�
GW���ɖ؍ނ���ƁA����Ȓi�K�Ń��X���Ă������̂���������݂܂���c
�ȑO���烂�m��������p�̂��̂�F�X�Ɩ͍����Ă����̂�
������FR6.5��1�{����Ă݂悤���Ə������ł��B
�R�[���c�C�[�^�[TW6NG-8�ƈꏏ�ɍw�����|���܂����B
����A�z�[���Z���^�[���U���Ƃ���
�p�C���W�ύނ�40�~45cm�̃J�b�g�ނ��������̂�
����Ɏ��̘͂g�����t������@�ōl���Ă��܂��B
40cm�{15cm�~2�{����foc=115Hz�Ƃ��������ł��B
�Ƃ肠����FR6.5����ʉ�����őg���Ă܂����B
40�~45cm�A15mm���̃o�b�t����
15�~45cm�A19mm�̔ŃO�����͂��������ł��B
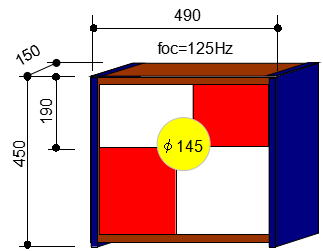
��30������̎��g�������i�������J�}�{�R�^�j

�X�e�b�v���������i�������f���Ń^�C�g�j
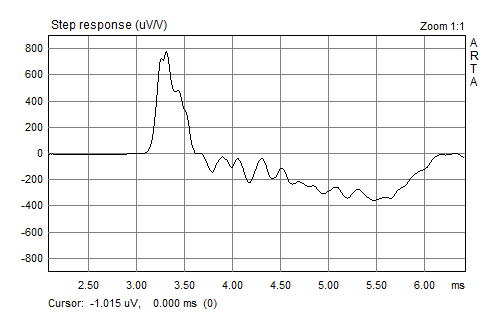
����ȃJ�}�{�R�����ł��A�X�e�b�v�������X�����_�[�Ȃ̂�
�ቹ���������x�ꂸ�ɓ����^�C�~���O�Ńo�V�b�ƌ��܂�܂��B
���̕ӂ̓��j�b�g��Q�����������̌����Ă��邱�Ƃ�����܂��B
���肽�Ă̂Ƃ��͍������o���Ƀ��S���S�����Ă��̂ł���
2~3���Ԗ炷�ƐF�ʊ����O�b�Ƒ����ăo�����X���ǂ��Ȃ�܂��B 500~2.000Hz�̐��������Ă���̂ŁA������Ƃ����\��̉�����
�t���b�Ɩc��オ���ċ�������Ă���悤�Ɋ����܂��B
�T�u�R�[���̋��U��4kHz��5kHz�ɂ݂��A���ꂪ�ǂ������������ɂȂ邯��
�X�e�b�v�����ł݂�悤�ɏo�������ŏI���A���������܂���B
�̂̃h�C�c���t�������W�ɔ�ׁA�����Ɛ����h�̉����ł���
���̔����������A�ؗ͂ɗ��t����ꂽ�\��̖L�����̂ق������������܂��B
�����ĂĈ�Ԗʔ��������̂�1970�N��̗̉w�Ȃ�
���i������萺�������Ǝ�X�����A�̒�������ۂ��v���o���܂����B
���̋t�������ĂŁA���Y���̉����o�����͋����O�C�O�C�����܂��B
400Hz����������ł܂����A�����ƍA���Ƃ̕������ł���
�o�b�N�o���h������オ���Ă��A���̕\����ꂸ�ɑO�ɏo�Ă��܂��B
��ʊJ���^�̍Œዤ�U���g���̋��ߕ��������o���Ȃ��̂ł����c
�o�b�t���̍����͕K�v�Ȃ��̂ł����H
�{���̎��́@foc=4250/L�@��
L �̓X�s�[�J�[�̒��S����[�܂ł̍ŒZ�����ł��B
�܂�Ȃ����ꍇ�́A�܂�Ȃ��������܂݂܂��B
����͉����Ȃ̂ŁA��ʕ����Ō��܂��Ă��܂��B
��W���Ȃ��Ē��ׂ��Ă��������ƂɂȂ�܂��B
�悭������̂́A�o�b�t���̌ŗL�U��������邽��
���j�b�g�̈ʒu���㉺���E ��Ώ̂ɂ��邱�Ƃł��B
�Q�l��IEC�K�i�̕W���o�b�t���̐��@�������܂��B

���ꂾ��20cm�p�̍ŒZ������45cm�Ȃ̂�
��ʓI�ɂ͂��̒��x�̑傫�����K���ƂȂ�܂��B
����̓{�[�J�������Ƃ������Ƃ�
200Hz�t�߂̋������Ⴂ���g���̓W���}�Ȃ̂�
���߂Ƀ��[���I�t����悤�� L=34�����ɏk�߂܂����B ���Ȃ݂Ƀ}�C�N�ł����錻�ۂɂ͋ߐڌ��ʂ�����
�}�C�N�ƌ������߂Â��ɏ]���ቹ���c��݂܂��B
https://pubs.shure.com/guide/BETA58A/ja-JP
���̂��ߑш�̍L���R���f���T�[�}�C�N�ł̓��[�J�b�g�t�B���^�[�����
�œK�ȃo�����X�ɒ������₷���悤�ɂł��Ă��܂��B
https://marketing.hibino.co.jp/akg/50.html
����̌�ʉ�����̏ꍇ��
�V���A�[�̃{�[�J���}�C�N�̑f�̓����ɋ߂�
�X�s�[�J�[�̌��̐v���\���A�i�E���X�p�Ƃ������Ƃ�
���������̏\���s���͂��Ȃ����Ƃ�z�肵���Ǝv���܂��B
���ۂɂ́A���W�I��e���r�̕����@��̃X�s�[�J�[��
�m�̓������킸�A���̉����Őv����Ă��܂����B �����͐F�h��ł��B
1950�N��̒��ۉ敗�Ɏd�グ�܂����B
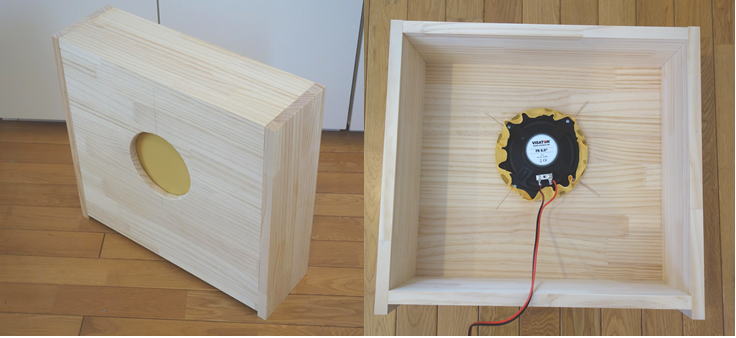

>>165
�����o���܂���
���肪�Ƃ��������܂�
>>167
�Y��ł��� Visaton FR6.5�����X�ɗ����グ�̃G�[�W���O���i��ł���
���̎��n��1960�N�ネ�b�N�A������Ȏ҂̃u���e�B�b�V���n�ł���B
�r�[�g���Yvs�X�g�[���Y�ȊO�������ƒ����Ă݂��B
CD�Ŗ炵��Ȃ��̂́A���̕��j���������Ȃ������Ǝv���B
���Ƃ���1960�N��̃��b�N�͑��v���[���[�Œ����Ă������̂�
���ꂪ�ȉ~�t�������W�i8��5�C���`�j�����^�^��ǂŖ炷�����̂��́B
�v���[���[���̓Z���~�b�N�E�J�[�g���b�W�q���ł���B


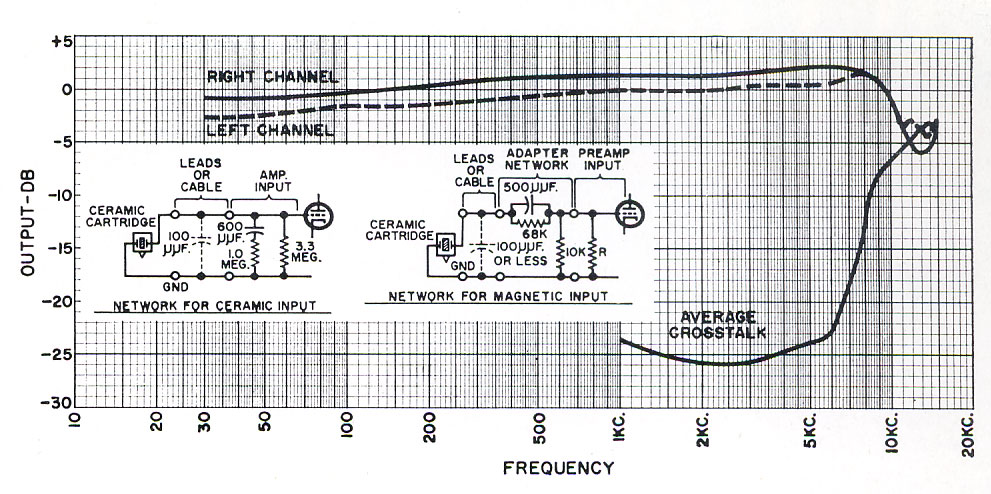
��ʉ�����ɓ��ꂽVisaton FR6.5��
�ቹ�̈����ۂ��^�C�g�Ń��Y���̈�̊����o���₷��
����̃{�[�J����͋��������o��
������ɊJ���I�Ȕ{�����o��
�����������ɂ����ƃp���[������i���\���ꂪ�d�v�j ���Y���̈�̊��Ƃ����ƁA�h���͂̂悤�Ɏv�����낤��
�ǂ�����Ă����Y�����e��ł��āA���Ƀx�[�X�̕\������������Ă���B
���ꂪ���ʂ𑝂��ăp���[������Γ����قǃK�b�c�����ݍ����Ă����B
�u���I�ȉ��̐����オ�肪�A���܂��ɍ��܂�Ă���؋����B
�����a�X�s�[�J�[�̃p���[���X�|���X��
���C�O�a�̂悤�ȏ�ԂɂȂ��āA�g�`�Ɉ��̃R���v���b�V�������|����B
���ꂪ�T�E���h�ɔS���ŁA���͂��o������
����|�C���g���߂���ƁA�g�`���x�b�^���ƒ���t���ă��S���S����B
Visaton FR6.5�͂��̕ӂ̏���܂ł̕����L������Ă���
�X�J�b�ƐU����ăz�[��������ł����悤�Ȕ������Ԃ��Ă���B
�����Q�������������������藘���Ă���̂�
�o���h�̉��ʂ�Max�ɂȂ��Ă����Y���̗��������ĂƂ���
��ԑ�ȂƂ��낪�S�ۂ���Ă���B
����FR6.5���悤�₭�`�ɂȂ�܂���
�o�b�t����60�~45���s��30���S��1.5
�{�[�J�����S�̃��X�j���O�ׂ̈ɉ��s���������炢���w�삳��Ă����ɂ��ւ�炸�A��ʊJ���͒ቹ���{���ɏo��̂��H�Ⴄ���j�b�g�ɕς���]����A�͂��܂����܂��s���Ȃ���Ζ���o�X���t�ɓ�����ȂǂƂ����ׂȍl�������s��30�ɂ��Ă��܂������R�ł��c
���j�b�g������ĉ��o�����Ă݂��
�z���ȏ�ɒቹ���o��w
�^�C�g�Ȓቹ�łƂĂ��S�n�ǂ��̂ł���
�v�������{���o�Ă܂�
���ꂩ�����܂��Ȃ������������
���̕\�ʏ������l���܂�
��ʂ̓��肪�C�ɂȂ�ꍇ�́A�z���ނő����͊ɘa�ł��܂��B
����ň�ԋC�ɂȂ�̂́A�����̂悤�Ȓ�ݔg�Ȃ̂�
�V�̗������ł����ʂ��o�܂��B
����ɑ��̕Е�����������A�����N�b�V�����Ȃǂ�u�����肵��
�F�X�Ǝ����Ă݂Ă��������B
>>173
������w�����肪�Ƃ��������܂�
�X�s�[�J�[��ʃX�y�[�X�ɂ��܂�]�T���Ȃ��̂ŃN�b�V�����͒u�����̂ł���
�z���ނ������Ă݂܂�
���ꂩ����X�������肢���܂� Jensen C12R�̑��_�̃c�C�[�^�[��Visaton TW6NG��t���Ă݂��B
�ŋ߂Ƃ�Ɩڂɂ��Ȃ��Ȃ����R�[���c�C�[�^�[����
1970�N��ɂ͑��������̂ɁA�f�W�^������ɓ����ĂقƂ�nj����B
���R�͕����U����j�Ȃ��f�W�^���^���ł͎�����肾��������B
�t�ɂ����f�W�^���L���̌�����������ɂ���Ƃ����Ă����B
Visaton�̏ꍇ�̓Z���^�[�L���b�v���������ŏ������₩�Ȉ�ۂ���
�W�F���Z���Ƃ̃X�s�[�h�����K�b�V�����ݍ����ė͋����{�[�J���ɂȂ����B
���ƂȂ��̂̃��m�����E���W�J�Z�̉����v���o���Ă���̂���
�|�b�v�X��b�N�ŁA�������Ƃ���̐���オ����݂���̂�
���ʂ��オ���Ă����Y���̎��ꂪ�ۂ���Ă��邩��ł�����B
�t�ɂ����o�C�I�����̋����ɏ������Ɏc��U���b�Ƃ������G��������
�l�i�������ƌ��������ȂƂ��낾�B
�z���ނ��V�Ƒ��Жʂɓ\�莎�������̂̂�͂�X�s�[�J�[��ʂɃX�y�[�X�]�T���Ȃ����̂Œቹ���]�v�ł�����
�����̂��̂̉��s������Č��炻�����Ƃ��v���܂������A�d�������Ƀv���A���v�Œ��𐔃f�V�x�����Ƃ�����[���������x���ɂ͂Ȃ�܂���
qts�͒Ⴂ�ق������j�A�Ȕ���������Ƃ������ł����A����FR6.5�ł��u���͂������܂�
��ʊJ��������ł��傤���H
Qts��fo�t�߂̒�R�̍����������Ă���
��ɒቹ�̏o�₷�����v��ڈ��ɂȂ�܂��B
�t�Ɍ�ʉ�����̓R�[�����ւ̒�R�����Ȃ�
fo�ȏ�̑ш�̔����͂����Ԃ鑬���ł��B
���ƃt�������W�͈�ʂɃR�[�������y���imo���Ⴂ�j�̂�
�����a�̃E�[�n�[�ɔ�ה������@�q�ɂȂ�X��������܂��B
���������A���{���ԕ����A�������[�~��50���N�Ƃ������Ƃ�
�g�X�s�[�J�[�Ń��W�I�����h�L�����y�[�����s���Ă��邪
�g���m�����X�s�[�J�[�Œ������h�A�̊ԈႢ����Ȃ����ƁB
���m��������p�̃X�s�[�J�[��
����Siemens��SABA�Ȃǂ̃h�C�c���t�������W���������B
�����炭���W�I�������i�̂̃f�b�h�X�g�b�N�ŁA1980�N���2~3��~���������̂�
���݂ł͌̐����������茸���āA���i���\�{���x�Ŏ�������B
���͂����p�Ƃ��Ă͕~���������Ċ��߂��Ȃ��B
����ɑ�����̂Ƃ��ē�Visaton FR6.5��
���݂���������ĉ��i��2,800�~
��ʉ�����Ɏ�y�ɓ���Ċy���߂郆�j�b�g���B
Visaton FR6.5�́A�����郍�N�n���̒��Ԃɂ݂��邪
���g�͑啪�قȂ�Ƃ��낪����B
�ЂƂ�Qts=1.96�Ƃ��������ŁA�o�X���t���ƃ{�����Ďg�����ɂȂ炸
��ʉ�����ɓ���Ē��x���������ł���B
�����ЂƂ́A�����R�[���Ȃ̂ɈӊO�Ƀp���[�����Ă��ւ����ꂸ
���Ẵ��N�n���̂悤�ȉߓ��͂Ŕj�]����コ�͂Ȃ��B
���Ƃ͊̐S�ȃg�[���L�����N�^�[�́A�����n���̂���O�̂߂�̉���
1960�N��̃��b�N�ł��S���C�����Ȃ��炵��B
���m�����Ƃ����ƁA�قƂ�ǂ̓W���Y�ƃN���V�b�N�̐̂���̃��R�[�h�}�j�A��
�r���e�[�W��JBL�ƃ^���m�C�Ńg�h�����h���Ƃ����������B
����ŁA�|�b�v�X��b�N�̂ق��́A����ɂӂ��킵����O�����C�ɂ���
JBL����LE8T��4311�A�^���m�C����III Lz�Ŏ��܂�Ǝv���B
����ł��܂��܂��Ȃق��ŁA�ŐV�̏��^2way�Œ����Ę^���]�܂ł���̂�
���g���o�����X���������Ă��Ȃ���Ȃ����Ƌ^�������Ȃ�B
�����g�́A�����Visaton FR6.5��
���b�N��|�b�v�X�̈��D�ƂɑS�ʓI�ɂ����߂���B
EQ�J�[�u�̋c�_�Ȃǂ���O��
�t�������W�̔����Ƃ������X�|���X���ׂ����B
���������Y���ƃ{�[�J�������Ȃ̂���
�����̋c�_�����܂�����������𐮂���ׂ����B
1970�N��ɂ͋Ȃ�Ȃ�ɂ����W�J�Z����������
�t�ɊC���Ղ̃��C�u�Ȃǂ͉������ň��������B
�������炱���A�t�������W�Ńo���o���炷�ׂ��Ȃ̂��B
�Â����b�N��|�b�v�X���Ƃ��A���̃g�[���L�����N�^�[������Â炭
�t���b�g�ȃ��j�^�[���Œ����Ă����A����ň��S�Ǝv���Ă���l��������
�l�I�ɂ͂��܂肨���߂��Ȃ��B��͕ʂ̂Ƃ���ɂ������̂��Ǝv���Ă���B
�Ⴆ�g�[�L�[�����ɒ�߂�ꂽ�����K�i�ɃA�J�f�~�[�Ȑ������邪
�ȉ��̂悤��100~1,000Hz�̗��[��-3dB/oct�Ń��E���h����B

����͍L����Ԃł̎��R�ȉ����ŁA�R���T�[�g����������������B
THX�K�i�ł��A�z�[���V�A�^�[�p�ɉߏ�ɂȂ�₷��������
���[���I�t�����郂�[�h�����������炢�ł���B
���Ȃ݂Ƀ��m�������ƍL���w�����ɉ����g�U�����Ē�������
��30~45������v��ƃ��[���A�R�[�X�e�B�b�N�ɋ߂Â��B
�����Visaton FR6.5�̎��g�������𑪂��Ă݂��
�ȉ��̂Ƃ���ŁA����ł�2~5kHz������o���C���ł���B

�܂�����̃p���X�M���̓m�C�Y�ƍ��������ŋ�ʂ����Ȃ��̂�
�ނ���L�����N�^�[��ς����肷��̂ŁA�ςɐL�тĂȂ��ق��������B
�Â��^���̏ꍇ�́A�_���X�z�[���̂悤�ȍL���ꏊ�Œ����悤��
�������h�ڂɒ������Ă���ƍl����̂��Ó��ł���B
����͎���ƂƂ��ɉ��y�̃p�[�\�i�������i�ނɂ���������
�T�E���h�͋ߐڂŒ����̂ɓK�����t���b�g�u���ɐ�����ꂽ�Ƃ�������B ���������Â��^���̃o�����X�ɂ��čl���鎞
���͌��݂�J-POP�̏��w�b�h�z����������Ƃ���
���Ȃ蒆����ɃA�N�Z���g���������^���̑����ƌ�����B
���Ȃ݂Ƀw�b�h�z���ł̎����́A�O�����̋��U�̉e�����傫��
4kHz�t�߂ɋ����s�[�N�������Ă���B
���̓��������Ƃɐl�Ԃ̌���͔��B���Ă������Ƃ��l������B

���������ߏ�ɋߐڂŒ��������ɂ��āA���Ȃ蒆�����}�������Ńt���b�g
���̂܂܍L����ԂŖ炷���炢�Œ��x�����B
���̈Ӗ��ł́A�A�����J���E�|�b�v�X��J-POP�Ǝ���x��ŕ���ł���
�t��20���I���̃\�E���̂悤�ɗ��������������T�E���h��
����I�ȃI�[�f�C�I�Œ����f��������̂ƂȂ��Ă���B Visaton FR6.5���A�̂��炠�郍�N�n���ɔ�׃����n���̋����̂�
�X�e�b�v�������݂Ă�������x�킩��B
�X�e�b�v�����͋�`�g�̗����オ��ɑ��鉞����
���z�I�ɂ́A���悩����܂Ŋ��炩�Ɍ�������B
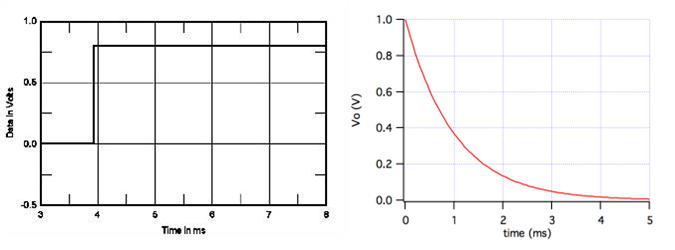
�o�X���t���ɓ��ꂽ���N�n��PE-16M�̃X�e�b�v�������݂��
��������ቹ�܂Ŗ��ՂȂ��o�Ă�������
4���炢�̑ш�ɕ�����Ĉʑ��̂��тꂪ�݂���B
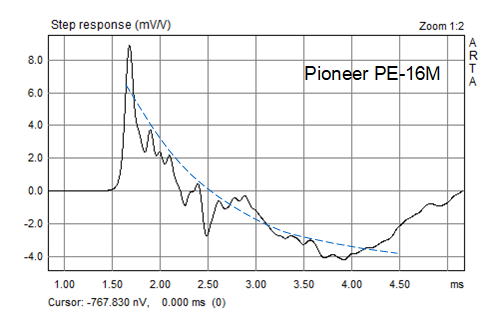
����̌�ʉ�����ɓ��ꂽVisaton FR6.5��
���ቹ�ɍs�������܂�0.5ms�������炸
�傫�Ȉʑ��̂��т���Ȃ��N���[���Ȕg�`���Ƃ킩��B
1.5ms�قǔ��������Ă���̂�4~5kHz�̃����M���O���B
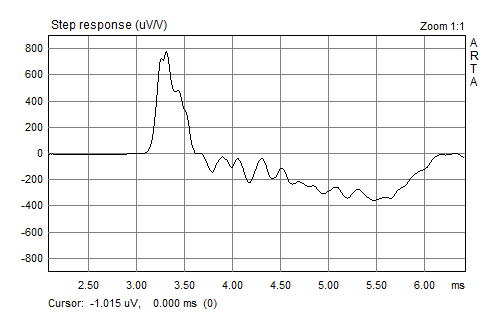
���Ȃ݂Ɉ�ʂ̃}���`�E�F�C�́A���Ȃ�L���ȃ��j�^�[�X�s�[�J�[�ł�
�N���X�I�[�o�[��H�̉e���ō���ƒ��Ƃ͊��S�ɕ�������B

����͍���̉𑜓x�ɁA���̃���������������Ȃ����_�����邪
�唼�͒�ʊ����o���p���X���̐M���̃N���[�����ɔ�₳���B
���m�����ɂ����Ƃ��A�}�ɉ����₹�ׂ�̂́A�p���X���̔g�`�����ڗ�����
����ȉ��̐M�����}�X�L���O���Ă��܂����炾�B �ŁA���ꂾ���X�����_�[�Ȕg�`�ł܂Ƃ܂�Ɖ����ǂ����Ƃ�����
���b�N��|�b�v�X���̂ɁA���ꂭ�炢�X�y�b�N�������Ȃ��Ɩ{�̔������Ȃ��B
�����1950�N��̃I�[���f�B�[�Y���猻���J-POP�܂ŋ��ʂ���
�X�^���_�[�h�ȃX�y�b�N���Ǝ����ł͎v���Ă���B
�d�ቹ�������Y���̃L���A����������{�[�J����̃N���A�l�X
����������O�̑ш�Ŏ��R�Ȕ����Ŗ邱�Ƃ��ǂꂾ���d�v����
���y������Ƃ��ĊO���Ă͂����Ȃ��X�y�b�N�Ȃ̂��Ǝv���B
�����Visaton FR6.5����ʉ�����ɓ��ꂽ�ꍇ
�d�ቹ�������Əo��X�s�[�J�[�����x�[�X�̃j���A���X���N����
����ł��ă{�[�J�����X�b�Ɣ����悭����Ă����B
�܂�A���|���|���̏d�ቹ�̍Đ��\�͂ɂ�����邠�܂�
���y�ɑ�Ȃ��́A�܂蓮�I�ȍĐ��\�͂�B���ɂ��Ă���B
���ƃ��m�������u��g�ނƁA���m�����^���łȂ��Ⴞ�߂Ǝv����������
�X�e���I�^���ł����m�����Œ����Ɩʔ������y�͑�R����B
�����g��10�N�قǑO����X�e���I�ł̎�������߂ă��m����1�{��
CD�v���[���[����ȈՃ~�L�T�[�ɂȂ��Ń��m�~�b�N�X���Ē����Ă���B
���ʂɕ����������m���������ʼn��ꊴ��������̂�
��ɍ���̋t�����������m�����ڍ��őł��������������
�����I�ȃo�����X�܂ŕς���Ă��܂��B
�~�L�T�[��3�o���h�E�C�R���C�U�[�̒�����ƍ�������݂�
6dB���x�������邱�ƂŁA�t��������ł��������o�����X����B
���̂Ƃ��p���i���E�U�蕪���j�͒����̂܂܂ɂ���B

���Ǝ����g���Ă��郄�}�n�̃~�L�T�[�ɂ�
�ȈՓI�ȃf�W�^���E���o�[�u���t���Ă���
���ꊴ�̃R���g���[�����ł���B

�����ƃn�T�~�͎g���悤�ƌ������A�C�R���C�U�[�ƃ��o�[�u��������
����ő�T�̘^���̓��m���������ŏ\���ȉ����ɂȂ�B ����ƃ��m���������ɂ́A�����̂����X�s�[�J�[��������
���݂̑����̃X�s�[�J�[�͍���̎w�������s�q��
���m�������Ƒ����ׂ邩���S���S���邩�̂ǂ��炩�ł��܂�ǂ��Ȃ��B
�������͓�����ʼn����H�v���悤�������ł��ł��Ȃ��B
Visaton FR6.5�͒�����̎w�������L���ēK���Ă��邵
�����ЂƂg���Ă���Jensen C12R�Ƀc�C�[�^�[��lj����Ă�OK�B
�ǂ����������Ɏ�̃����M���O�������āA���ꂪ����t���Ă���B
���Ƃ͌�ʉ�����ɓ���Ă����v��Qts�̍����v�B
����Œ����܂Ō��ʂ��̍����L���̂����������Ԃ��Ă���B
Visaton FR6.5�̃r���e�[�W����1970�N��O���̂��̂��Ǝv����
���͂��̍��͊C�O���܂�FM�X�e���I�����s��������
�����������オ�i��ŏ��^2way�Ɉڍs�������O�̃X�^�C�����c���Ă���B
���K�i�Ƃ̉��ʌ݊���ۏ��邽��
�������AM���W�I�ɓK�������₩�����c���Ȃ���
�S�̂Ƀ��C�h�����W�Ȏu���������Ă���̂��B
���̉��₩���́A�^��ǂ���g�����W�X�^�[�ւ̈ڍs���Ɍ���
�Ⴆ��NEVE 1073�̂悤�ȃg�����X�t���}�C�N�v�����W���[����
EMT�̓S���o�[�u�̂悤�Ȃ��̂��܂܂��B
�����Ƌ������Ď��R�ȏΊ炪�ۂĂ�Ƃ����̂��r���e�[�W���Ȃ̂���
���̓t�������W�Ƃ����`�ł͍��ł͂قƂ�ǂ݂��Ȃ��B
����̃I�[�f�B�I���_�ł͂����̉��͕t�щ��i�c�݁j�ł���
�^���ɂ���Ă͌ÏL�����ς̂悤�Ɋ�����l�����邩������Ȃ��B
�I�[�f�B�I�i���_�҂ɂ͒��r���[�Ȑ�Ŏ�̂悤�ł�
�^���͎c�葱���āA�|�b�v�X�̏ꍇ�͈�����œ�x�ƍĘ^����Ȃ��B
���y��̂ɍl����Ȃ�i���r��̊��ω��ɑς�����@�ނ�
�I�[�f�B�I�̎�ɉ����ėǂ��̂��Ǝv���B
���Ȃ݂Ƀ��R�[�h�Ղŋ���
�m�C�}�� SX-68����SX-74�Ɉڍs����Ԃ̏o������
�\�����̃����W���̊g���Ɖ��ꊴ�̕s���肳���������Ă���B
���ꊴ�̕s���肳�̓}���`�g���b�N�ւ̑Ή����܂��A�i���O������
���o�[�u�̑��p�͎��^�����܂��܂��ȉ�������܂�����ւ�
���ʓI�ɃX�y�[�X�G�C�W�ƌĂ��F���I�Ȗ������̉��ꂪ�`�������B
���ꂪ���������̂�1978�N�ɃX�`���[�_�[A800����������Ĉȍ~��
�������Ɍ������ʂ����炩�ɂȂ���BBC�̃j�A�t�B�[���h�����Ƒ��܂���
���݂̃I�[�f�B�I���_�ɋ߂����̂��`������Ă������B
�ł́A���k�ȉ��ꗝ�_�Ɋ�Â��Ȃ��X�e���I�^���͂ǂ��Ȃ�̂��H
�����I�ɂ�A800��A80�̈Ⴂ�Ȃǔ���͂����Ȃ���a���������B
���̌������s�[�X�߂�̂�Visaton FR6.5�ł̃��m�����������B
�F���I�Ȗ������̉���̌`���̌�����
�^���̖��Ƃ������A���݂̃p���X�����ɉߏ蔽������
�c�C�[�^�[�̐v�Ƃ̑��ݍ�p�ŋN���Ă���Ǝv���B
�����̈�ʓI�ȃX�s�[�J�[�̓R�[���c�C�[�^�[��������
�����Ĉ����낤�����낤�ł͂Ȃ��A�v�I�ɃR���g���[���������₷������
�O�H2S-305�AJBL 4311�Ȃǃv���@��ɂ��g���Ă����B
�����ŋ߂�Jensen C12R�̃c�C�[�^�[��Visaton TW6NG�ɑウ����
�A�i���O����̘^���͂���łȂ��ƃ_���Ǝv���鉽�����l�܂��Ă���B
����1968~74�N�̘^���́A���g�������W�����L��������
�꒮����Ɣ����炭��������A�{�[�J�����������Â�ł܂�����
�����Ȋ������V�������Â��̂ق����ڗ���ۂ��������B
�����̓��}�X�^�[�Ɏg�����e�[�v����������R�s�[�������̂�������
��������AD�R���o�[�^�[�̐��x���������̐F�X�Ȉӌ����������B
�Ƃ��낪Visaton�̃T�E���h�e�C�X�g��
�̃��R�[�h�Œ������悤��
�{�[�J�����͋��������Ă���̂�
���悪�_�炩���L����s�v�c�ȃo�����X���B
�����1990�N��̃o�W�F�b�gCD�ł���ۂ͕ς��Ȃ��B
���悪�L�т���Ȃ��A�U���������ɕt���Ƃ�
���������v��Ȃ��ш���o������
���̑N�x��ۂ錍������悤���B
�Ⴆ��EMI�̃A�r�[���[�h�ł�1972�N��1980�N���r�����
JBL 4320����4333�����C���ɁA�I�[���g�[��5c���T�u�ɂ��Ă���B



1972�N�̃A�����E�p�[�\���Y�͑ш�15kHz�܂ł�4320�ƈꏏ��
�I�[���g�[��5c�����m�����ł̎����Ɏg���Ă���B
���̎���̉p���̓|�b�v�X��AM������������
��҂̃��R�[�h���������v���[���[������������B

FM�����ł���50~15,000Hz�̋K�i�Ȃ̂ɉ���
2kHz�ȏ�͎O�p�m�C�Y�ō���̃_�C�i�~�b�N�����W�͉��̌�������
CD�̒�����̃f�W�^���m�C�Y�Ȃ�ĕ���������ɂȂ������B

�����B&W���j�^�[�̓��鍠�ɂȂ��Ă��~�L�T�[��͋����̂܂܂�
CD�K�i�����肷��ۂɑ����̘^���G���W�j�A�Ƀq�A�����O�������ʂ�
16kHz�ȏ�͊y���Ƃ��ĉe�����Ȃ��Ƃ̈ӌ����������߂��B
������ǂ����Ⴂ�������A�f�W�^���Ή��̂��߃I�[�f�B�I�@���
20kHz�܂ōĐ��ł��Ȃ��ƕs�Ǖi�Ƃ݂Ȃ��ꂽ�̂��B
�ł��A������80~10,000Hz�ŏ\���������Ȃ��
�ǂ̃I�[�f�B�I��]�������邾�낤���H �X�e���I�^���ŃT�E���h�X�e�[�W���A�[�g�̈�܂ʼn����グ���̂�
���L�V�[�~���[�W�b�N�u�A���@�����v��ҏW�����{�u�E�N���A�}�E���e���������B
����܂Ńo�����X�m�F���x�Ɏg���Ă������^���j�^�[��
�X�e���I�̒�ʊ��𐳊m�ɔz�u���邽�߂̕K�{�A�C�e���ƂȂ�
���}�nNS-10M���g�p�����j�A�t�B�[���h�E���j�^�[�̕��@�_���m�����ꂽ�B
����܂ł̃I�[���g�[��5c�ɔ�׃p���[�n���h�����O�ɗD��
�i�������肵�Ă������߁A���E���̃|�b�v�X�n�̘^���ō��ł��������B
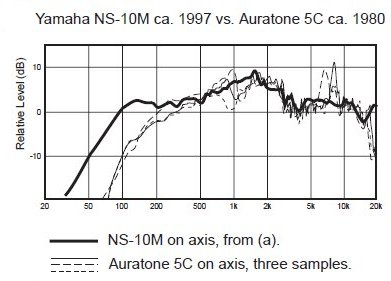
���łɃc�C�[�^�[�Ƀe�B�b�V����\��V�������s������
���悪3��B�}������Ƃ����ȊO�ɂ�
�c�C�[�^�[�̃p���X������}���ăX�e�b�v�����𒆈�哱�ɂ����Ǝv����B
����ŃX�s�[�J�[�̕Ȃ�ʂ�z�������ՓI�ȃX�e���I�������o����B
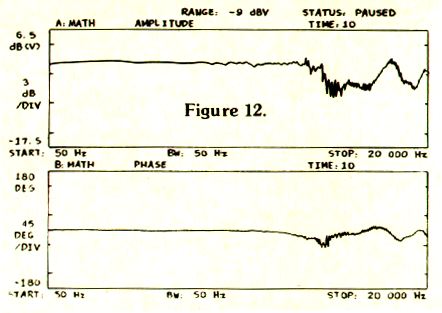

�Ƃ���Ń��L�V�[�~���[�W�b�N�u�A���@�����v�Ȃ̂���
���������^���ł����m�����Œ����Ă݂�ƐF�X�Ɣ���������B
�܂�������O�̂��Ƃ����A�e�p�[�g�̓x�[�V�b�N�ȉ��Ř^���Ă���B
���̌������̂��ƂȂ̂ŁA���͋C�ł��܂����Ă邾������Ɗ��J���
�e�p�[�g�͋����قǑf���Ő��^�ʖڂȉ����Ȃ̂��B
�ӊO�Ƀ^�C�g�ȃh�����ƃx�[�X���_���X�i���o�[����������x���Ă��邵
�G�O���{�[�J�����������葫�̒��������Y��������ł���B
���̂������łǂ̊┧�ɐl�������āA�݂��̑傫�����ǂ����Ȃ�
���̂��Ȃт��Ȃ��ŞB���������y�Ȃ̍\�}�����炩�ɂȂ�B
���̂悤�ɉ��ꊴ���������������m�����ł̎�����
�ԊO���X�R�[�v�̂悤�Ɏ�����I�m�ɑ�����X��������B
���Ƃ����ăM�X�M�X���������ł��Ȃ��A�_�炩�����ێ����Ă���
���Ȃ₩�ȋؓ��̂������Ɏx����ꂽ�A�X���[�g���ςĂ��銴�����B
�l�I�ɍD���ȃA���o���ɋg�c���ގq�u�t���b�p�[�v��������
�������o�[�Ђ��߂��o�b�N�o���h�̔]���A�����W���y�Ȃ��ǂ��Ɏ����Ă����̂�
�h�L�h�L���Ȃ���s����ǂ��悤�Ȋ������A�������Ă��O���Ȃ��B
�����ɂ����ƃW�F�b�g�R�[�X�^�[�E���[�r�[�̓W�J�Ɏ��Ă�B
���m�����Œ����ƁA�܂��g�c���ގq�̐��ɐc���ʂ�
���̏����̖ʉe���c�� �͂����t�ȃL���������R�ɗN���o�Ă���B
���ʂɃo���h�̉��ɖ�����₷�����Ȃ̂���
���̋���Ȑ��̕`�����܂�70�N�������������B
�����ЂƂ́A�������ᔠ���Ђ�����Ԃ����悤�ȃo���h�̃A�����W��
�e�X�̊y��ł����ƈӖ��������ăU�����Ă���l�q������B
���������l�ߏ�Ԃɂ���u���b�N�E�R���e���|�����[�n����
�K���{�X�I�Ȑl�����A�����W�ɖڂ����点�Ă���̂���
���̃R�����e�̂��Ȃ��Ƃ���ŁA�����ȋ����Ń}�C�N�ɗ�����
��[���h���ŃX�^�[�g���������ɂ��݂���B
����������ۂ����̂��A���m�����Œ����Ɖ���ɍ��߂�ꂽ
�y��Ԃ̕���ʒu���q�G�����L�[�����Z�b�g�����
�y���̃f�B�e�[���ɏW�����Ē�����悤�ɂȂ邩�炾�Ǝv���B
���Ƀh�����A�x�[�X�̕\��̖L�����́A���̃v���C���[�ɐG������Ȃ���
�F�ʂ�ω������ăX���X���Ɩ�o��߂�J�����I���̂悤���B
������X�e���I�̉��z�����ł̓{�����₷�����̂̂ЂƂł���B
���m�����Œ������ƂŎv�����ׂ�̂́A�e�����Ƃ������y�Ƃ�
��r�I�V���v���Ń_�C�i�~�b�N�����W�̋����Ǝv���鉹�y���B
����ŁA�����̓_�C�i�~�b�N�����W�������Ƃ�������
�ނ���R���v���b�T�[��o�[�u�ʼn��H���Ă��Ȃ���
�@�ׂŃX�s�[�h�̑����g�`�̗����オ���v������B
��ʂɃI�[�f�B�I�ɂ�����@�ׂ��Ƃ͍���̕���\�̂��Ƃ��w����������
�X�e���I�̏ꍇ�́A�����8~15kHz���炢�̊�����
����̃R���g���[���A��ʊ��̃p���X���Ȃǂ����o�ł���B
���Ƀ_�C�i�~�b�N�����W�̑唼�������̏��ɔ�₷�̂��B
����ŁA���m�������Ƃ��������떂�����͗����Ȃ��Ȃ�
�𑜓x�̉��߂͋t�]���āA100~6,000�g���̐����̂ق��ɏW���B
����悩�璆����܂ł̔g�`���ώ��Ɋm�ۂ���Ȃ��ƕs���R�ɂȂ�B
�܂�e�����⎺���y�̓��m�����Œ���������������̂ł͂Ȃ�
���m�����Œ�������ɂ́A����ɂӂ��킵���r�q�Ȕ������K�v�Ȃ̂��B
��L�̃A���@�����̊e�p�[�g���^�ʖڂɘ^���Ă���Ɗ������̂�
�E�[�n�[�����悤�ȑш�̎��������g��̂܂c����
���Ԕ��Ńt�H�[�J�X���Â����Č떂�����Ă���킯�ł͂Ȃ�
�{���̓����������̊���ڎw���Ē��J�ɑ��荞�܂�Ă��邱�Ƃ��B
����悩�璆����܂ł̔g�`���ώ��Ɋm�ۂ����Ƃ����̂�
�^�C���R�q�����g�����i���ԓI�������j�ʼn������邱�Ƃ��ł�
�C���p���X���������X�e�b�v�����̂ق����Ȃ�����₷���B
���Ȃ݂�Visaton FR6.5�̃X�e�b�v�����͈ȉ��̂Ƃ���B
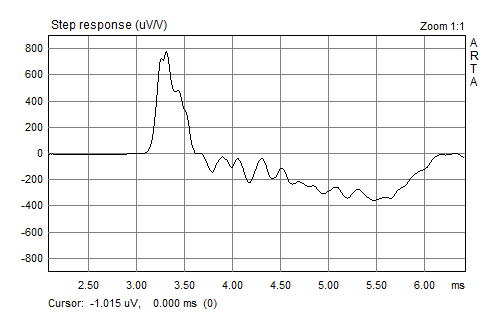
��������N�n���̂��̂Ɣ�ׂ�Ƒш�͋������g�`�̓N���[���ł���B
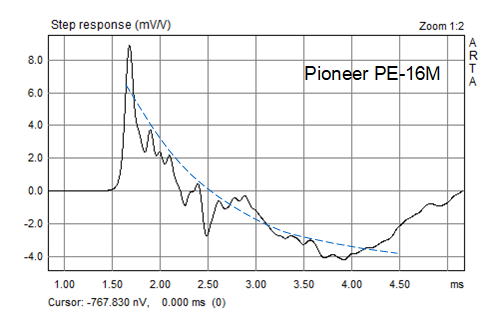
����Ɉ�ʓI�ȃ}���`�E�F�C�E�X�s�[�J�[�ł͈ȉ��̂Ƃ����
���j�b�g���Ƀs�[�N�ƈʑ������т�A�E�[�n�[�͑啝�ɒx���B
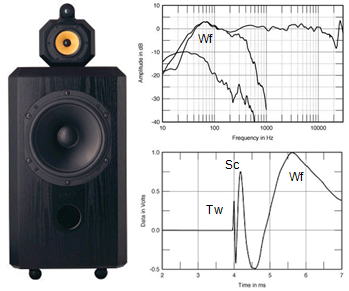
����ɉ𑜓x���V�t�g�����̂̓X�s�[�J�[�̐v��̖��ł�����B
���Ȃ݂Ɏ���Jensen C12R�{Visaton TW6NG�̏ꍇ��
�ȉ��̂悤�Ƀt�������W�Ȃ݂̑f���Ȕg�`��ۂ��Ă���B
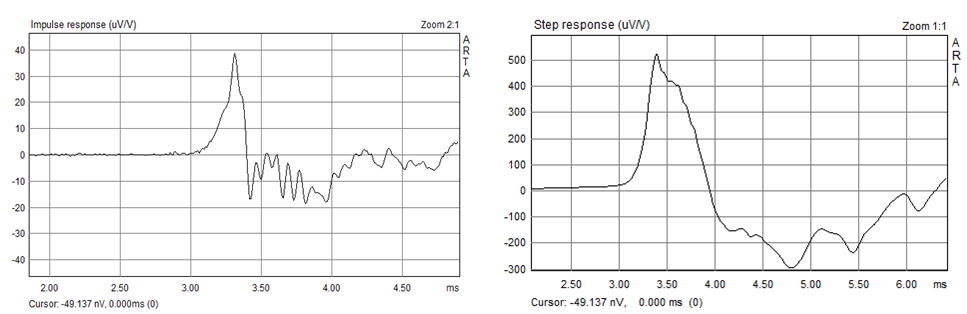
�Q�l�ɃC���p���X�������ڂ������S���Y��Ȕg�`��
���g�`��MQA�̃V���[�g���[���I�t�̃C���p���X�M���Ƒ����ł���B
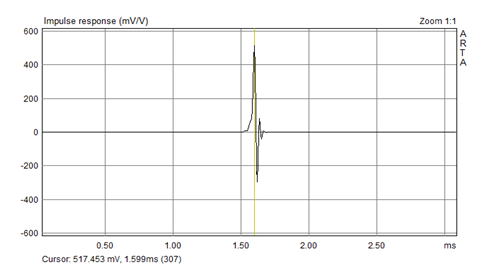
�X�s�[�J�[�̉������Ԃ����C���M����3�{�܂Ŋԉ��т��Ă���̂�
�d�C�I�Ȓ�R�̂Ȃ����C���M���̔�r�ł͊撣���Ă���ق���
��ʂ̃X�s�[�J�[�ł͂����͂����Ȃ��B
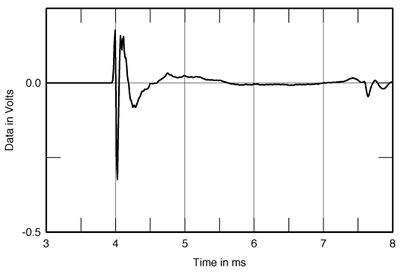
�g�`�̃^�C���R�q�����g�����������m���������ŁA�ł����͂�����̂̓��C���^���ł���B
�Ⴆ�ΑΏƓI��2��1960�N��̃��C�����������
�@�s�[�^�[�C�|�[�����}���[�̓��{����1967
�@�W�F�[���Y�E�u���E���̃_���X����1968
�O�҂�3�l�̃t�H�[�N�e�������}�C�N3�{�Ř^���������^���B
��҂̓I�P���݂̍ŋ�JB's��ڂ����ς����^������敨���B
���Ƃ���1960�N��̃��C���^���͉��ꊴ���ӎ����Ă��炸
�}�C�N�̉���PA�Ŋg������@�\����Ƃ��Ă��邽��
���̃��}�X�^�[�̓��C�����̉��ꊴ����ō���Ă���B
�ƌ����Ă��A���ꂾ���i�ʂ̍����܂Ŏ����Ă����̂ɂ�
�����̌o���ł͓���A�X�S�r�̃G���W�j�A���Ή����Ă���B
�A�i���O����̕ҏW�Z�p�ł͂����ƎG�ȊC���Ո����ɂȂ������낤�B
����ł����ꊴ���Ń��m�����Œ�����
���̃e�[�v�Ɏc���Ă��镑���̃p�t�H�[�}���X�̌������Ɉ��|�����B
�t�H�[�N�e�����Ƃ����ƁA��т��т̃������s�[�X�Ƃ������o����
�Ȃ��̋Ȃł��������b�N�ɒʂ���u���[�W�[�ȉ̂���
�����Ă�ق����O���O���ڂ܂����������Ȃقǂł���B
��̉ԂƂ����Ă��A�O����̂��̂͌��\�g�Q�g�Q�������C���h��������
�F���Z���ڂʼn������猩�Ă��ڗ����������邪
�ނ炪�t�H�[�N��ʂ��ē`�������l�Ԃ̐����͂ɉ��߂ċC�t���B
������ł��邾�������̊ϋq�Ƀ��b�Z�[�W��`���悤�Ƃ��邽��
�����ŋN���Ă���M�C���ߐڃ}�C�N�����܂��߂炦�Ă����B
�t�@���N�̒鉤�̂ق��́A2�g�̃h�����ƃx�[�X�̊拭���������
�Ƃ�����1���ԋ߂����m�炸�ɒ@��������t�@���L�[���Ɉ��|�����B
�A������r�[�g�������̃h���͂ɏI�n�����A�u���[�X���[�̃J���t�[�f��̂悤��
������荜���Ԃ��荇���悤�Ȕ��͂Œ���ł���B
���̂Ƃ����Ƀo���h�����̘r�O�̐����̂ق���JB�̑��݂������Ă���
�����炭���̔��M���C������������ɂȂ����̂́A���̌�ɂ�������������
JB���o���h�����o�[����ĉ��ق������߂��Ǝv����B
���łȂ̂ŊC���Ղ̐��E��`����
�ŏ��̊C���Ղƌ�����{�u�E�f�B�����̒n�����I���W�i���e�[�v��
Ampex 601��602�Ƃ��������^��ǃe�[�v���R�[�_�[��
�{�[�J�������X�v�����O�G�R�[�̕t���^��
�}�C�N���̋@�ނ��܂�PP&M�̎莝�����番���Ă�������Ƃ����B
https://museumofmagneticsoundrecording.org/images/R2R/Ampex602and6022Manual.pdf
�^�����g����65~10,000Hz�܂ł�AM�K�i���t�H���[���Ă�����
�����ȉ����̓��C�����^�ȂǂŐ��E�I�Ɏg�p����Ă����B
����̕t���i�Ƃ������y�A�ɂȂ��Ă�̂�620�A���v�t�X�s�[�J�[��
JBL�����J�X�^�}�C�Y����20cm�t�������W���g�������B
�����Visaton FR6.5�́A�����\�ȃI�[�f�B�I���i���Ɣj�]���鉹���ł�
�S�̂̐g�̏䂪���܂����܂�S�n�悳��̌����邱�Ƃ��ł���B ����ɉ��̍ד��֓����
���F�����F�b�g�̉��U���C���ɂȂ���1970�}�N�V�Y�E�J���U�X�V�e�B�̐��^��
�E�H�[�z���E�t�@�~���[�̃x���������j���\�j�[���J�Z�b�g���R�[�_�[�Ŏ��^�����B
�����J�Z�b�g�e�[�v�Ń��F�����F�b�g�ƒǂ����������o�[�g�E�N���C���ɔ��
�őO�ȂŘ^�����^���͑N�x�����{����
�t�����[���[�������g�̎O��̐_��Ɋ܂܂�Ă������Ƃ��[���ł��鉹�����B
���Ȃ݂ɂ���2��̓|�����C�h �C���X�^���g�J�����A�x�����n�E�G�� 8mm�J����
�Ƃ������Ƃ��낤���B���݂ł͂����̋@�\�̓X�}�z�ɑS�������Ă���B
�Ƃ���ŁA���߂ăt�������W�����m�����Œ��������F�����F�b�g�̃��C����
�����}�C�N�Ř^�������̉��ߊ���������
�o���h�Ɗϋq�̋����̋߂��A���̓V��̒Ⴓ�Ƃ�
�ӊO�ȏ������������Ă���̂�����B
�_�E�����[�h���֘A���恄��
���Ȃ݂Ƀ��o�[�g�E�N���C���̃e�[�v��
���F�����F�b�g�����f�B�A������ߏo����ė��Q�̗��ɏo�Ă��������̂��̂�
���̎����̃��C��������ԗ��������̂Ƃ��āA���߂Đ��ɖ₤�����̂������B
�������I�t�}�C�N�Ř^���Ēቹ�̎c�����R����Ŕ���Ă��邤��
�e�[�v���g�̎��C���������A������u�[�g���O�ł��ň��ɑ�������̂��B
���̎�̂��͍̂����I�[�f�B�I�ł͑S���������Ē��������Ȃ��̂���
����ƂăJ�Z�b�g���R�[�_�[�t����8cm�t�������W�ł��F�����܂܂ł���B
���̎�̘^���ł̓^�C���R�q�����g�����̗D�z���N���ɕ\��
Visaton FR6.5�̃G�b�W�̌������g�`�Đ���
�����������Ř^���̃O���[�h�A�b�v���ʂ����Ă����B
����LP�Ĕ̂̍L�����݂����A������y���ɗǂ����ʂ��o���鎩�M�͂���B
���ꂾ���I�[�f�B�I�@��̑I��͑���Ǝv���B
1960�N��̃��C���Ղɂ́A��Ŋϋq�̊������I�[�o�[�_�u����
������U���C���^�������\�����[�X�������
�X�g�[���Y��1966�N�K�b�g�E�C�t�E���[�E�E�H�E�C�b�g���g�͂��̓T�^��
�o���h�����o�[���F�߂Ă��Ȃ��A�����̃u�[�g���O�Ƃ�������ȑ��݂��B
�i�ŋ߂ɂȂ��ăW���j�X�E�W���v�����̃`�[�v�E�X�������������ƒm�����j
�Ƃ���ł��̘^���́A�����ł����̈������R�[�h�̑㖼����������
���̃��R�[�h�����{�Ŕ������ꂽ���̓��C���^�����̂��̂�������
���b�N���Ă���ȂɌ�����������_�[�I�I�ȃm���𖣂������i�炵���j�B
���ہAGS�̃U�E�^�C�K�[�X�����g�̖ڕW���X�g�[���Y�ɂ����̂�
���̃A���o�������Ă̂��Ƃ������B
���A���߂�CD�Œ����Ă݂�ƁA���̓t�������W�ł͎~�߂��ꂸ
�W�F���Z��30cm�őR���Ă悤�₭�^��������Ƃ����������B
������肩�Ƃ����ƁA�h�����ƃx�[�X�����m����Ԃŋ��肵��
���[�����O�X�g�[���Y�̖��O�ʂ�̃c���̂߂��ē]���藎�����
�t�������W�ł͏d�������炸�ɏ����R���Ă���悤�ɂȂ�B
30cm�܂ō~�낷�ƁA�l�Ԃ̏d�����炢�̔��͂ɂȂ��Ă���B
����ȏ�d�����ƁA���x�͓]���炸�Ƀh���ƍ\���銴���ł��������Ȃ��B
�����ቹ���̘^���𗿗�����ɂ��A�F�X�Ǝ�i��������̂��B
���b�N�ɂ�����X�e���I�^���̔��W�́A�}�W�J���~�X�e���[�c�A�[�ȑO�ɂ�
�t�B���E�X�y�N�^�[���E�H���E�I�u�E�T�E���h��ł��o�����ۂ�
�u�e�B�[���Y�̂��߂̃��[�O�i�[���̃|�P�b�g�E�V���t�H�j�[�v�ƕ\�����Ă�����
�o�C���C�g�j�Ռ���̂悤�ȏd�w�I�ŃJ���X�}�I�ȃT�E���h��ژ_��ł����B
���ۂɂ͓����̎�҂��悭�s���Ă��������ă��X�j���O���l�������
���m�����Ń|�P�b�g�ɓ���g�у��W�I�ł��f���鉹���������Ǝv���B

�����艹���K�͂̑傫�����̂̓W���[�N�{�b�N�X��
50~100���W�q�̏��Ǝ{�݂ł��\���ȉ��ʂł������B


����ŃE�H�[���E�I�u�E�T�E���h�̏����̍�i�Q���݂��
�_���X�z�[���̉������̂��̂�������Ă�����̂�����
�W���[�N�{�b�N�X�ł̑̌��̂���ɐ��ڂ�����
���y�̃p�[�\�i�����𐄐i�����悤�ɂ�������B


�܂�ƒ�ł̉��y�ӏ܂̋��ɓI�ȃS�[����
�R���T�[�g�z�[���̔�����߂ƒ�`�����̂��B �����g�����m���������̟B�ɕ��������čl�����̂�
�W�q�͂Ƃ����R���T�[�g�̖��͂��䂪���ɂ��悤�Ƃ���~�]����
���y��������P2P�̊W�ɖ߂��Ȃ����Ƃ����v���������B
�܂�A�䂪�ƂɃA�[�`�X�g�������ĉ��t���Ă��炤�B
���ꂪ���ɂ��ґ�ł���B
�����Čl�̎v�����l�ւƓ`���I�[�f�B�I�݂̍����
�����炩�Ɉ��̍����̃V�`���G�[�V�����łȂ���Ȃ�Ȃ��B
�ǂ����̃h���}�̂悤�Ɂu�V�ɂ܃V�F�[���v�Ƒ吨�̂Ȃ��ŋ��Ԃ̂ł͂Ȃ�
�l���l�ɓ`���������Ƃ�b���̂͏�Ƀ��m�����ł���B
�A���[�i��z�[������Ȃ��ڂ̑O�ʼn��t�Ȃ�S���Ȃ肵�Ă��炢�������
�j�A�t�B�[���h�ł������
�Ԋu�����߂čĐ�����悵
���^2way�̃j�A�t�B�[���h�͎v���Ă�ȏ�ɉ��ꊴ�̏�ߑ���
����̕��͋C�ʼn��t�]���̑唼�����܂��Ă��܂��B
���ꂾ���c�C�[�^�[�̃p���X�����s����������Ă���
�ǂ����Ă������Ɏ����s���Ă��璆��ȉ��̉����悤�ɂȂ�B
�܂�Vistaton FR6.5�̂悤�ȃt�������W�Ń��m����������������
����̎x�z����y����藣���Ē������Ƃ��K�v���B
���Ɨm�y�̘b���肵�Ă������ǁA
Jensen��Visaton�͏��a�̗w����������������B
��{�A�����A�N�h�C���炢�̃A�����J���̂ق���
�̂̃A�C�h���A���̉̎�̕\��f���Ă���B
���{�̗̉w�Ȃ̘^���X�^�W�I�ɂ�
1980�N��܂ŃI�[���g�[��5c���u����Ă����B
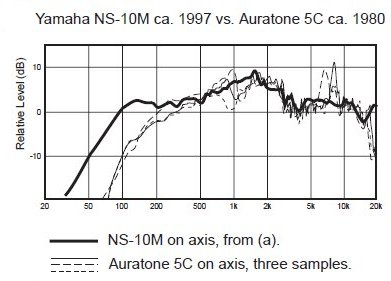
�e�����j���~�L�V���O�̎嗬�ɂȂ��Ă�����ނ������Ƃ�����
���x�̓��m���������p�Ƃ��Đ����c�����B
�����͂܂����m�����̃��W�J�Z�A�L�������ł̎����҂�
���R�[�h�̔��̗L�͂Ȍ������������̂�
�����Œ����f���̂��Ȃ��y�Ȃ͉҂��Ȃ��Ƃ������f�������B
�ŋ߂܂����ڂ𗁂т�悤�ɂȂ����̂�
�p�\�R����e���r�ł̎��������獷���ʂ�
�o�����X���������^2way�����ł͓���Ȃ�������ƌ�����B
https://umbrella-company.jp/contents/auratone-5c-review-abrir/ ���ǁA���������������Ƃ�����
1980�N��܂ł̗̉w�Ȃ̓��m�����Œ����đ��v����
���m�����Œ����Ă����y�Ȃ̃R�A�ȕ������`���B
�V���O���o�[�W�����̃~�b�N�X�̐l�C���������̂�
������͖{�Ƃ��Ɣ��邾���̐����͂����邩�炾�Ǝv���B
���������Ή������ׂ���I�ɂ���ƁE�E�E
�̗w�Ȃ̐^�ł̓V���O���Ղ̃~�b�N�X��
�V���O���ՃR���N�V������CD���Ă݂�
�����ȃX�e���I�Œ����Ă������W�������G�����ڗ���
CD���W�J�Z�Œ����Ă����ڂŌ��Ă���悤�ʼn������Ⴄ
�����̉��Ø^�ł̓��m�����Ńo�����X�`�F�b�N���Ă��炵��
���m�����Œ����Ɣ��͂�����A���̍��̃e���r�̉f����������ł���
�E�E�E�Ƃ����킯�ŁA�V���O���Ղ̓��m�����Œ����Ƃ����I
���Ȃ݂Ɏ����̃��m��������
���j�b�g�̐����N�㏇�ňȉ��̂Ƃ���
�p�e�E�}���R�j�[�Ё@Westminster�i�}�O�l�e�B�b�N�^�j
STENTORIAN JUNIOR+���ʃo�b�t��
JBL D130+��^�o�X���t���{Altec 802+511B
�G���{�C SP8B�{�o���l�b�g��
�p�C�I�j�A PE-16M�{�W���o�X���t��
Micro Solution Type-S�i5cm�t�������W�j
Jensen C12R+��ʉ�����{�c�C�[�^�[5���
Jensen C6V+���^�o�X���t���i���s��j
Visaton FR6.5+��ʉ����
�����̉��Ø^�ł�~���m�����Œ����Ɣ��͂�����
�܂ł̋ɂ͐F�X�Ǝ��s���낪��������
�V�i�Ő�������A�����Ŏ�ɓ���₷�����j�b�g���g����
���l�������ł������ȃ��m�������u���ł���悤�ɂȂ����B
���Ȃ݂Ƀ��C���g�����X��
AT&T KS8614
PEERLESS 15356
UTC C2080
�pLissen Hypernik Transformer
�ȂǂȂǎ����Ă݂���
���ǁA�T���X�C�g�����X ST-17A�Ɏ��܂��Ă���B
�ŋ߂̓R�[���c�C�[�^�[�ɑウ����
�T���X�C�g�����X ST-78�̂ق��������������̂�
������ɂ��悤�ƍl���n�߂Ă���B
�A���v�͓����T�u�V�X�e���Ƃ��ĊJ�n�����̂�
���������ʂ̂��̂ɕς���Ă���B
45�A71A�AVT-25�����ւ��\�ȃ��m�����^��ǃA���v
EL84�V���O��3���A���v
���f�W�A��Lepai LP-2020A
�f���I�� PMA-1500RE
�X�s�[�J�[�A�A���v�A���C���g�����X�Ɨl�X�ȑg�����i�����j��������
5�N���x�Ō���ɃV�X�e���ɒH�蒅�����B
http://cent20audio.html.xdomain.jp/Audio-108.html#Hi-Fi

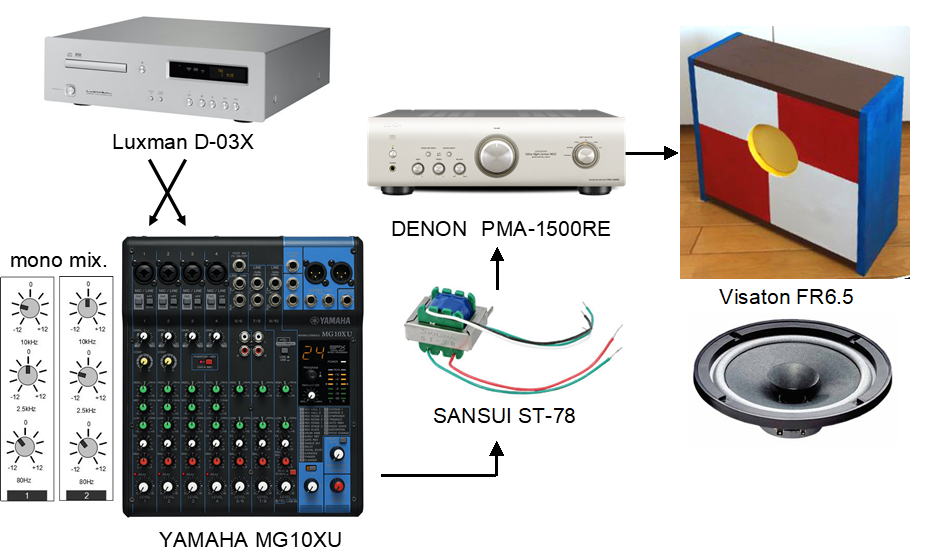
���ǁA���W�J�Z�̉����O���[�h�A�b�v�����邱�Ƃ��ړI����������
����ȏ�̐��ʂ�����ꂽ�Ǝ����ł͎v���Ă�B ���W�J�Z�̉��Ƃ������̂����������������^���Ƃ���
�V���K�[�x�C�u�u�\���O�Y�v�������悤�B
�V���K�[�x�C�u�̗B��̃A���o����
���r��̃i�C�A�K�����R�[�h�̏����̂��̂�
�s������y�ϓI�ɉ̂����u�₩�ȃ��b�N��
�V�e�B�|�b�v�Ƃ������̂����߂Đ��ɒm�炵�߂��ƌ����悤�B
���́A��������f���e�[�v�ȉ��Ɲ������ꂽ�^���i����
�K���[�W�o���h�I�Ȃ�����������Ƃ�����������
���̌��c�V�e�B�|�b�v��{���ɑu�₩�ɒ�����
�I�[�f�B�I���u�Ƃ����̂����܂�v�������Ȃ��B
����AVisaton FR6.5��Jensen C12R�Ȃǂ�
���m�����E�X�s�[�J�[��g�Ƃ��ɋC�t�����̂�
�ǂ����������5kHz�t�߂ɏo�郊���M���O���A�N�Z���g�ɂ����
���ɑu�������o�āA�{�[�J�������肪�o�銴�����B
���Ƃ����Ē��܂ł������背�X�|���X���~��Ă���̂�
�����Ń��Y���̉����̋����������o�����X������̂��Ǝv���B
�����ЂƂ̃��W�I���̉��́A�����݂䂫�u�V���O���Y�v�ł���B
������f�N�m���ɒ��킵���䗐�S�̍��͂��Ă���
����ȑO�̘^���́A���}�X�^�[���Ȃ��܂܂̃����W�̋�����
������̗L�������Ƃ����A�����A��̂��銴��������B
����ŏ��a���̃��\���\�����A�肾�����������Ă��邩�Ƃ�����
�W�F���Z���̂悤�ȃA�����J���ȃe�C�X�g�Ŏx�����
�����̃L�����A�E�[�}���̉����̂̂悤�ɕ������邩��s�v�c���B
���s�I�œł̂��鏗����������̂����邾���Ǝv�����낤��
���ʂ̒j�ǂ��������{�^�t���Ƃ��������錾�Ȃ̂��B
���ꂾ���c�̂��鐺�A�z�Ƃ������t�g��������Ƃ����Ƃ��B
���Ȃ݂Ƀ��}�n�����ŃL���L���Ƀ��}�X�^�[�����̂�
���ؖ����̃t�@�[�X�g�A���o���i1973�j��
��L��2���������ƐV���������ɕ�������B
�A�C�h���̗w�ɖ����ꂪ�������A������V�e�B�|�b�v�̑O�����
���ɃX�|�[�c�ɖZ�������q�吶�̋��̂悤�Ȃ��̂��B
����������n���ĂȂ����オ�܂��t���Ă����Ȃ���������������B
�����̓���̂��A1980�N�O��̉��̂�
���R�[�h��܂�̗w��܂𑍂Ȃ߂��Ă����ɂ��Ă�
�����Ə�������Ę^�����ꂽ�Ƃ͎v���Ȃ�
�A�C�h���̎�Ȃ݂̎��]�ԑ��Ƃ������̂ł́H�Ǝv���B
�ΐ삳���u�Ìy�C���E�~�i�F�v�̓A�C�h���H�����猈�ʂ���
�R���Ղ���Ԃł̎��^�ŁA�u���̂���ȁv�ȂǂƔ�ׂ��
���̌�܂��߂ɉ̂̏C�s�ɗ���Ƃ��f����B
����I�u�M�S�v�́A���łɃx�e�����̎�Ȃ̂���
�����ė}�����A�����W�Ŏ⛌�����o���Ă���̂�
��͂�V�������n�Ɍ������Ƃ��̕s����Ȋ�����
�t���܂Ƃ��̂ł���B
����͎R���S�b�u�������������v�̃S�[�W���X���Ɣ�ׂ��
���S�̔����Œ��A�����W�̈Ⴂ������₷���B
�ł��A���Ɏc���Ă�̂͂��̃A�����W�B���ɕs�v�c���B
�ŁAVisaton��Jesnen�̐����́A���������I�[�f�B�I�f�����Ȃ��A�����W�ł�
�K���̐��̕\��ɏœ_�ĂāA�S�̂̃o�����X������Ȃ����Ƃ��B
���ʂ𑝂��Ă��o�����X������ăr�b�O�}�E�X�ɂȂ�Ȃ��̂�
��{�I�ȃ^�C���R�q�����g�������f���ɐ����Ă��邩�炾�Ǝv���B
CD���A���v�����������^�C���R�q�����g�͕���Ȃ���
�X�s�[�J�[�������l�b�g���[�N��H�ňʑ����˂����B
���ꂪ���̒��̃f�t�H���g�ƌ���������Ȃ̂��낤��
���W�I�p�̃~�b�N�X�͉��ꊴ�ł͌떂�����Ȃ��̂��B
�������g�̑̌��ł�����
���W�J�Z�̉������\����ɂ͌��\�ȘJ�͂�����B
�t�������W�̎��͑�^�z�[���Ƃ��������Ȃ̂��B
���̗������ǂ����琶�܂�邩�Ƃ����ƁA�{�[�J����̍��̋����ł���B
�Ⴆ�A�A���e�b�N�̏ꍇ��10cm��405A�A20cm��755E�Ȃ�
��菬�������a�ł��{�[�J�����S�̃T�E���h�|���V�[�͕ς��Ȃ��B
�N�����O�t�B�����̃I�C���_�C���ƃR�A�L�V�����ɂ��Ă����l���B
�A
�ߋ��ɒ����S�j���e���r�p�X�s�[�J�[�ɂ���
2�K�Ŗ炵�Ă���̂�1�K�Œ����Ă��A���̐��ƊԈႤ�ƕ]�����B
1960�N��̘b�Ȃ̂ŁA����肸���Ɨ��h�ȑ傫����������
������2way�X�s�[�J�[��������O�������B
�����1970�N��̃��W�J�Z�ł������p����Ă���
AM�����R���p�`�Ƃ͂����A�ȉ��̂悤�ȍ\���������B

����̃X�e���I���u�̓p���_�C���V�t�g����������
�X�e���I�̃X�C�[�g�X�|�b�g�̊O�ɏo��ƃo�����X�������B
�p���X�g�̂Ȃ��Â��^���ł͋P���������B
�c�C�[�^�[�̉��ɉߓx�ɂԂ牺�����Ă���Ƃ�����
150~2,000Hz�̃{�[�J���悪�Ȃ�������ɂ����B �ߍ��悤�₭1980�N��̘^�������m�����Œ����C�ɂȂ����B�G�R�[�Ƀ��\�[�X���������X�b�L�������B
Jesnen�����������ɂȂ��Ƃ̂��Ƃő҂��ڂ������B
�o���オ�����犴�z�������Ă�������
�u���m�����v�́umonaural�v������ŁA�u�Ў��ŕ����v�����`�ł��B
�V���O���`�����l���̉����V�X�e���≹���t�H�[�}�b�g�A�I�[�f�B�I�M���́A�u���m�t�H�j�b�N�v�܂��́u���m�v�ƌĂԕ����A����������Ȃ��Ă悢�ł���B
���m���������Ȃ���������̎ʐ^���݂��
�߉����璮���Ă���̂�����B
���ʂ��璮���悤�ɂȂ����̂�
�e���r���o������B
���Ȃ݂Ƀg�[�L�[�ł͍L���X�N���[����
���������N���Ȃ����߂̕��ցB
>>227
3���ڂ̃K�[���Y�O���[�v�͒N�H >>233
���ȃ��X
�摜��������
�U���l�b�c�炵�� ���[�h�{�[�J���̓t�B���X�y�N�^�[�̉ł炵��
�E�H�[���I�u�T�E���h��››208�ɂ���悤��
�g�у��W�I�������Ă��Ē�����
���E�h�ɋ����悤�ɂ��Ă����B
�|�P�b�g�̈Ӗ���ǂݔ����
�����ȕ��Ƃ���̂͊ԈႢ�B
��~��AJensen C12R�������ז���Ƃ́B
�W���[�N�{�b�N�X�̃��y�A���T�C�g����
�A���j�R��P12R
�}�O�l�b�g��������C12Q
�Ƃ������ɏオ���Ă邯�ǎ����ĂȂ��B
���ʂȂ獂���Ȃق��������\�Ȃ��ǂˁB
�~�L�T�[�͓��������Bjensen�͖����͂��Ȃ��B��������ĂȂ�����������|���낤���Ǝv���B
�T���X�C�g�����X�@ST �[17A���Y��Ȃ���~
�g�����X��2��ލw�����Ă���܂��B
�Ⴂ������̂��H�͓�ł��B
�V�C�������������̂Ŕ������C�������Ȃ��̂ōޗ��ɉ����g�����ϑz��
>>1
�����c���{�m�I��Q�҂̕����ɂ��݁u���y��S����y���߂邩�獂�����Ȃ�ėv��Ȃ��v �K�v�Ȃ͍̂���������Ȃ��čD������
>>242
ST17A��ST-78�����i�ł��B�X���傳��ł����傤���H�Ǝ����������Đ\����Ȃ��ł��B ����ɒ�C���s�[�_���X�̃r���e�[�W����
����o���ĂȂ����C�ɂȂ��������ł��B
���C���s�[�_���X�Ŏ��
10kHz�t�߂������オ���ĉ������ĂɂȂ�����
���Ⴂ���邱�Ƃ��悭����܂��B
�ł��E�G�X�M�A���v�̏㐙���Y����
�J�[�g���b�W�̎��̃C���s�[�_���X����������
�g�[���̈Ⴂ���y����ł����Ƃ����̂�
���邠�鎖��̂ЂƂł��B
�ł����ݎg���Ă���visaton�̃R�[���c�C�[�^�[��
5kHz��13kHz�ɋ��������M���O��������
���̃X�e���I�̒�ʊ��͏o���܂���B
����ŁA���m�����ł̉��̍L����͏o���₷��
�W�F���Z���Ƃ����̃^�C�~���O�����ݍ���
�ނ���s���������悤�ł��B
�g�����X�ŐF�t�����邩�X�s�[�J�[�ŏo������
�܂��ɍD�݂̖��ł��B
���͂ނ���������̂ق��őI�т܂����B
���Ȃ݂ɃT���X�C�g�����X�͌����ړ����ł�
ST�|17A��MM�J�[�g���b�W�̂悤�ɗ͊��ƃR�N�̂���T�E���h
ST�|78��FM�����̂悤�ɑu�₩�Ŕ����̂����T�E���h�ł��B
��܂��ȕ��ނł�1960�N��܂ł̘^����ST-17A
1970�N��ȍ~��ST-78�������̂ł���
�ŋ�1980�N�O��̃j���[�~���[�W�b�N��ST-17A�Œ�������
�������A�����J���ȃ��C���h�����O�ʂɏo�Ă���
���炽�߂Ē��������Ă���Ƃ���B
>>246
�X���傳��ł������I�����b�Ɉׂ�܂��B���̍��E�������Ƃ��\�t�@�[�ŐQ�Ȃ��烊�X�j���O�����C�����Ƃ��ŕs���ł������m�����ɋ������N���Ă���܂��B�����Ǝ����̋L���ŏ����߂̂P�̖����Ƀ��N�n���t�������W���c�ɔz�u���ă��m�����Đ�����L���L��ǎ����܂�����F�X����Ă݂����Ȃ荟���ɒH�蒅���܂����B �g�����X�Ƃ��~�L�T�[�ȂǐF�X���̌��Ȃ�œ����ǂ��t���Ȃ��Ȃ�ɖʔ����M���Ă܂��B���̓g�����X�̐ڑ��Ƃ��������P�[�X�ɕt���ĐF�X�l���Ă���܂��B�ǂ��ɂ��l�����Z�܂�Ȃ����͂��q�˂����Ē����܂��̂ŋX�������肢�v���܂��B
���m�����̐Q�Ȃ��玎���͂��͂�`���|��
�N�����g�E�C�[�X�g�E�b�h�A�}�������E�������[��
���L���l�����悵�Ďʐ^�Ɏ��܂��Ă�����B
���ƃg�����X�̓A�[�X�������Ƃ���
����قǃm�C�Y�ɂ͔Y�܂���܂���B
���Ƃ��ƃ��W�I��ł����̂܂܂ł����B
���h���̖�肪�قƂ�ǂł��B
�F
�T���X�C��ST-92�Ń��m�����������������Ȃ肢���Ƃ������ō�
�����X�e���I�ɂ͖߂�Ȃ��A�o�f�B�E�z���[�A�`���b�N�E�x���[���f����f����
�~�L�T�[�����R�X�p�ǂ����������ǂǂ����낤�H
���͂Ƃ����ꃂ�m�����̐S�n�ǂ��ɋC�Â����Ă���Ė{���Ɋ��ӂ��Ă��܂�
�F
�T���X�C��ST-92�Ń��m�����������������Ȃ肢���Ƃ������ō�
�����X�e���I�ɂ͖߂�Ȃ��A�o�f�B�E�z���[�A�`���b�N�E�x���[���f����f����
�~�L�T�[�����R�X�p�ǂ����������ǂǂ����낤�H
���͂Ƃ����ꃂ�m�����̐S�n�ǂ��ɋC�Â����Ă���Ė{���Ɋ��ӂ��Ă��܂�
ST-92�̓T���X�C�g�����X�ł͈�ԍL�ш�ł���
�X�v���b�g����150���Ȃ̂�
����������ƃn�C�オ��X���ɂȂ�Ǝv���܂��B
����̓X�s�[�J�[�Ƃ̑�����������
����ƌ����Ă��Â��^���̓p���X���������Ȃ�
�V�����v�̃X�s�[�J�[�̓p���X�����Ȃ���
�r�[���Ă��������ɂȂ�̂ő����������B
�����Ɏ��C�O�a���₷���g�����X�����܂���
�����g�c�݂Ńp���X���̔{�����o���̂�
�������~�Ŋ��ݍ����̂ł��B
���Ȃ݂ɌÂ��^���ō���s����������
������C�R���C�U�[�Ŏ����グ���
���̎G�����ꏏ�ɃU���U���������ɂȂ�܂��B
���̓_�ł̓g�����X�͊y���ƘA������
�p���X������̂ł����ƃN���A�ł��B
�^��ǂł��I�[�o�[�V���[�g��
�����M���O���ČG����^���܂���
����̎��g����ɏW������̂ő���������܂��B
�̂̃I�[�f�B�I�ł̉����̑g������
�������Đ��ݏo����܂����B
�W�F���Z���g���̎��̂ق���
�R�[���������o�[�u�̂悤�ɔ{�����o���̂�
�ނ��뒆��ł̉����o�����ق����D�܂���
ST-17A�������������悤�ł��B
visaton�̃R�[���c�C�[�^�[��5kHz��13kHz��
�h�C�c�����L�̃����M���O�������Ă���
������}���鑤�ɂ܂�邱�ƂɂȂ�܂��B
�ǂ�����Â��v�̃X�s�[�J�[�Ȃ̂�
���������`���[�j���O���\�Ȃ̂ł��B
���ƃ~�L�T�[�̎g���l�ł���
���i�̃X�s�[�J�[�̉��ʂŒ��̃o�����X���ς��
���ɏd�����U���̃E�[�n�[�������^SP��
�����ʂł͒���t�߂���ቺ����̂�
���̕ӂ̃o�����X����K�v�ł��B
BOSE�͓��d�����g�����l�b�g���[�N��H��
�A�N�e�B�u�ɒ��������グ�Ă��܂����B
�I�}�P�̓��}�n�����̃f�W�^�����o�[�u�ł����ˁB
�J���I�P���ő劈��̂悤�ł���
������40�����炢�̔����̍�����������
�������̃h���C�ȃp���X��
������ɉ��Ə�����^����Ȃ�
�ׂ����ݒ�ł���̂ŕ֗��ł��B
�`���[�i�[CD��̌^�A���v�̃X�s�[�J�[�A�E�g��C���A�E�g��AM������LR2�{�Ƃ��o�͂������ǒP�̃`���[�i�[�̏ꍇ��AM��L���炾���o�͂���܂����H
�`���[�i�[�ł����m����2ch�o�͂ł��B
����AM���W�I�ɓ�������Ȃ�
�p�i�\�j�b�NRF-300BT�Ȃǂ�
���W�I�̂ق����ꖇ���ł��B
�ʏ�̃X�e���I�p�`���[�i�[�̓m�C�Y��������
����𑁂߂ɐ��ă��S���S���܂��B
1990�N��Ƀp�C�I�j�A��AM�����ł�
����⊮�̃`���[�i�[���o���Ă��܂�����
���C�hFM�Ɉڊǂ���\���̂悤�ł��B
AM���W�I�ł܂����Ȃ̂���M���x��
�����̂ق��͓�̎��̂悤�Ɍ����܂��B
����ŗ��j��R�����ƁA���a30�N��ɂ�
Hi-Fi�K�i�ł̍L�ш����������܂����B
���̂Ƃ�����vs�X�[�p�[�_��������
�����������g�ւ̕ϊ������ŏ������Ă��܂��B
�Â��R�����Y��M�@�̃��J�j�J���t�B���^�[�Ȃ�
���ł��ō��̉������ւ��Ă���ƌ����܂���
���͎c�O�Ȃ��畷���y��ł��܂���B
���݂�AM���W�I�́A�l�b�g��FM�ւ̉�������
radiko�̉����K�iAAC48kbps�Ƃ����̂�
�p�\�R�����X�}�z�ł̎����Ƃ����̂�
���r���[�Ŗʓ|�������Ƃ��������ł��B
���������ǂ̎v���Ƃ��Ă�
���̔ԑg����̓f�W�^���őS�Ă��Ȃ��Ă���
�A�b�vto�f�[�g�ȃR���e���c�̎����Ǝv���̂�
�l�b�g�z�M�Ɉڍs�����ق��������I�ł��B
���Ȃ݂Ɏ��̓X�}�z�����m�����o�͂ł��B
��������Ă���Ɖ��̕s�ւ�����܂���B
�X�}�z�̃��m�����o�͂Ŏv���o���܂�����
�C���z���W���b�N��32�����������ׂł��Ȃ��̂�
�T���X�C�g�����XST-92(150���X�v���b�g)�ł�
���m���������ŃI�[�f�B�I�ڑ����A���ł��ˁB
���ƃ��W�I�����Ă��郁�[�J�[��
AM�����ɍ������X�s�[�J�[�ɂ���
���W�J�Z�������ƍ���Ă�����ɔ��
�ꉹ�̃j���A���X�Ȃnj�ނ��Ă���Ɗ�����B
����Jensen�ŋC�t�����̂�
�����ƌÂ�1940�N���PA�Z�p��
���t�ʂ�̍u���X�s�[�`�����ʓI��
�g������T�E���h�f�U�C�����B
���ǂ����Ń��W�I�����ɂ͂ǂ�����Ⴂ���́H�d�g�ł�
>>261
�ǂ������肪�Ƃ��������܂�
�P�̃`���[�i�[�ł����m������2ch�o�͂ł�����
�p�C�I�j�A�̖�����F-777�ł�����ς�1ch�o�͂ł͂Ȃ�2ch�o�͂Ȃ�ł��傤���H
�X�e���I��FM�������n�܂����ȍ~�̃`���[�i�[�͂��̎����炸���ƃ��m������AM�ł�2ch�ɂȂ��Ă��܂�����ł����H
80�N�ゲ��܂ł̃A���v�ɂ͓��͂�1ch�̏ꍇ��2ch�o�͂ɂ��邽�߂̃��m�������[�h�X�C�b�`���t���Ă��܂������`���[�i�[��2ch�Ƃ������Ƃ͂��̃X�C�b�`�͎������m�������R�[�h��p��������ł��傤���H >>266
�u���������������ȎG���ł�����
LED�d���ł��傫�������������邻���ł���
��Ԃ̃m�C�Y���͌g�ѓ��̏[�d��Ƃ��B >>268
���܃��m�����X�C�b�`��
�X�e���I�X�s�[�J�[�̒�����ʂ�
�������邽�߂��ƌ����l�����܂���
���݂̘^���̒�ʊ��͉s���p���X�����Ȃ̂�
�قڃc�C�[�^�[�݂̂ŃR���g���[������܂��̂�
����ȉ��ł͎��g���o�����X�ȊO���Ӗ��ł��B
���m�J�[�g���b�W���z���ŃX�e���I�ɂ�����
�t�ɃX�e���I�J�[�g���b�W���������
�F�X����Ă�݂����ł��B ���Ȃ݂Ɏ��̓X�e���I�v�����C���̑O��
�`�����l���f�o�C�_�[�����܂���
���m����2way�̃}���`�A���v�Ŗ炵�Ă܂��B
�p�b�V�u�l�b�g���[�N�̓d�C�I�ȕ��ׂ��Ȃ�
�X�s�[�J�[�����������Ɩ�܂��B
�}���`�A���v�Ƃ�����
���}�j�A�̂��̂̂悤�Ɍ����܂���
�����̎g���Ă�x�����K�[����
�N���X�I�[�o�[�ƃ��x�������̊ȈՌ^��
����Ɉʑ��̐��t�A�I���E�I�t���t���Ă܂��B
�ނ���Jensen�̂悤�Ȗ��m�̃��j�b�g�ɑ�
�p�b�V�u���i����葵����
�J�b�g���g���C����̂��ʓ|��������
��i�ōςރ`�����f�o�ɂ������炢�ł��B
���ʂ͑���a�ɂ��Ă͍��߂�3.5kHz���x�X�g��
�{�[�J������X�J�b�Əo���Ă��������ł��B
��ʓI��2.5kHz�ȉ��ł͂��ƂȂ�������
�ނ����悪�L�тȂ����Ƃ̕s�����ł�
4kHz�ȏ�������̓X���[�Ŗ炷��
�����悪�s�[�L�[�ŕ�����ꂷ�銴���ł��B